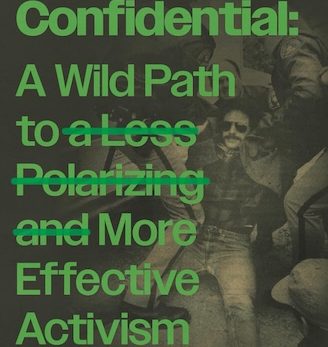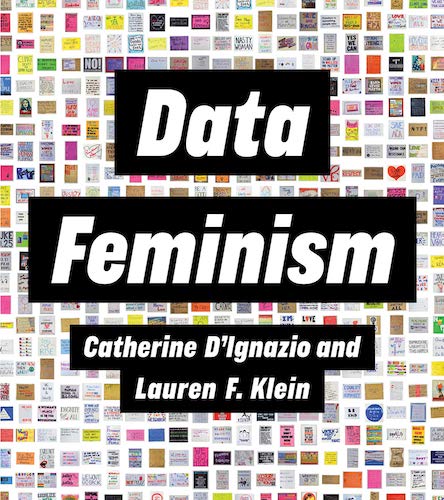Sarah Wynn-Williams著「Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism」
ニュージーランド出身で、ニュージーランド外務省や国連機関で働くなどしていた理想主義的な考えを持つ著者が、世界の人々を繋げる目標を掲げてきたフェイスブックに未来を感じ自ら「フェイスブックの外交官になる」と自分を売り込んでマーク・ザッカーバーグやシェリル・サンドバーグらの側近として働くようになったが、理想を裏切られて同社を追われるまでを綴った自叙伝。後述するようにタイトルはアメリカ文学の代表とされるフランシス・スコット・フィッツジェラルドによる作品「グレート・ギャツビー」から取られており、とても示唆的。
著者が自身をフェイスブックに売り込んだのは、当時「アラブの春」をはじめとする世界各地の民主化運動にツールとして採用され大きな影響力を持つなど、ソーシャルメディアが輝いていた時代。当初ザッカーバーグはフェイスブックはアメリカの企業だからアメリカ以外の国の政府ととくに関わる必要はないと考えていたが、アメリカ国外での成長、そしてそれに伴う広告収入の重みが増していくと同時に、それぞれの国の法律に従うよう求める各国政府との交渉も必要になり、著者の役割が大きくなっていく。なかでも米国に次ぐ第二の巨大市場を擁し、コンテンツの検閲や国内にいるユーザの個人情報へのアクセスを求める中国政府との関係は困難を極めたが、中国政府による人権侵害への加担をするべきではないと主張する著者は、ブッシュ政権で働いていた経験があり共和党保守派と関係の深いジョエル・カプラン公共政策担当副社長とフェイスブック社内で対立していく。
カプランは中国政府に対して自国民によるフェイスブック利用を監視できるツールを提供するとともに、ヘイトやフェイクニュースへの対処を求めるヨーロッパ各国政府に対抗するためにドイツのAfDやフランスの国民戦線(現・国民連合)など極右勢力との関係を深めようとしたり、ブレグジットやトランプの一回目の当選に繋がった右派政治勢力との綿密な協力を行う。いっぽう著者はミャンマーでフェイスブックがロヒンギャやムスリムに対するヘイト拡散に利用されていることやインスタグラムが10代の女の子たちのメンタルヘルスを傷つけているという内部報告に対して対策を取るよう訴えるが、社内では部署が違うと無視される。そうするうちにミャンマーでのヘイトデマの氾濫は何万人もの被害者を出すジェノサイドに発展してしまう。
いっぽう著者が任されたのは、サンドバーグによる著書「Lean In」の会社ぐるみの宣伝のために外国政府を巻き込むことで、ターゲットとされたのが「ウーマノミクス」を掲げていた日本の安倍晋三首相だった。サンドバーグと安倍首相の面会は実現したものの、商品の売り込みみたいなことはできないとして首相側にはサンドバーグの著作と一緒に写真に写ることは拒否されたが、無理やり首相に本を渡して周囲の誰かが慌てて本を首相の手から取り去るまでの瞬間に写真を撮影するというアホみたいな仕事をさせられた。女性のリーダーシップを主張しているサンドバーグが部下の女性たちを押さえつけて自分だけ浮上させようとしていたり、著者が出産のために休職しているのに仕事に呼び出されてしかもその仕事の内容が不十分として低評価を受けたり(産休で休んでいる最中の人に低評価をつけるのは性差別で明らかに違法)、さらにはカプランによるセクハラをなかったことにされたりと、サンドバーグもアレなんだけど、そのサンドバーグも最近ではザッカーバーグによって「うちが血迷ってファクトチェックとかヘイト検閲とかやったのはサンドバーグが無理やりDEI推進したせいで、自分はあんなのやりたくなかったんだ」という感じでマスクやトランプたちに対する言い訳に使われてしまっていたりするけどそれは別の話。あとダボス会議に赤ちゃんを連れて参加した著者勇気あるけど、やっぱりダボス会議は子連れ参加者を一切想定してなかった件。あとザッカーバーグが「フェイスブックがトランプ大統領を生んだというなら自分が立候補すれば当選確実じゃね?」と思ったのかなんなのか突然大統領選挙に出る準備をはじめる話とか、唖然とする内容も。
フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」では、「ケアレス・ピープル(不注意な人たち)」というテーマが出てきて、登場人物はだいたい全員不注意なのだけれど、自分が不注意でも周囲の人が気をつければいい、相手が注意深ければ一人だけ不注意でも事故は起きないのだから、と言い放つ人物も登場する。その結果何人もの登場人物が死ぬことになるのだけれど、不注意な人たちは愛していた相手の葬式にも出席せずに、さっさと帰っていってしまう。「不注意な人たち… かれらは物でも生き物でもぶち壊しにしては、自分の財産だか不注意さだかなんだかに逃げ込んで、自分たちが作った大惨事の後片付けを他人に押し付けてしまう」というフィッツジェラルドの記述はザッカーバーグをはじめとするテック富豪に対するこれ以上にないぴったりとした言葉であり、本書のタイトルに「不注意な人たち」と付けた著者のセンスに感動すら覚える。