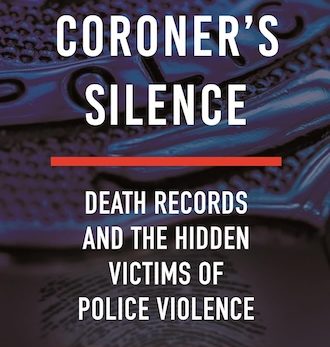Joseph Lee著「Nothing More of This Land: Community, Power, and the Search for Indigenous Identity」
マサチューセッツ州沖にありケネディ家やオバマ家をはじめとする富裕層や有名人の別荘地として知られるマーサズ・ヴィンヤードに祖先からの土地を持つ先住民アークィナ・ワンパノアグの一家に生まれた著者が、メディアでよく見かけるアメリカ西部の先住民部族とは異なる経験をしてきたワンパノアグとして、先住民だけでなく入植者のオランダ人の血を引き中国人と日本人の祖父母を持つ現代のジャーナリストとして、自身のルーツを探るとともに世界各地の先住民たちと関わる自叙伝。
著者は子ども時代、普段はアメリカ本土で学校に通い、休みのたびに家族とともにマーサズ・ヴィンヤードの親族を訪れる生活を送っていた。総父母に中国人と日本人がいるためラストネームも中国系だし、外見的にもアジア人に見えるので典型的なアメリカ先住民とはみなされず、特に裕福だというわけではないのにマーサズ・ヴィンヤードに別荘を持つ裕福な家庭のようなパターン。本人も自分は先住民だというプライドを抱いていたが、メディアで目にするオクラホマやアリゾナ、コロラドなど西部の先住民たちにはあまり共感できず、またかれらが訴える先住民主権もピンと来なかった。やがて一家はマーサズ・ヴィンヤードで観光客向けのお土産物屋を引き継ぐことになり移住すると、先住民であることの意味を考えさせられることに。
アメリカにおける先住民部族の多くはかつて独立国としてアメリカ合衆国と条約を結び、主権の尊重を保証されている。しかし主権国家としての部族の存在が面倒になったアメリカは次第に条約を一方的に破棄し、あるいは無視し、かれらの土地を奪い僻地に強制移住させた。先住民たちを文明化する、との名目のもと、先祖代々受け継いできた共有地を分割し個人の所有物として、借金させたり高い税金を支払えない状況に追い込んで奪うといったことも行われた。先祖代々の土地を税金によって失いかけたハワイ先住民一家の抵抗について書かれたSara Kehaulani Goo著「Kuleana: A Story of Family, Land, and Legacy in Old Hawaiʻi」と同様に、著者の家族もマーサズ・ヴィンヤードが別荘地として有名になり地価が高騰するとともに重くなる税負担に悩まされる。
主権が主権として尊重されなくなり、「インディアン主権」という本来の国家主権より弱いものに変質させられたアメリカで、先住民たちはできるだけ本来の主権を取り戻そうと、また主権の簒奪を止めようと抵抗を続けている。しかし主権について調査をはじめた著者は、部族政府が主権を口実に部族内の民主主義をないがしろにしたり、一部の権力者に利権を集中させている仕組みにも気づき、ただ主権をありがたがるのではなく、それを人々がどう行使するのかにも注目するようになる。また先住民運動をカバーするジャーナリストとして国際的な会議に出席したり、アメリカ本土やアラスカ・ハワイの先住民だけでなく、資源簒奪に抵抗するペルーの先住民や米軍基地に抵抗する琉球の活動家、フィンランドのサミ活動家らと出会い、関係を紡いでいく。
著者を含め、アークィナ・ワンパノアグの過半数は職を求めてマーサズ・ヴィンヤードを離れて生活しており、部族の未来にかかわる会議に参加したくてもできないことが多い。現地に住んでいる人の意見が尊重されるべきだという考えにも一定の合理性があるけれど、しかしそれは土地を離れて生活している若い人たちを部族から遠ざけ、自分たちの未来を先細りさせることにもなりかねない。ほかの先住民部族にはアメリカ政府が押し付けたブラッド・クアンタム(血液定量制)を導入しているところが多く、世代が進み先住民以外の血が入るごとにどんどん先住民の数が減っていくことが運命付けられているが、アークィナ・ワンパノアグではそれがなく、ヨーロッパやアジアの先祖も持つ著者やその子孫が排除されることはない。しかし、それでも部族の未来を守るためには主権をただ守るのではなく、それが公正に行使されるように働きかけ続ける必要性を著者は訴える。