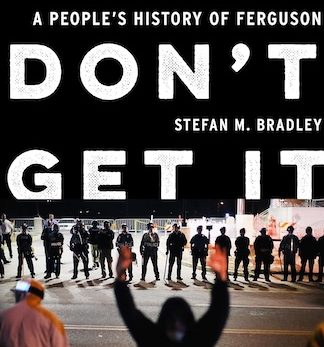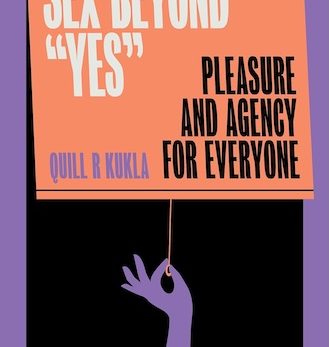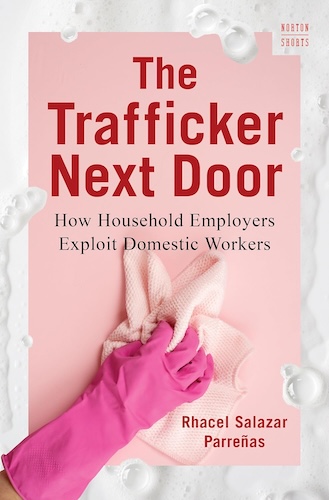
Rhacel Salazar Parreñas著「The Trafficker Next Door: How Household Employers Exploit Domestic Workers」
アメリカ国務省によって性的人身取引の温床とされた日本のいわゆるフィリピンパブにホステスとして潜入し、アメリカ政府の主張の過ちと実際に起きている労働搾取の仕組みについて「Illicit Flirtations: Labor, Migration, and Sex Trafficking in Tokyo」にまとめて以来、世界中をまわり人身取引や労働搾取の現場を調査してきた社会学者が、欧米だけでなく香港、ドバイ、シンガポールなどで働く家庭内労働者(ドメスティックワーカー)の搾取とそれを生み出す環境について書いた本。
人身取引というと犯罪組織が女性を誘拐してきて売春させるといった性的人身取引が注目を集めがちだが、実際にその大半は労働力の搾取。なかでも家庭内労働者の被害はその大きな部分を占めているが、それを実際に行っているのは犯罪組織などではなく欧米やアジア・中東の裕福な一般人たち。一部の地域で今も残る、貧しい子どもを裕福な人に預けて家事をさせるかわりに教育を受けさせたり、親戚のなかで貧しい女性を家政婦として引き取るといった文化や、家事をとおした奉仕を女性の生きがいとする価値観にくわえ、移民を厳しく規制する法制度により極端に弱い立場に置かれた労働者たち、そして「彼女たちがもといた環境よりは良いから」と彼女たちを善意で救済しているつもりでその弱い立場に付け入れ搾取する雇用者たちについて本書は伝える。
第一章はフィリピン系アメリカ人ジャーナリストAlex Tizon氏が死後にThe Atlantic誌に発表し話題を呼んだエッセイ「My Family’s Slave(わたしの家族の奴隷)」を中心に、アメリカで働く移民家庭内労働者たちがどのように扱われているか論じる。Tizon氏の両親はフィリピン出身で、外交官だった父親は家事労働をするための使用人として遠い親戚の女性を連れてきたが、その後Tizon氏の一家がアメリカでの居住権を取得したいっぽう、彼女は法的立場を失い非正規移民となる。両親はその後離婚するが、彼女は母親に引き取られ、休みなく家事労働を続けるが、給料は与えられずフィリピンにいる家族との連絡を取ることもできない状態におかれた。彼女に育てられたTizon氏は、母親の死後その女性を引き取り、彼女が亡くなるまで給料を払って彼女を雇い、また彼女が故郷を訪問することを手助けした。
Tizon氏は記事の中で、彼女が長年無償労働をさせられていた一家の奴隷だったと認めつつ、それでもアメリカ人が考えるような奴隷制とは異なり、フィリピンの伝統に根ざした比較的人道的な奴隷制であり、自分自身を彼女に対して償いを行った倫理的な人物として描いていた。2017年に記事が発表されるとフィリピン系アメリカ人コミュニティを中心に大きな論争が巻き起こり、彼女が奴隷として扱われたというのはフィリピン文化への無理解とレイシズムに基づくのではないか、という意見がある一方、Tizon氏は償いを行ったというが生涯の奉仕に対する報酬としてはまったく足りず、また大人になったかれ自身も彼女の弱みに付け入れて搾取していたのではないか、という意見も聞かれた。
これは当時わたしが実際に目撃した話なんだけど、Tizon氏の一家がかつて住んでいたシアトルのフィリピン人コミュニティでは、実際に一家を知っていた人も多く、またTizon氏の一家と同じように本国から家庭内労働者を連れてきて無償かほぼ無償で働かせてきた家庭も少なくなかったことから、あまり大っぴらに認めたくない事実を掘り起こされ困惑するような反応とともに、こうした件を奴隷制として扱うことは人間を文字通り財産として扱っていた黒人奴隷制があったアメリカでは誤解を呼ぶので不適切だという反発が広がった。なかには、普段は人身取引に反対する活動をしているフィリピン人のリーダーまでもが、この件に関してはフィリピン文化における伝統的な相互扶助や弱者救済の一種であり批判するなと言ってたのを聞いたけど、覚えてるからなてめーら。と同時に、わたしの周囲のフィリピン系二世・三世以降の若い人たちには、この記事をきっかけにコミュニティ内で見かけたことはあるけれど家族とどういう関係なのか分からなかった家庭内労働者の女性たちの存在をはっきり理解し、ショックを受けた人もいた。
このような極端な労働搾取が横行する背景には、移民労働者に対する厳しい規制や人身取引被害者への支援の欠如がある。Tizon氏を育ててくれた女性が一家の支配を離れ自由になろうとしても、頼れる人もいないし、非正規移民となってしまった彼女は無職でフィリピンに強制送還されるだけ。フィリピンで露頭に迷うくらいなら寝る場所も食事も与えられる一家のもとに留まったほうがマシだし、家事労働に励むことで自分の役割を果たし、それなりに自分の居場所も守ってきた。こうした事態に対してアメリカ政府は彼女がより良い条件で働けるように支援するのではなく、そもそも彼女のような人を排除するような移民規制によって対処しており、それが彼女のような被害者をさらに追い詰めている。日本のフィリピンパブで働くフィリピン人女性たちについて著者が書いた「Illicit Flirtations」でも書かれているように、アメリカ国務省の圧力によってフィリピン人女性の日本への入国が厳しく制限された際も、ブローカーとの偽装結婚など違法に日本に渡航・滞在する女性が増え、かえって彼女たちの日本での法的立場は悪化した。また、多くの女性たちが日本より条件が悪く、さらに法的保護の少ない国へと出稼ぎに行った。
欧米が入国管理を厳しくしたことで締め出された家事労働者たちは、家事労働者の流入を認めている香港・シンガポール・ドバイなどに渡ることになるが、これらの国や地域も移住労働者の権利を守ってくれるわけではない。むしろ労働許可が厳しく管理され、特定の雇用者との契約を条件に渡航が認められるだけでなく、給料の六ヶ月分をブローカーに経費として支払うよう求められる。彼女たちを雇用する裕福な家庭は給料六ヶ月分に相当する額をブローカーに建て替えて支払い、最初の六ヶ月の給料を労働者に払うかわりにローンの返済という形で回収するが、それはすなわちどんな扱いを受けても六ヶ月間は仕事を続けないと一切給料を受け取れないし、辞めたら借金を背負うことを意味する。約束されていた勤務時間は無視され、携帯電話の使用を制限あるいは禁止され、辞めたいと言っても雇用者がそれを認めない場合は巨額の借金を負ったうえで本国に戻りまたはじめから応募しなおすという状況は、国際法上の人身取引の定義に当てはまっているのだが、たまに問題とされることがあっても個別の雇用者の制度悪用という形で処理される。
人身取引の加害者である雇用家庭は、多くの場合なんの悪意も持たず、むしろ貧しい国の困っている人を救済しているという善意をもって加害行為を行っている。廊下や物置で寝泊まりさせていても路上で暮らすよりはマシだし、マクドナルドが年に一度のご馳走と思えるほど乏しい食生活でも餓死するよりは良い、彼女たちだって本国で失業にあえぐよりはマシだから出稼ぎに出ているわけで、そうした人たちに仕事と衣食住を与えている自分たちは彼女たちの救世主だと考えている。かれらは家庭内労働者たちを家族のように扱っていると言うが、家族という言葉で彼女たちがあくまで労働者であるという事実を覆い隠し、契約上の労働時間や労働条件を無視した酷使を当たり前のように行う。
さまざまな制度や文化が家庭内労働を行う移民や移住労働者たちの権利を脅かしている現状において、家庭労働者を雇う人たちは意識的に人身取引を行わないよう意識しないと、彼女たちの労働を搾取する側にまわってしまう。待機時間を含め拘束時間のすべてに対して地域の標準的な賃金をきちんと支払う、労働時間や休暇を尊重し、時間外労働を依頼する場合は相手の意志を尊重したうえで割り増しした報酬を支払う、拘束時間以外の私的な生活に口を出さない、パスポートを取り上げたりスマホの使用を制限したりしない、など、当たり前のことなのだけれど、家庭内においては子どもが病気になったり突然の訪問客があったりして予定外の労働が発生することがあるし、家族のような存在だという意識もあるせいでつい労働搾取の一線を踏み越えてしまいがち。ブローカーが勧めてくる条件や待遇は労働者が集まる最低限の水準でしかないので、たとえば六ヶ月分の借金を帳消しにして最初の月から賃金をフルで支払うなど、人身取引や労働搾取に加担しないように意識し雇用者としての責任を果たす必要がある。
もちろん個々の雇用者の意識改革で追いつける話ではなく、移住労働者一般を排除するのではなく保護する法制度も必要だし、そもそも労働者が外国への移住を強いられるような経済格差の是正も必須。アメリカでは家庭内労働者組合が各地で(シアトルでも)「家庭内労働者の権利章典」を成立させているように労働者自身の運動も活発となっており、人身取引や労働搾取を無くすためにはそれらの運動を通して労働者の権利を拡充していかなければいけない。現実の政治では、人身取引への対策という名目で移民・移住労働者や性売買をさらに厳しく規制するようなアプローチが取られがちだが、それらは状況を悪化させるだけだ。
ノートン社が出している、日本だと新書に該当するような短い本のシリーズの一冊として本書は出版されていて、正直物足りない。著者はフィリピン人女性を中心に世界各地で働く家庭内労働者たちについての本をほかにもいくつも出しているので、本書で興味を持った方はそれらを探してください。