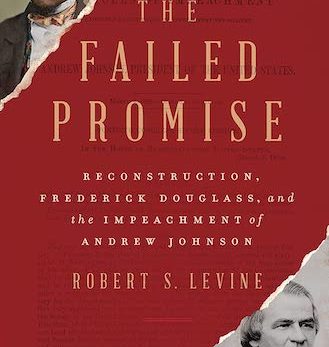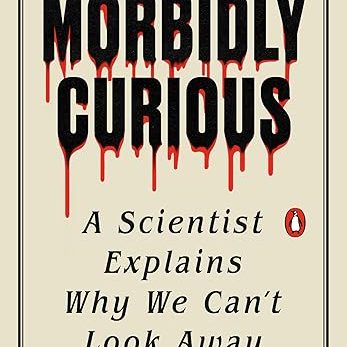Andra Becker著「Get It Out: On the Politics of Hysterectomy」
子宮摘出術の政治についての本。子宮摘出術の発展やその実施の歴史とともに、子宮摘出を受けた、あるいは考えている100人のシス女性、トランス男性、ノンバイナリーの人たちへのインタビューをもとに、子宮摘出術がジェンダーや人種、階級、セクシュアリティをめぐる政治によってどう形作られてきたか論じられる。
子宮摘出術はその名の通り子宮を摘出する外科手術であり、子宮内膜症をはじめとするさまざまな疾患の治療法として、究極的な不妊手術として、優生思想のもと特定の人種や階層の人たちの人口を制御する手法として、そしてトランスジェンダーの人たちが求めるジェンダー肯定医療の一部として行われる。優生学との関わりから明らかなように、その歴史はジェンダーや人種、階級、セクシュアリティの政治と深く結びついている。
ここ数年でニュースで取り上げられ注目された子宮摘出に関する2つの話題を見てもそのことは分かる。一つは子宮内膜症による激痛に苦しんでいた著名な白人女性が子宮摘出を求めるも「あなたはまだ若い、将来子どもが欲しくなったらどうするんだ」と医師によって止められ、何週間ものあいだ余計な苦痛を経験させられた話。もう一つはトランプの移民政策によって国境で拘束された若いラティーノの女性が収容所の中で本人の知らないまま移民局によって子宮摘出を受けさせられていた話。一方は医学的な理由があり本人も望んでいるのに子宮摘出が認められず、もう一方は医学的な理由もなく本人も知らされずに勝手に子宮摘出が行われるという対比は、アメリカの性差別的・人種差別的な医療や移民政策の歴史において繰り返されてきたパターン。妊娠中絶の法的禁止と優生政策による強制的な避妊手術が同時に進行していた時代を思い起こさせる。
産婦人科の歴史が奴隷とされた黒人女性やプエルトリコなど植民地の女性たちを使った人体実験から発展していること、そこで彼女たちは何の知識も与えられず痛み止めすらもらえないまま外科手術の実験台として使い捨てにされてきたことや、その一方で白人女性たちは白人社会の存続のための「産む道具」として扱われ、生理痛や疾患による痛みを訴えても女性は子どもを産むために苦しむのが当然といった扱いを受けてきたこと、そしてこれらのパターンが現代でも形を変えて続いていることが次々と指摘される。妊娠中絶の犯罪化が進む現在のアメリカでは、中絶とは何の関係がない子宮摘出の手術に対しても医者が過度に慎重になっており、医学的な理由があり本人が求めていても「あと子どもが欲しくなるかもしれないから」と手術を認められない白人女性が多くいる。レズビアンを含め出産する意思がまったくない人でも医者はなかなかそれを認めようとしない。
妊娠中絶の問題をめぐっても、中絶する権利を求めてリプロダクティヴ・ライツの運動を起こした白人女性たちに対して、黒人やプエルトリコ人の女性たちは政策的な、あるいは医療による、強制的な避妊手術の禁止や子どもを安全で健康な環境で育てる権利を求めてリプロダクティヴ・ジャスティス運動を起こしてきた。子宮摘出をめぐる議論でも、子宮摘出を受けるのかどうか決める権利は本人にあるというのは当たり前の前提としたうえで、子宮摘出を不当に遠ざけたり、あるいは逆に不当に子宮を摘出するような圧力を生み出す社会的環境を変えていくことが必要。自己決定・自己責任の論理では、もともと恵まれた環境にある白人中流女性の権利しか守れない。
本書はさらに多くのトランス男性やノンバイナリー自認の人たちにもインタビューしている点が興味深い。トランス男性の中にも子宮内膜症など性自認と関係のない医学的な必要性があって子宮摘出を受ける人もいるけれど、そういう人たちにとっても白人であれば疾患から来る身体的苦痛よりジェンダー肯定医療を理由にしたほうが子宮摘出を受けやすいという。本書でインタビューを受けているトランス男性たちは既にホルモン摂取や乳房除去などほかのジェンダー肯定医療を受けている人が多く、その過程においてすでに本人の意思を尊重してくれる医者と出会い、またトランスジェンダーであることを医者に認めさせることに成功していることも関係していそうだけれど、出産するつもりが全くないレズビアンに対して「将来あなたの気が変わるかもしれないから」と説得しようとする医者が、トランス男性に対しては何の心配もせず、また卵子保存などのオプションについて説明しようともしないのは、また別のバイアスがかかっている気もする。トランス男性は男性とみなされて本人の自己決定権が尊重されるのか、それとも守るべき「白人女性」の枠から外れてしまったのか、どっちだろう。まあそもそもインタビューに唐書する多くのトランス男性にとっては、ジェンダー肯定医療としては世間の目線が一変するホルモン摂取や乳房切除のほうが優先度が高く、子宮摘出はそれほど優先されてはいない。
いっぽう、子宮を持って生まれたノンバイナリーの人たちは、疾患の治療のためであれジェンダー肯定医療の一部としてであれ、トランス男性に比べて医者に子宮摘出を考え直すよう説得されることが多く、かれらがトランス男性よりシス女性に近い存在として扱われていることがわかる。そのため子宮摘出を求めるノンバイナリーの人たちの多くは医者の前ではトランス男性としてふるまうこともあるが、医者の偏見を回避して必要とする医療にアクセスするために自分を偽り本心から相談できなくなるのは良いことではない。
このように本書は子宮摘出の歴史を振り返りつつ、医療がどのようにジェンダーや人種・階級・セクシュアリティの政治を反映し、また生み出してきたのか、そしてそれを前提として女性やトランスジェンダー・ノンバイナリーの人たちがどのようにして必要な医療を求め、また望まない医療と闘ってきたのか明らかにしている。多くの人たちへのインタビューを通してどうして子宮摘出を受けたのか、あるいは考えている・いたのか、その傾向とともに例外的な経験にも触れられている点も興味深い。