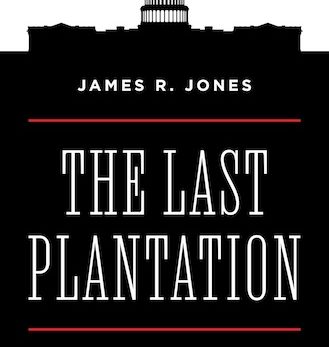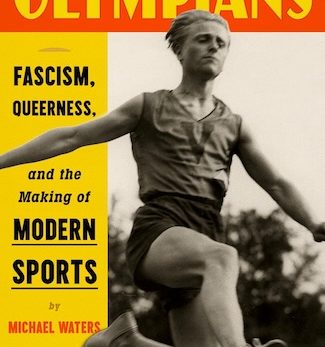Margaret Price著「Crip Spacetime: Access, Failure, and Accountability in Academic Life」
大学に勤務する障害のある300人以上の研究者・教員たちへの聞き取りをもとに、職場としての大学における障害者包摂の仕組みとその限界について論じる本。
ほかの職場と同じく、職場としての大学にも障害者に平等なアクセスを提供するための「合理的配慮」の実施が義務付けられている。この枠組みのなかでは、障害者が経験する障壁やかれらが必要とする補助は常に一定であると想定されているが、実際の障害者たちはその日の体調や天候、ほかにやらなくてはいけない用事、突発的な環境要因などによって日々異なる、必ずしも予測のつかない障壁に直面している。たとえば気温によってその日感じる体の痛みやスタミナが変化したり、エレベータの故障や道路工事による移動ルートの変化、騒音や大気汚染、その他さまざまな状況によってその日できることや必要とする補助は変化する。また、障害者にとって「できること」と「できないこと」のあいだには「無理をすればできるけど、ダメージがたまり数日寝込んだりほかのことができなくなる」などグレイエリアが存在する。
しかし合理的配慮の要請を受けた大学は、それはその人が本当に必要な補助なのか、それともただの甘えなのか、といった基準で補助を与えるかどうか決めようとする。インタビューに応えたある人は、一定以上の度数肩を上げることが困難であることを大学に伝えていたところ、自分がYouTubeにアップロードしていたバケーションの動画を大学の人事部の人が見て、肩があがっているじゃないか、と指摘された。彼女は一切肩が上がらないと言っていたわけではなく、仕事の中で毎日肩を上げることができないとして黒板やホワイトボードに代わる代替テクノロジーの採用を求めていたのだが、障害者たちは日常生活に至るまで疑いの目で監視される。そうした監視や疑いの目は手話通訳やキャプショニング、介助者など比較的コストのかかる補助を必要とする人に対して特に厳しく、仮に介助者の採用が認められても大学ができるだけコストを圧縮しようとした結果、頻繁に必要な時と場所に来なかったり、必要な技能がなかったりする。さらに、大学は合理的配慮を給料や授業の割り当てと同じように交渉の土俵にあげ、双方の主張をすり合わせ歩み寄ることで同意にこぎつけようとするが、障害者にとって合理的配慮の有無はそもそも仕事ができるかどうかという問題であり、それを交渉させられること自体が大きなストレスを生む。
新たな問題として、技術的環境やその設計によるアフォーダンスが激しく変化するなか、仕事をするためにどのような補助が必要とされるのか、当人にだって事前に把握することは難しい。たとえば画面をスワイプする動作は以前は必要ではなかったが、新たに教室に導入される器具にそうした動作が必要とされた結果、それまで不要だった補助が必要になることもある。ソフトウェアのバージョンがアップデートされ、これまであったアクセシビリティ機能が変化したり、それまで有効だった対処法が使えなくなることもある。コロナウイルス・パンデミックによってリモート授業が広く行われるようになり、移動が困難な障害者にとっては便利になったが、相手の顔が必ずしも見えなかったりテキストチャットが行われるなどの変化によってコミュニケーションが困難になった人もいる。
合理的配慮の枠組みは1990年に成立したアメリカ障害者法(ADA)で実現した大きな成果であり、政府の建物や民間の店舗や公共交通機関のアクセスが向上するなど多くの人たちがそれに助けられたことは事実だが、そこで想定されているのは常に一貫した静的な配慮であり、実際の人々が経験している動的な社会的・物理的障壁に対応するには限界がある。大学にとってはコストを押さえたうえで障害のある研究者や教員の生産性を確保することが目的であり、そうしたなか精神的・身体的な無理を重ねすり潰され大学を離れていく多くの障害者たちの個人的な犠牲が無視されている。もちろん当人の人種やジェンダーなどによっても扱いは異なり、白人男性障害者が求める補助はすんなり通るのに女性や非白人、クィアやトランスの障害者たちは「甘えている」とみなされやすい。
現行制度のこうした限界は、健常者社会を前提としたまま、障害者がそこに適応できるように合理的配慮を与えようとする制度的な根幹から生じている。
著者はここでMia Mingusが提唱するアクセス・インティマシーの概念を援用し、健常者社会に障害者を適応させるのではなく、すべての人の尊厳とアクセスが当たり前のものとして共有された社会の構築を主張する。それは、コロナウイルス・パンデミックの初期に確かに広まった、ロックダウンの苦しみを共有しつつお互いの命を守るために責任ある行動を取ろう、という意識を拡大していくことだが、今ではあれだけのパンデミックを経たというのにそうした意識はほとんど消え去り、いまでも命の危険にさらされ続けている障害者や慢性疾患のある人たち、長期的後遺症に悩む人たちが置き去りにされている。
制度の欠陥に対する解決策として社会的・文化的な意識改革を、という主張には、制度的欠陥を放置したまま個人の意識向上に頼り切ってしまうという危険があるが、もちろん著者が主張するのはそういうことではない。もちろん制度的対処は必要だし、そのためには「障害者に合理的配慮をしたほうが生産性が向上して企業や大学の利益になる」といった生産性至上主義的なレトリックを戦略的に使うこともあるし自分も使ったことがあると認めつつ、その限界を超える方法を考えた結果が本書だといえる。前半では研究手法について延々と説明があり、その倫理的かつ真摯な内容に納得がいったのだけれど、ちょっと長いかなあと思ってしまったので、そのあたりは軽くさっと読むのがいいかもしれない。
白人研究者が大半を占める批判的障害学の分野と非白人の女性やノンバイナリー、クィア・トランスの人たちが発展させてきたディスアビリティ・ジャスティスの考えは共通点もあるけれど重要な分岐もあり、そこに触れつつMingusガスやLeah Laksmi Piepzna-Samarasinhaから引用してくるのも良かった。