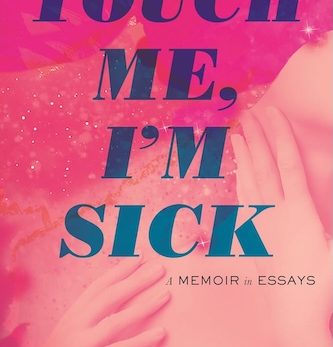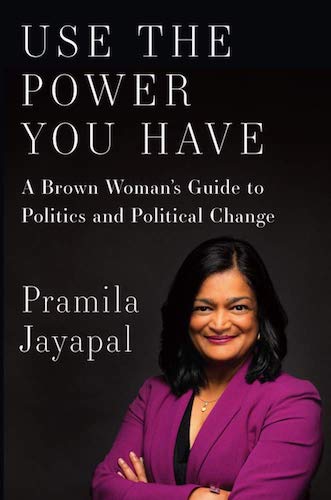Leah Laksmi Piepzna-Samarasinha著「The Future Is Disabled: Prophecies, Love Notes and Mourning Songs」
ディスアビリティ・ジャスティスの活動家として知られるスリランカ系クィア詩人・アーティストがアメリカ西海岸で毎年起きる大規模な森林火災による大気汚染や世界規模で大きな影響を与えたコロナウイルス・パンデミックの経験を経たうえで障害者の未来性を展望するエッセイ集。著者の前著「Care Work: Dreaming Disability Justice」は20年の時間をかけて展開してきた議論を満を持して記した本だったけれども、本書はいま必要なことを速いペースで書いて出版された。
ディスアビリティ・ジャスティスは(戦争で負傷した退役軍人など)白人男性が中心だった伝統的な障害者運動へのオルタナティヴとして、障害のある非白人のクィアやトランスたちが中心になって生み出した運動であり思想だ。既存の社会構造に障害者を適応させる形で障害者の「自立」を目指すのではなく、障害のあるなしに関わらずすべての人はほかの人たちに支えられて生きている事実から出発し、すべての人が必要な支えを受け取り、またお互いを支え合えるような仕組みを指向する。
著者は、コロナウイルス・パンデミックによってはじめて世界全体が「障害を負う」経験をした、と指摘する。それまで「普通」とされてきた生活は送れなくなり、人々はお互いの健康と命を守るためにマスクを付けるなど行動を変えることを強いられた。買い物をするにも自分や周囲の人たちの免疫力の強弱を頭に入れて行動し、ミーティングや授業はリモートに移行。これまで免疫や持病や障害を理由に行動が制限されてきた人たちにとっては、はじめて自分たちの経験が社会に共有され、障害のある生活が「普通」になったばかりか、制限された生活をしてきた人たちの知恵や経験がその他大勢の人たちがパンデミックを生き抜くための教訓になった。
社会はこれを契機に「特定の人たちだけが行動を制限されない社会」に移行することもできたはずだけれど、パンデミックが3年目になった現在、いまだにウイルスの危険は残っているのにせっかく作られたワクチンに対する反対運動や陰謀論は広がり、マスクは隠避され、免疫の弱い人たちを守るためのさまざまな取り組みは終了した。ある公衆衛生専門家はメディアで「最近COVIDで亡くなった人のほとんどは合併症のある人たちだ」として状況の改善を歓迎する発言をしたが、それは「普通の人がCOVIDで亡くなるのは容認できないが、もともと持病や障害がある人が亡くなるのは構わない」という優生主義だとして批判された。Steven W. Thrasher著「The Viral Underclass: The Human Toll When Inequality and Disease Collide」も指摘しているようにコロナウイルスへの対応をめぐっては新たな優生主義がさまざまな形で噴出している。
本書の内容はほかにも、もともと非白人や障害者のコミュニティで行われていてパンデミックのなかで急に注目を集めた民間の相互扶助(ミューチュアルエイド)の考え方が間違ったかたちで主流派社会に取り入れられて新たな「慈善事業」となっていることへの批判や、アートや出版やアカデミアで障害のある人たちが活躍するために必要な条件、気候変動の影響で大規模になり続けている森林火災による大気汚染にディスアビリティ・ジャスティス界隈がどう対応してきたか、そしてそれでも気候変動そのものを止めなければ年々激しくなる危機に対応しきれないこと、フィクションのなかの障害者の未来(優生主義的に排除されていることも多いほか、テクノロジーによる適応がなされているなど)、障害とルッキズムの問題など多岐にわたるけれども、ディスアビリティ・ジャスティスの未来を語りながら本全体に憂鬱なムードが漂うのは、パンデミック初期の2020年5月にステイシー・パーク・ミルバーンさんが亡くなったことが強く関係している。
ステイシー・ミルバーンさんは韓国系アメリカ人でクィアの活動家で、ディスアビリティ・ジャスティスの中心人物の一人。オバマ政権では障害者政策のアドバイザーを務めたほか、バーニー・サンダースの選挙公約のディスアビリティ・ジャスティスの項目を作成したり、共和党がオバマの健康保険改革を廃止しようとした際にそれに抵抗する活動をしし、またネットフリックスで放映された障害のある子どもたちのサマーキャンプについてのドキュメンタリ「Crip Camp」のオンライン展開にも関わった。ミルバーンさんが亡くなった際には#StaceyTaughtUsというハッシュタグで多くの人が彼女から学んだことをシェアした。この数年、著者の周辺ではコロナや自殺などによって何人もの人が亡くなったけれども、ミルバーンさんの死はコミュニティにとって衝撃が強かった。
実はわたし、この本は少し前に読んでいたのだけれど、著者と著者が書いているディスアビリティ・ジャスティス界隈、とくにシアトルのコミュニティの話がわたしに近すぎて、この紹介を書くのを後回しにしてしまっていた。著者は7-8年くらい前にわたしと同時期に東海岸からシアトルに引っ越してきたけれど、今年の初め頃にまた東海岸に引っ越している。わたしたちがシアトルに来たころ、シアトルではディスアビリティ・ジャスティスの運動が活発で、シアトル・ディスアビリティ・ジャスティス・コレクティヴというグループの人たちに歓迎してもらったことをよく覚えている。そのなかにはbillie rainやE.T. Russian、少し離れたオリンピアのNomy Lammら旧ライオットガール出身のアーティストや活動家たちがたくさんいて、当時はとても賑やかだった。でも大きくなりすぎたSDJCは自分の持つ障害への配慮が足りていないとと感じた人たちの不満や個人的な対立などから2016年ころに瓦解して、何人もの人が疎遠になったりほかの街に引っ越したりしていった。
著者がシアトルで暮らした10年近くを振り返ってネガティヴな印象を語っているのは、その最後の数年がコロナウイルス・パンデミックであったことや、パンデミックの数年前から森林火災による大気汚染で持病や障害のある人たちの外出が困難になっていたこと、同じころからクィアが多い地域でプラウド・ボーイズによる暴力的な嫌がらせが頻発して多くのクィアや非白人にとってシアトルの街がより危険になっていたこと(わたしたちの共通の友人で障害のある黒人トランス男性が標的とされたことがある)などを差し引いても、ディスアビリティ・ジャスティスを通して繋がるコミュニティに期待を抱き、裏切られ、そしてその目立つリーダーの一人として批判の標的となったことが関係しているだろう。読んでいて悲しく感じた。著者ともだけれど、SDJCの瓦解、そしてコロナウイルス・パンデミック以来疎遠になっているディスアビリティ・ジャスティス界隈の知り合いたちのことを思い出したので、これをきっかけにまた連絡を取ってみようと思った。