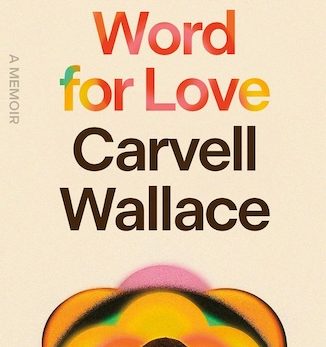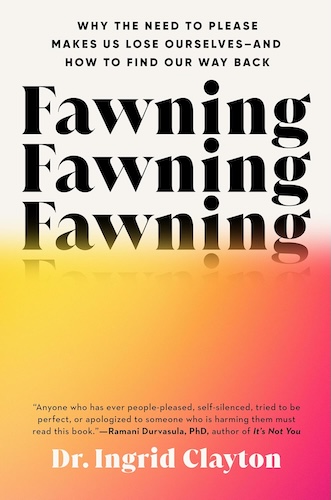
Ingrid Clayton著「Fawning: Why the Need to Please Makes Us Lose Ourselves—and How to Find Our Way Back」
子ども時代の虐待など、抵抗する力を持たないか奪われた状態で長期にわたってトラウマを経験した人が生存のために身につけてしまう、「媚びへつらう」行動とその解消について、自身もサバイバーであり臨床心理士でもある著者が自身の経験とこれまでカウンセリングをしてきたクライアントの経験を通して語る本。
ここで「媚びへつらう」と訳したの言葉はタイトルにもなっている「fawning」という単語。もともと動物が生存を脅かされたときに見せる行動のパターンとして「闘争・逃走反応」(fight or flight response)という言葉が知られていた。戦うにせよ逃げるにせよ、いずれも危険を逃れるために自律神経系のうち交感神経系を活性化させる反応だが、のちに逆に副交感神経系を活性化させ心身の反応を抑えつける(死んだふりをする、立ちすくんだり動かなくなったりする)こともあることが知られるようになり、これがfight、flightに続く三つ目のF「freeze」(立ちすくみ)反応として認識されるようになった。本書がテーマとする「fawn」(媚びへつらい)とは、交感神経系と副交感神経系を同時に活性化させ、平常を装いつつ危険を中和するために相手の歓心を買うための行動を取ることを指し、最近では三つのFに続く第四のFとして議論されている。
四つのFのどれにせよ、危険が迫ったときに生存するための反応であり、人類を含む動物が進化の過程で発達させてきた有用なものであることは確か。しかし長期に及んで日常的な危険や脅威に晒され続けたとき、人は危険が迫ったときだけでなく意識しないまま日常的にこれらの反応を発動させるようになってしまう。これが、突発的な危機を経験した時に発症するPTSD(心的外傷後ストレス障害)とは区別された複雑性PTSDの仕組み。とくに子どもをはじめ、戦ったり逃げたりすることが不可能な環境におかれた人が長期にわたって日常的なトラウマを経験した場合、立ちすくみ反応を身につけてこれといった危険がなくても頻繁に乖離を起こすようになったり、媚びへつらい反応を身につけて危険がないのに常に周囲の人の望みを優先して自分を消すようになってしまうことが多い。
さらに媚びへつらい反応は、社会において周囲の人たちをケアする役割を与えられている女性や、強者の都合を優先せざるを得ない非白人やクィアなどのマイノリティなどにとっては、社会から逸脱せず適応して生き延びるための手段にもなり、トラウマのせいでそうした行動を取っていたとしても「誰にも優しく気配りのきく素晴らしい女性、身の程をわきまえた良いマイノリティ」として歓迎されたりもする。また、周囲に媚びへつらい反応を見せている限りはトラウマに苦しんでいるようには見えないので周囲が被害を見て見ぬふりしていても済むし、有害なポジティヴ思考(Whitney Goodman著「Toxic Positivity: Keeping It Real in a World Obsessed with Being Happy」参照)を脅かすこともないので、全てがうまくいっているように見える。ところが、これからもそうあろうと努力しているうちに、自分を消して犠牲にすることが当たり前になってしまい、次第に原因のわからない苦しみがどんどんと積み重なっていく。著者のカウンセリングを受けに来たクライアントのうち本書で紹介されている人たちは、過去のトラウマに向き合おうと考えたのでもなければ自分を大切にしたいと願って彼女のもとを訪ねたのでもなく、自分が親やパートナーとして不十分なのではないか、もっと周囲のためになれるのではないかと悩んでいた人が多かった、というのは象徴的。
一般の人にはよく知られていないが、トラウマについて、特に複雑性トラウマについてきちんと理解しているカウンセラーはそれほど多くない。本書の主題である、トラウマを根源とした媚びへつらい反応の内面化は一般的なカウンセリングでは「共依存」「八方美人」といった言葉を通して当人の行動が病的なものであるかのように扱われており、セラピーを通して本人の考え方や行動を変えることが治療の目標とされる。しかし著者はこうした反応はサバイバーたちがトラウマを生き延びるために身につけた生存戦略であり、それを解消するためには本人がその原因を理解し、もうこうした生存戦略は必要ない、そのような手段を取らずとも自分は愛されていいのだ、と心から受け入れることが必要だと言う。当然ながら、ドメスティック・バイオレンスの被害を受けているなどの形で現在進行形で生存戦略を必要としている人からそれを奪うことはできないので、まず当人の安全と生活の安定を実現するのは必須。
媚びへつらい反応を捨て去るために有効だとされている心理療法としてEMDRや内的家族システム(IFS)療法を挙げるとともに、最近幻覚剤援用心理療法が注目を集めていることを紹介するあたりは、トラウマ治療業界的にスタンダードで安心の内容。著者自身が自分の「媚びへつらい反応」に向き合い、自身を潰そうとしてくる家族と決別することでそれを克服した壮絶な話とともに、彼女のクライアントたちが自分を取り戻してきた過程についても書かれており、「有害なポジティヴ思考」ではない、癒やしになる希望を感じる。サバイバーやその家族・支援者らに読まれてほしい。