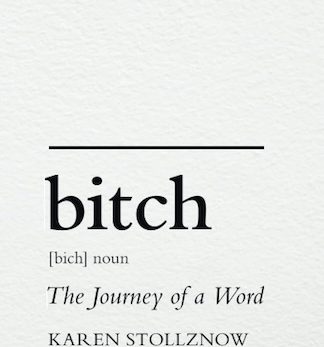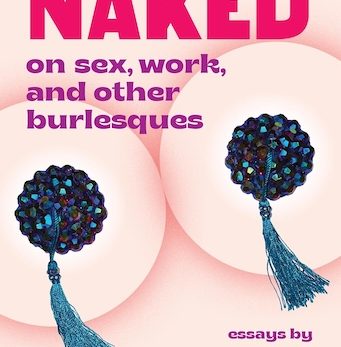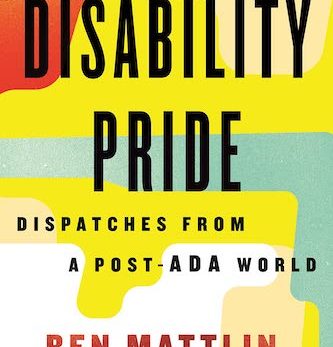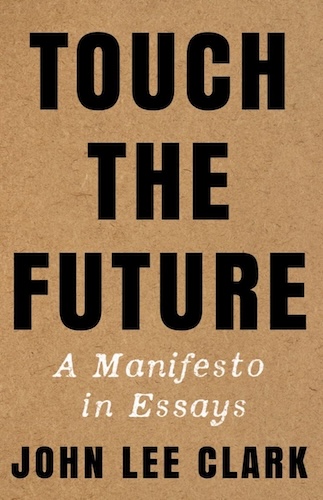
John Lee Clark著「Touch the Future: A Manifesto in Essays」
デフブラインド(DeafBlind、盲ろう者=視覚と聴覚に重度障害のある人)の著者が触知(タクタイル)革命を呼びかける本。ちなみにアメリカではデフブラインドの人たちがコミュニティとして一つの文化であることを主張しているけれど、日本の状況を知らないし日本語の「盲ろう者」がどう使われているか、ほかに良い単語があるのかどうかなど分からないので、ここではカタカナの「デフブラインド」で記述します。
著者はアッシャー症候群を持って生まれたため、生まれつき難聴であり、子どものうちに次第に視力を失っていった。著者の父はデフブラインド、母は難聴であり、著者はアメリカ手話を教わって育つ。デフブラインドであっても全ての人が全く何も見えないわけではないので、多くのデフブラインドの人たちはアメリカ手話を主な対人コミュニケーション手段としているが、しかし目が見えることを前提に作られたアメリカ手話は表情や口の動きなどが重要な意味を持つためデフブラインドの人にとっては分かりづらく、デフブラインドの人同士では会話を成り立たせることが難しい。
そういうなか2007年、シアトルのあるデフブラインドのグループでは、会合に参加するはずだったアメリカ手話の通訳がドタキャンしてしまい、必要に迫られてはっきり見えない同士でなんとかしてアメリカ手話で会話をしようとした結果、手話と物理的な接触を組み合わせることでデフラインド同士で直接コミュニケーションできることに気づいた。これが元に作られたのが、デフブラインドによるデフブラインドのための新しいコミュニケーション言語、プロタクタイルだ。椅子に座って向き合う場合、プロタクタイルでの会話は話す側が手話で表現する一方、聞いている側は片手で話している人の手に触り、もう一方の手を膝や背中、肩などに触れて体全体の動きを追う。また当初はアメリカ手話の語彙を採用していたものの、プロタクタイルが広まるなかで表現はよりデフブラインドの人たちにわかりやすいように変化していった。
デフブラインドの人たちにとってプロタクタイルは、ただ手話を置き換えるものではない。かれらにとって手話はデフブラインド同士でコミュニケーションを取るには使えないものであり、主にはっきり見える通訳とのコミュニケーションに使うものだった。そうした通訳はたとえば学校であったり、病院であったり、自分たちに対する「合理的な配慮」として施設の側によって提供されるもので、視覚や聴覚のある人たちが作った仕組みに自分たちが参加するための手段でしかなかった。それに対してプロタクタイルは、ほかのデフブラインドの人たちと同じ立場で会話するための道具であり、他人が作った仕組みに適応する(させられる)のではなく、自分たちで文化を作り上げる土台となるものだ。
その一例が、プロタクタイル演劇だ。デフブラインドの演者によりデフブラインドの観客に対して提供されるプロタクタイル演劇では、観客が演者と物理的にふれあい、ストーリーを経験する。観客がステージに参加するという意味では「第四の壁を破る」実験的な演劇の一種だという捉え方をする人もいるが、それはこうした演劇の本質ではない。第四の壁以前の話として、これまでデフブラインドの人たちを拒んでいた演劇場の壁を取り払い、デフブラインドの人たちが演劇を鑑賞するには、必然的にこうした手法が必要となっただけの話だ。また、この方式だと一度に一人の観客しか演劇を鑑賞することができないが、場面ごとにスペースを分けて、ベルトコンベア式に観客が場面を移動することで、一度に場面の数だけの観客が鑑賞することができるようなイノベーションも生まれた。
そもそもプロタクタイル以前のアートでは、視力と聴力が当たり前あることを前提として作られた芸術作品をデフブラインドの人たちにどう経験してもらうか、という形でデフブラインドの人たちのインクルージョンが考えられていた。しかし貴重なアートであるほど「実際に手で触れて感じる」というデフブラインドの人にとって有効な鑑賞方法が使えないし、だからといってそのアートを触っても構わない別のもので象徴するとかわけがわからない。またあるものを物理的に象徴する方法にしても、デフブラインドの人の感覚は視覚に過度に頼る他の人たちの感覚とは大きく異なるが、「デフブラインドの人たちにもこの作品を理解して欲しい」と思って善意で象徴を生み出そうとする人は、そもそもデフブラインドの人が世界をどう理解しているのか、分かっていない。デフブラインドの人たちのアートをまず理解しなければアートの翻訳なんてできない。必要なのは「いまある社会」へのアクセスではない、「いまある社会」をより多くの人たちが参加できるように作り替えていくことだ、というのがディスアビリティ・ジャスティスの運動の共通認識。
わたしの住むシアトルはプロタクタイル発祥の地でもあり、デフブラインドコミュニティの活動も活発だと聞いているけれど、わたし自身はこれまで直接関わりがなく、部分的に聞いたことがある話が実際こういうことだったのか、的な発見がたくさんあった。アメリカ手話もプロタクタイルも分からないわたしはプロタクタイル演劇を見ても全く理解できないだろうけれども、それも悪い経験ではないかもしれないので、相談して迷惑でないようならいつか体験してみたい。
そういえば以前、わたしはろう者のための学校・ギャローデッド大学に講演で呼ばれたことがあり、学校のアーキテクチャが全てアメリカ手話でのコミュニケーションを前提とした設計になっていること(広く見通しの良い廊下、低い机など)に気づいたり、アメリカ手話が共通語であり通訳に頼らないと周囲の人たちと会話もできない不便さを経験したことは大切な思い出になっているのだけれど、その時にも「デフブラインドの人たちは苦労している」と聞いていたとおり、本書ではギャローデッドのようなだだっ広い空間がデフブラインドの人にとっては逆に不便なことや、ギャローデッド卒業生にありがちなアメリカ手話のエリート的な表現が分かりにくいことなどが書かれていて、さまざまな障害のある人たちに同時に配慮することの難しさをあらためて痛感した。
視覚や聴覚のある人たちによって作られた社会にデフブラインドの人たちを適合させるのではなく、デフブラインドであることが不利になるような視覚や聴覚を前提とした社会とは異なる社会を設計したらどうなるか、ということを根本から訴えているすごく重要な本。もっとも現実は、ノブやダイヤル・ボタンといったタクタイルなインターフェイスがどんどん排除され「タッチスクリーン」という皮肉にもタッチに頼っている人にとって一番使いにくいデザインが社会に浸透している。