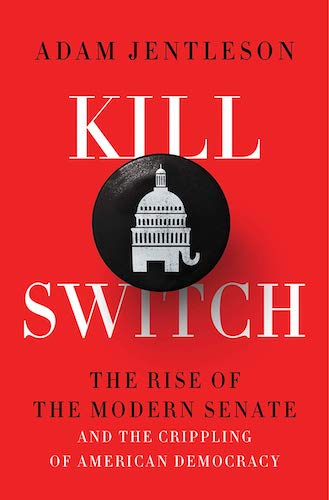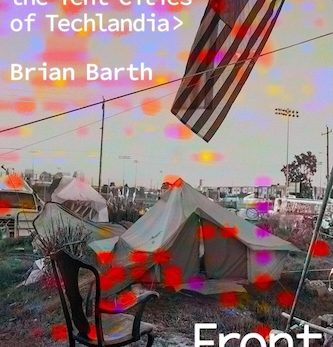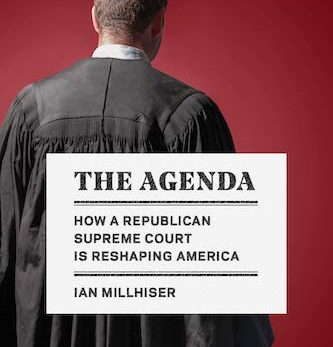Robert B. Reich著「Coming Up Short: A Memoir of My America」
クリントン政権の労働長官にして最近は左派政治インフルエンサーとしても活躍しているロバート・ライシュせんせーの自伝。障害により幼いころから周囲よりかなり身長が低くいじめにあった経験から、人種差別や経済格差のような社会的・構造的ないじめの存在を意識するようになり、あらゆる排除と戦ってきた著者の人生と、その過程で出会ったたくさんの政治家、社会指導者や一般市民らのエピソードが散りばめられている。
子ども時代いじめにあっていた著者は年上の大きな白人少年の庇護を受けることでいじめから逃れたが、のちにその少年は公民権運動を支援するために南部で活動中、現地の警察に捕まり白人至上主義者たちに引き渡され、リンチによって殺害される。いじめが個人間だけで起きるものではなく社会的・構造的にも起こるものであること、ドナルド・トランプに典型的なような、他人をいじめることで権力や財産を独占しようとする人たちが存在することに気づいた著者は、学生運動やユージン・マッカーシーやボビー・ケネディの選挙運動から影響を受け、またのちに大統領夫妻(および大統領候補)となるビル・クリントンとヒラリー・ロダムやのちに超保守派の最高裁判事となるクレランス・トマスらと出会う。
ライシュが最初に注目を集めたのは、1991年に出版した著書「The Work of Nations」がベストセラーになったことがきっかけ。またローズ奨学生として留学先のイギリスで親しくしていたビル・クリントンが1992年の大統領選挙に出ると、早い段階から将来のクリントン政権での役割が噂されていた。「The Work of Nations」はアメリカ経済において知的労働者の役割が大きくなり社会全体の富は増えるいっぽう、肉体労働者やサービス労働者の立場が弱くなり知的労働者との格差が拡大する未来を予見しており、それに備えて教育への支援などによる労働者のリスキリングや格差是正のための再分配強化を主張。大統領に当選したクリントンのスタッフから希望するポジションを聞かれて迷わず労働長官を選んだのは、経済構造の変化に対応するための労働政策を進めたいと考えてのことだった。
しかしクリントン政権内では金融業界出身のロバート・ルービン財務長官やその後任のラリー・サマーズらが経済政策を担当し、北米自由貿易協定(NAFTA)に署名する前に労働者保護の条項を加えるよう求めるなどしたライシュの主張はなかなか通らない。長期的な繁栄と社会の安定のためにライシュが訴える政策はことごとく「財政健全化のため」という理由で潰されるいっぽう、NAFTA締結に続き金融規制緩和や福祉削減などルービンやサマーズの政策が実現していく。政策論争に負けたというよりは、金融業界をはじめとするビジネスによる政治献金によって政策が歪められていったという側面が大きかったが、著者の予測どおり国内の経済格差は拡大し、のちのティーパーティ運動、オキュパイ運動、そしてトランプを当選させたMAGA運動に繋がる大きな分断が民主党政権のもと放置された。
著者はそのあともオバマ大統領にアドバイスをしたり、インターネットメディアで成功した息子に説得されてソーシャルメディアで政治について語る動画をアップして人気を博したり、バーニー・サンダースに惚れ込んだり、トランプやバイデンについて語ったり、マサチューセッツ州知事に立候補して自分が政治家に向いていないことをはっきり理解したり、構造的ないじめが横行するアメリカを救うために具体的な行動を起こしている人たちを紹介して希望を訴えたりして、興味深いことがたくさんあるのだけれど、やっぱり一番面白いのは政治の中枢に関わった労働長官時代の話。閣僚の指名や承認の裏舞台ってそうなってるんだとか、ヒラリーやっぱやべえな(褒め言葉)とか、いろいろ感想はあるのだけれど、クリントンがライシュの話をちゃんと聞いていたらなあと残念。
タイトルの「coming up short」(十分ではなかった)は本人の低身長をかけているとともに、ビル・クリントン、ヒラリー・クリントン、ジョージ・W・ブッシュ、ドナルド・トランプ、アル・ゴア、ニュート・ギングリッチ、クレランス・トマスら著者の世代の指導者たちが構造的ないじめを防ぐことに失敗してきた、あるいは率先していじめを主導あるいは加担してきた、という反省の言葉でもある。第二次世界大戦後に世界一の大国となったアメリカで育ったこの世代は、一般の人々の生活を支え民主主義を守ることに十分に力を果たさなかった。その役割は、来年80歳になる著者にとっては不本意だけれど、今後を生きる若い世代に押し付けることになってしまったと著者は言う。