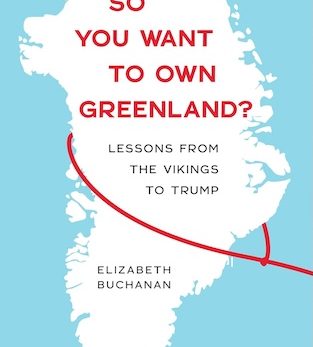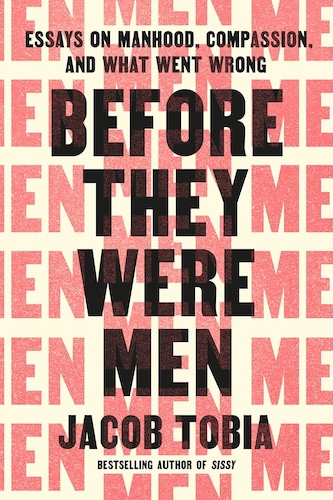
Jacob Tobia著「Before They Were Men: Essays on Manhood, Compassion, and What Went Wrong」
男性として育てられたノンバイナリー自認の著者が、かつては多感な子どもだったのに、いつの間にか規範的な男性性に囚われ、自身と周囲の人たちに害を振りまいている男性たちに共感的に歩み寄り、かれらの解放を目指す本。
女性やクィア・トランスジェンダーやノンバイナリーの人たちはシスヘテロ男性による暴力に晒され、長年かけてようやく勝ち取ってきた権利すら脅かされているが、それでも規範的なジェンダー制度によって自分の自由や権利が制限されていることを知っている、という一点において、大半のシスヘテロ男性よりは解放に近い位置にいる。誰もがかつては子どもだったのに、シスヘテロ男性たちは大人の男性になるために自分の気持ちを押し殺し、国や家族のためという名目で自らの命を削り暴力で物事を解決する考えを内面化する。かれらは暴力や権威主義政治の直接的な被害を受ける女性や子ども、クィアやトランスたちに対しては加害者だが、規範的な男性性はシスヘテロ男性自身たちを信頼に基づいた対等な人間関係から遠ざけ、感情的な充足を阻み、ゲームやギャンブルや薬物や極右権威主義政治への依存に陥らせる。
比喩的にも実際にも冷酷な兵士として生きることを男性たちに強いる規範的男性性の非人道性をもっとも良く理解しているのは、現在進行系で兵士として戦わされている現役兵でも、女性や子どもを支配するために暴力や権威主義に人生を捧げてしまい取り返しがつかない退役兵でもなく、著者のように男性性の押し付けに耐えかねて逃走した脱走兵だと著者は言う。実際著者は、自身が男性性とはっきりと決別したのは、はじめて化粧をしたりドレスやネイルを身に着けた日ではなく、9/11連続多発テロを受けてイラクやアフガニスタンへの侵攻が熱狂的な支持を集める当時のアメリカで、9/11への復習のために人を殺したり自ら死ぬことを拒否し、反戦運動に参加したときだという。
本書には大きく分けて「男性に呼びかける部分」と「フェミニストに呼びかける部分」があるのだけれど、前者については著者がインターネット上のインセルコミュニティに取材してインセルを自認する男性たちの悲しさに歩み寄ろうとしている例からも分かるように、共感的で妥当に思える。シスヘテロ男性はみんな一度はアナルセックスの受け手になるべきだ、という提言とか、一見何言ってんだと思うかもだけれど、自分の体のセンシティヴな部分が他人の身体に侵入される経験をせずに、セックスをする相手女性の気持ちを思いやり寄り添うことができるはずがない、という説明を聞くとすごく納得。フェムな表彰を取り入れたノンバイナリーである著者のことを心配するからこそかれを受け入れるのに時間がかかった父との関係や、その父が交通事故にあったあと著者が感じた理不尽な思いなどを通して、男性たちが抱える問題の深刻さが語られる。
いっぽうフェニにストに呼びかけている部分は、著者自身フェミニストとして「自分たちフェミニストは〜すべきだ」という言い方をしているのだけれど、どうもおかしな内容が多くて気になる。「有害な男性性」という言葉は男性全体を攻撃していると思われて男性たちをさらに敵対的にするだけだから使うなとか、「男性特権」は存在しないと言うんだけど、そこに何か目新しい議論があるわけでなく、ただの普通のアンチフェミニズムの意見を代弁しているだけ。たとえば著者は「男性特権」とされるものについて、他者に対する不当な有利さや支配や暴力を行使する力など「そもそも女性やノンバイナリーの人たちが求めていないもの」や、性暴力を恐れて服装や行動を制限しなくても良いみたいな「男性だけでなくすべての人が当たり前に享受すべきもの」で構成されており、したがってそれらを「特権」と呼ぶのは間違っている、と言うのだけれど、だったらどういうものがあったら特権と呼べるのか明らかではない。しかも著者は、お金持ちの白人女性が世界中のすべての男性よりも抑圧されているなんておかしい、とも言っており、構造的差別や特権について論じるための最低限の認識に達しているようには見えない。
MeToo運動について著者は、加害行為をしたとされる男性を吊し上げるだけに終わってしまいサバイバーが求める公正な解決をもたらさなかった、と言うのだけれど、そうした議論はMeToo運動そのものの中でもフェミニズムでもいくらでも繰り広げられてきたものなのに、著者が独自に考えた新たな視点・既存フェミニズム批判のような扱いになっている。同様に、男の子は子どものうちから軍隊や武器をモチーフにしたエンターテインメントやおもちゃに晒され、暴力で物事を解決する兵士として社会化されている、と言うのだけれど、著者はそれをフェミニズムがかねてから訴えてきたこととしてではなく、これまでフェミニズムによって見過ごされてきた新たな論点として扱う。
しかも困ったことに、著者はたとえばインセルについての議論においてAmia Srinivasan著「The Right to Sex: Feminism in the Twenty-First Century」(放題『セックスする権利』)を参照したりと、ところどころでフェミニズムの文献を引用しており、これだけ内容を一切理解しないまま引用するのすげーな、と思ってしまう。
性暴力加害者の処遇についても著者はアンジェラ・デイヴィスらの著書に言及して、自分は監獄廃止主義者であり加害者に対する報復を司法の目的にすべきではない、と言うのだけれど、収監へのオルタナティウとして著者はかなりの熱をもって「自宅での監禁」を提唱する。しかしMaya Schenwar & Victoria Law著「Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences of Popular Reforms」が詳しく論じているとおり、電子的な監視技術を採用した「自宅監禁」は既にコスト削減(自宅に監禁すれば政府は囚人を収容し食事や衣服、医療などを提供するコストを外部化できる)と民間監視技術業者への利益供与(監視にかかる費用は政府でなく本人負担となる)を目的として年々拡大しており、受刑者だけでなく家族やコミュニティに負担が押し付けられ、また頼れる家族がおらず費用を負担できない人は引き続き刑務所に収監されるという不平等を引き起こしているだけでなく、収監コストが政府にとっての制約でなくなったせいでこれまでより多くの人たちが監禁の刑罰を受ける結果ももたらしている。
もし著者が、そうした批判を踏まえたうえで「自宅での監禁」を主張するなら一つの意見として耳を傾ける意味もあるだろうが、著者はまったくそうした批判を聞いたことがないかのように、監獄廃止主義者を名乗りながら無邪気に「自宅での監禁」を推進する。もし本当にアンジェラ・デイヴィスらの議論を読んでいたら、少なくともこんなに無邪気にデイヴィスらが「改革のための改革」として批判する選択肢を推奨することはなさそうに思うのだけれど。このように著者はフェミニストを名乗り、フェミニストの著作を引用しながらフェミニズムが実際に何を主張しているのか知らないし、監獄廃止主義者を名乗り監獄廃止主義者の著作を引用しながら監獄廃止主義者が実際に何を主張しているのか理解していない。
こうなると、わたしから見てそこそこ妥当に見える「男性に向ける呼びかけ」の部分も、実際のシスヘテロ男性から見れば全然話にならないレベルなのかもしれないと思えてくる。まあ仮に著者の訴えがシスヘテロ男性たちに通じたところで、著者のフェミニズムに関する認識がアンチフェミニストが抱いている偏見や思い込みと大差ないものであることを思うと、それが本当に良いことなのかどうかも自信が持てない。これまで目にしてきた「男性に男性性からの脱却を呼びかける男性(プロ)フェミニスト」の実際の行動があまりにアレなのでかれらにほとんど期待を抱かなくなったわたしだけれど、ノンバイナリーの著者にはそこそこ期待していただけに(そしてなかにはとても良い部分もあるだけに)残念というより無惨。