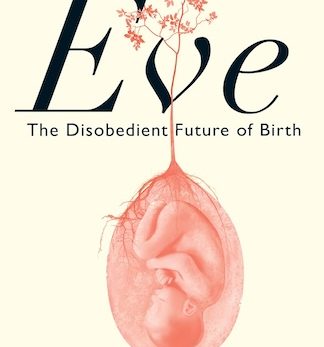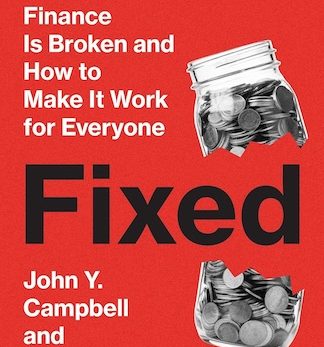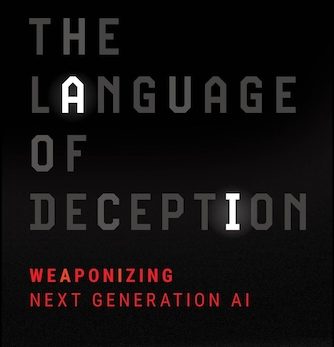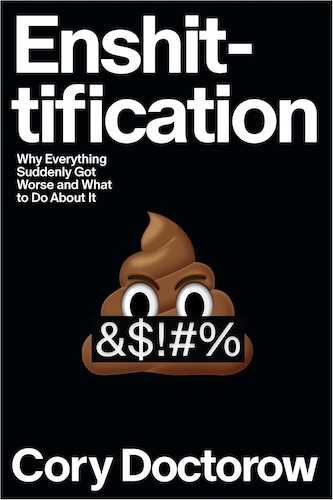
Cory Doctorow著「Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do about It」
かつて人々に愛されていたインターネットサービスや電子機器などが急激に劣化する、日本語では「メタクソ化」と呼ばれる(他にもいくつか訳はあるけどこれが一番いいと思う)enshittificationという現象について、この言葉を考え出した著者がこれまでに論じてきたさまざまなことを一冊にまとめた本。テクノロジー関連のトピックに関心がある読者からするともはや目新しいことはないけれど、これだけ多くの事例をまとめてあると圧巻というか激しいうんざり感を感じる。
本書はフェイスブック、アマゾン、iPhone(iOSプラットフォーム)、ツイッターを例にあげ、メタクソ化のサイクルがどのように起きているのか説明するところからはじまる。これらのプラットフォームは魅力的なサービスや商品を提供することで多くの消費者を集め、その消費者を目当てにサービスや商品を提供する業者がさらに集まる。これらのプラットフォームではベンチャーキャピタルの投資によって短期的な利益を度外視して市場占有を目指す経営戦略が取られているほか、スケールメリットやネットワーク効果による有利な立場を利用することで競合他社を駆逐し、独占的な市場支配が実現する。
こうしたサイクルの最終段階では、プラットフォームに参加している消費者や販売業者から限界まで利益を搾り取るためのシステムの改悪が進められる。一般の消費者にとっては、フェイスブックの使い勝手が悪くても家族や友人、仕事や趣味やアイデンティティに関係した多くの人たちとの繋がりを人質に取られていては簡単にはフェイスブックをやめたり別のソーシャルメディアに移行できない。ツイッターがXになりあれだけオーナーであるイーロン・マスクの号令のもとレイシズムやトランスフォビアが横行するプラットフォームになったのに多くのマイノリティやトランスジェンダーの人たちが離脱しないのは、状況が悪化しているからこそかれらは仲間との繋がりをますます必要としており、全員が申し合わせて一斉に別のプラットフォームに移行する方法がない以上はXに居座るしかないから。
いっぽうプラットフォームはフェイスブックに広告を出す業者やアマゾンで商品を販売する業者にも圧倒的に不利益な条件を押し付けかれらの経営を圧迫するが、拮抗しているプラットフォームがない以上、いまさらフェイスブックへの出稿やアマゾンでの販売をやめたら存在すら認識されなくなるので、泣き寝入りするほかない。こうしてかつて消費者にとっても販売業者にとっても魅力的だったプラットフォームは劣化し、プラットフォームを運営する企業以外の誰にとっても不満だらけのものになってしまう。
メタクソ化が起きる原因の一つはネットワーク効果がはたらくプラットフォームの性質だが、著者はそれだけではないと指摘する。究極的には、わたしたちが政治的な選択により独占禁止法の執行や経営陣の身勝手な方針に抵抗できる労働組合を弱らせたり、著作権制度の拡張により消費者たちが自分たちが購入した製品を自由に使えなくしてきたことに原因がある。要するに「できたから、許されていたから、やった」。まあツイッター/Xの劣化は状況が特殊すぎて独占企業による利益追求だけでは説明が付かないわけだけど、それでも未だにあれだけ影響力を持っているのだから、メタやアップルやグーグルが自分たちは何をやっても安泰だと思い込むのも理にかなっている。
まあ大筋はだいたいこれまで著者が言ってきたことをまとめてあるだけなんだけど、テック労働者たちが労働力不足を背景として経営に口を出すことができたケースや、ゲームエンジンの料金改悪や顧客のデータをAIに学習させようとするデザインソフトの利用規定の改悪が大きな反発を受けて撤回に追い込まれたケースなど、プラットフォーム企業の支配力がかれらが思っていたほど強くなくメタクソ化が抵抗を受けたケースを紹介するなど、興味深い事例も多数。またメタやグーグルと違ってユーザのプライバシーを保護する優等生ぶっているアップルについての記述で、消費者が割高の料金を出せばメタクソ化から逃れられるわけではない、無料のサービスだろうが料金を払おうがそれが可能であればプラットフォームはメタクソ化することを指摘している部分もおもしろかった。enshittificationというキャッチーな言葉を作った著者は偉いけど、それに負けない「メタクソ化」という日本語を作った人も偉い。
本筋とは関係ないけど、最後のまとめの部分で黒人レズビアン詩人・活動家オードリー・ロードの「マスターの道具はマスターの家を解体しない」という言葉を引用して、「いやいや彼女は間違いだ、マスターの道具を使ってこそマスターの家は解体できる」と書いている部分は、彼女の主張をまったく無視したダメすぎな引用。ロードがこの言葉を使ったのは、彼女が活動していた1980年代の白人フェミニストたちが自分たちが考えるところの「女性の解放」を優先して黒人やレズビアンの権利を後回しにするばかりか、人種差別やホモフォビアについての取り組みを排除したり黒人やレズビアンを黙らせようとしていたことを批判する演説でのことで、人種差別やホモフォビアを使って性差別を解体することはできない、というのがその意味。著者は「マスターの道具=プラットフォームやテクノロジー」という解釈から、プラットフォームやテクノロジーを使ってそれらの濫用に抵抗することを主張していると思うんだけど、それならロードの言葉を捻じ曲げて引用する必要はなかった。