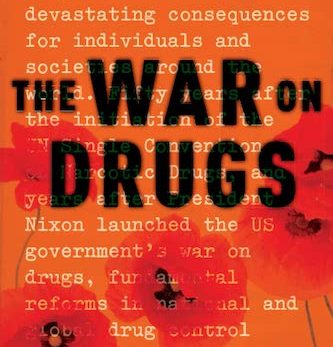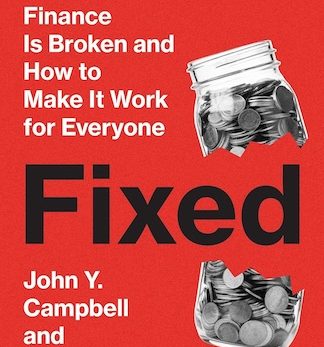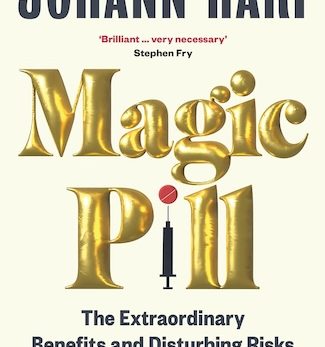Shelley Sella著「Beyond Limits: Stories of Third-Trimester Abortion Care」
アメリカ全国でも数か所でしか行われていない妊娠後期(第三トリメスター)の中絶手術を含め、20年にわたって反中絶派による過激な抗議活動や脅迫、法的妨害を受けながら妊娠中絶を希望する患者に寄り添い中絶を行ってきた医師の自叙伝。
著者はレズビアンで、12歳のころから年の離れた兄による性的虐待を受けるようになった。誰にも相談できず自殺も考えるなか、14歳のときに生理が止まり兄の子どもを妊娠したのではないかとパニックに。結果的に彼女は妊娠しておらず、生理が止まったのはおそらく極度のストレスによるものだったと考えられるのだけれど、そうした経験を経て著者は同じように追い詰められて孤独を感じている女性たちの支援を志す。20代になった彼女は妊娠中絶を受ける患者の心理的サポートをするようになるが、クリニックによっては予算もないなか中絶医療が流れ作業になり患者のケアが十分に行えないことに気づき、クリニックの外で患者に寄り添うことができる助産師に転職する(その過程でのちに結婚するパートナーとも出会う)。
助産師からさらに医師免許を取って産婦人科医になった著者は、全国でも限られたクリニックでしか行われていない妊娠後期の中絶に興味を抱く。妊娠中絶を合法化した1973年のRoe v. Wade判決では妊娠を初期・中期・後期の三つの期間に分け、初期においては原則として中絶の権利が認められ、中期においては胎児を保護しようとする政府の意思とのバランスが必要、そして後期には母体の生命維持など特定の理由を除き胎児の保護が優先される、というフレームワークが採用されたこともあり(このフレームワーク自体は1992年のPlanned Parenthood v. Caseyで破棄された)、後期における中絶医療は特に攻撃に晒されていた。著者はコンファレンスで妊娠後期の中絶手術を行う数少ない医師の一人であるジョージ・ティラー医師と出会い、かれに誘われてロサンゼルスでパートナーとともに住みながら定期的にカンザス州ウィチタにあるティラー医師のクリニックで仕事をすることに。
ティラー医師は女性の権利擁護を公言しており全国的な反妊娠中絶運動の主要なターゲットとされ、クリニックの前にはレジつ各地から抗議者たちが集結しティラー医師やかれのスタッフ・患者たちに罵声を浴びせていた。脅迫や施設への不法侵入が繰り返されたが地元の警察は反中絶団体に訴えられるくらいならティラー医師から訴えられたほうがマシだと見て見ぬふりをし、著者も街を歩いていたりレストランで食事をしているだけで知らない人が近づいてきて脅されたり、妊娠中絶を行ったことで殺人犯として医師会や警察に通報されたりした。ある時期からは空港でタクシーを拾おうとしても乗車拒否されるようになり、遠方から来た患者が泊まるのにちょうどいい近くのホテルもクリニックの患者や関係者の宿泊を拒否されるなど、業務への影響も大きくなる。そして2009年にはティラー医師が反中絶派活動家によって暗殺され、クリニックも閉鎖に追い込まれる。著者はその後、他の医師たちとともに妊娠中絶に対する規制が少ないニューメキシコ州アルバカーキで新たなクリニックをオープンしたが、彼女を弟子として受け入れ技術だけでなく患者との向き合い方までメンターしたティラー医師の影響は大きかった。
妊娠後期に中絶を求める人たちに対して世間は、どうしてそんな後になるまで待ったのだ、と詰問する。少なくとも2022年にDobbs v. Jackson Women’s Health Organization判決で妊娠中絶の権利が剥奪されるまでは、初期の妊娠中絶であればどの州でも認められていたのに、どうしてもっと早く中絶を行わなかったのだ、という意味だ。しかし実際のところ、医療を受ける機会が十分にあり、妊娠を中絶するかどうか決めるための十分な情報もあったにも関わらず、何の理由もなくただじっと妊娠後期になるまで待ったうえで中絶を受けようとする人など一人もいない。彼女たち、かれらは、医療や情報へのアクセスがなかったり妊娠中に事情が変化したり、あるいは未成年だったりDV被害を受けていたりして自分の意思で行動できなかったために、もっと早く中絶することができたら良かったのにやむを得ず妊娠後期の中絶を求めざるを得なくなった人たちだ。患者の多くは自分が妊娠中絶を必要とするまでは宗教的な理由から妊娠中絶に反対していた人たちで、仮に合法であっても実際に中絶を受けることを困難にするさまざまな規制だけでなく、中絶に対するスティグマを内面化していたこと、周囲に望まない妊娠や中絶という選択肢について相談する相手がいなかったこと、そして反中絶派が広めた妊娠中絶についての間違った知識によって、より早い段階で中絶を選択する機会を奪われた人も少なくない。
著者はどういう理由なら中絶が認められるべきかといった序列を否定し、それぞれの患者にそれぞれの事情があり、自分や生まれる可能性のある胎児、そして既に育てている子どもたちにとって最善だと考える決断を下しているのだ、と訴える。ティラー医師が生前よく言っていたように、「女性(患者)は常に医者より賢い」。妊娠後期の中絶を必要としている人たちは初期や中期に中絶にアクセスできる人たちと比べてより深刻な事情があり周囲から孤立している人も多く、彼女たちがお互いの話を聞いて自分だけでないと実感できる環境を提供することも著者は忘れない。中絶手術の翌日著者は、自分の人生を取り戻し、ある人はDV加害者のパートナーと別れることを決め、またある人は次に妊娠したときは胎児への悪影響を心配しなくて良いように飲酒をやめようと決意するなど、それまで何ヶ月ものあいだ悩まされてきた問題が解消しふたたび生きる希望を取り戻した患者たちを目にする。
本書と同じく最近読んだHarrison Browne & Rachel Browne著「Let Us Play: Winning the Battle for Gender Diverse Athletes」は本来はトランスジェンダーの権利に好意的なリベラルな人たちが現実のトランスジェンダー・アスリートたちの経験や実態を知ろうともせずに頭の中で「女性の権利とトランスジェンダーの権利のバランス」という反トランス派による議題設定をもとに考えてヘイトに加担してしていることが指摘されていたが、妊娠後期の中絶についても決して反中絶派ではないリベラルな人たちが実際にどういう人たちがそれを求めているのか、どういう理由があるのか知ろうともしないまま「女性の権利と胎児の権利のバランス」という反中絶派による議題設定をもとに考えかれらを追い詰める施策に加担してしまっている。
ティラー医師に育てられた著者はこんどは自身が後進を育て引退しており、だからこそ本書を出すことができたのだけれど、長年の仕事とともにこの本を書いてくれて本当にありがとうと言いたい。