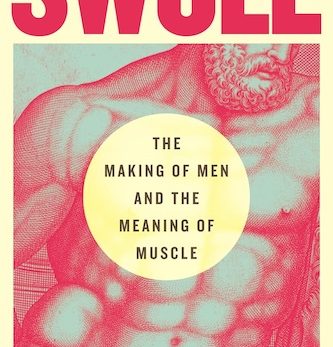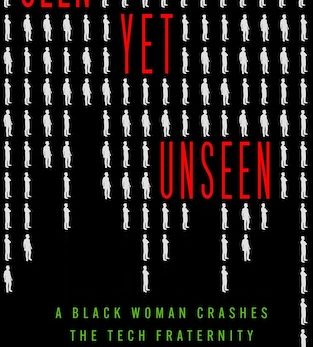Ellen Ruppel Shell著「Slippery Beast: A True Crime Natural History, with Eels」
ぬるぬるしたウナギな本。
ウナギといえばかつて世界で最も多い淡水魚とされたけれどいまでは日本人が食べすぎたせいで絶滅の危機にあるとか、生態が謎すぎて古来から著名な哲学者や科学者を悩ませさまざまなトンデモ説に飛びつかせたとか、そういった話はだいたい本書でも引用されているPatrik Svensson著「The Book of Eels: Our Enduring Fascination with the Most Mysterious Creature in the Natural World」でもう読んで知ってるよ、と思っていたのだけど、さらに研究は進んでいるし、それで不思議な点が解明されるかと思うとさらに疑問が生じてきたりと、ウナギは油断ならない。
著者は別荘があるのか夏のあいだメイン州の森の中で過ごすのだけれど、そこを訪れた著者に近所の住人がいろいろ注意することをおしえてくれるなかで、「池にはたくさんウナギがいるから注意して」と言われる。え、ウナギって噛みつくの?毒あるの?と疑問に思った著者だけど、危険なのはウナギそのものではなく、ウナギの稚魚を狙う密猟者だった。メイン州ではアメリカでほぼ唯一のウナギ稚魚の商業漁業があり、捕まえられた稚魚は中国に送られて養殖場で育てられる。商業的な完全養殖が成功していない現在、ウナギの稚魚は重量あたりキャビアより高い価値が付けられ、したがって密猟・密輸しようとする犯罪組織も後を絶たない。そういう連中に気をつけろ、というのが近所の住人の意図だったけれど、あのメイン州でそんなことが起きているとは。
メイン州といえばロブスターの名産地として有名だけど、先住民のあいだでは古くからウナギが食べられていて、入植してきた白人たちにも「海のゴキブリ」に見えたロブスターよりはウナギが好まれたらしい。20世紀になっても先住民による伝統的なウナギ漁はほそぼそと続いていたけれども、日本から寿司が紹介され、その中でウナギは生の魚に抵抗を感じる人も食べられるネタとして人気に。商業的なチャンスを狙った人たちがウナギ養殖に挑戦するもうまくいかず、世界的にウナギの消費量が増えるとともに稚魚を中国に輸出するビジネスモデルが広がる。政府は資源の枯渇や生態系への悪影響を避けるためにウナギ漁業に免許制を導入し、限られた免許の一部を先住民部族に、残りをクジで分配した。
本の最後にはメイン州では「サラ」というファーストネームだけで通じるウナギ起業家Sara Rademakerさんが登場し、彼女がはじめた会社アメリカン・ウナギについての話が。メイン州の資源であるウナギの稚魚を中国に売るのではなくメイン州でサステイナブルに育てて出荷しよう、という考えではじめられたアメリカン・ウナギは各方面から称賛されているけど、値段がめっちゃ高くて(184gの缶詰1つで6000円近く)いくらサステイナブルなウナギが食べたいわたしでも手が出せないので、良くてブランドとして通用するくらいになって高級レストランで提供されるくらいの未来しか見えない。でもあれがサステイナビリティまで加味したうえでのウナギの本来の値段なんだろうとは思うし、死ぬ前に一度、昔わたしも住んでいたメイン州に行って地元のレストランでアメリカン・ウナギを食べられたらいいかな、くらいに思っておく。
ただまあ、こんなに素敵なウナギの本なのに、著者は「自分はウナギ大好き人間ではない」って書いているんだよね… ウナギについて全然知らなかったけどたまたま調べてみることになっただけで、著者の関心はウナギそのものではなく、学術的にあるいは商業として成り立たせるためにウナギの生態を解明しようと力を尽くしてきた人たちに寄せられていて、ウナギ好きというか水棲の生きもの好きで本を手に取ったわたしにとっては著者に裏切られた気分。まあウナギの謎生態についての新発見や生態系におけるウナギのはたらきなどについてもちゃんと紹介してくれたからおもしろかったけど。