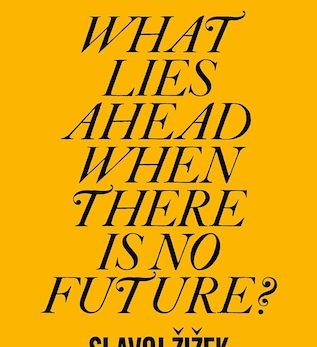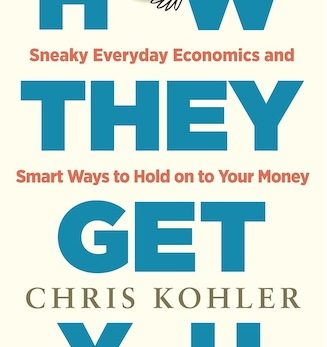Owen Flanagan著「What Is It Like to Be an Addict?: Understanding Substance Abuse」
「心の哲学」の分野で有名な哲学者が、アルコールや抗不安剤に依存して大学の講義の合間に研究室でそれらを摂取していた自身の経験とともに、薬物依存とはなにか考える本。
自身の経験をもとに議論を立てるのは、まあ実際のところ哲学者はみんなやっているのにそれに意識的でない人が多いので、哲学者としてはリスキー。しかし著者は、脳科学や医療、社会史とともに、依存症を経験している本人がそれをどう経験しているかという依存症の現象学の必要性を訴え、自身の経験と依存症からの回復を目指す中で出会った人たちの経験にも注目する。
ただし著者自身も認めるとおり、著者は白人男性の大学教授で、依存対象は合法的に入手することができるもの。哲学者ともなれば多少おかしな言動があっても誤魔化せるし、その気になればいつでも医者やカウンセラー、治療プログラムにかかることができるだけでなく、法的な問題が生じたとしても弁護士を雇うことができるという、薬物依存者のなかでは特権的な立場。著者が黒人だったら、大学進学を望めないほど貧しい家庭の出身だったら、とっくの昔に刑務所に入れられているかオーバードースして亡くなっていた可能性は少なくない。
そうした社会的立場にも意識的であるからか、薬物依存とは何なのか、どういう理由で人はそういう状況に陥るのか、どうすれば離脱できるのか、という疑問に対して著者は、なにか一つの回答を出そうとはしない。個人の道徳の欠如であると考える伝統的な価値観に対し、依存症は病気であり倫理的な責任はないとする病理モデルが提唱され、さらに社会的な困窮や疎外、トラウマなどの影響を訴える社会モデルが登場しているが、著者はなにか一つの解釈に基づいてその解決を押し付ける治療や政策がこれまでさんざん失敗してきたことを指摘したうえで、薬物そのものの危険性とそれが使われる社会が生み出す危険、法的な取り締まりが生み出す危険を整理していく。
著者は自らの回復の過程でアルコホーリクス・アノニマスが提唱する12ステップが役に立ったと感じており、12ステップに対するさまざまな批判を取り上げる部分はやや弱い。たとえば研究によると12ステップはほかの治療法と同程度には有効だと書いているが、それは「ほかの治療法も12ステップも同等に有効性は低い」というだけの話なんだけど(被験者をランダムにさまざまな治療法に割り当てるタイプの研究では効果はほぼ確認されていない)そのあたりどうなの。12ステップを自ら選び取り、そこに長年参加している人がアルコールや薬物を辞めるのに成功している事例がたくさんいるのは事実だけれど、生存者バイアスに基づいているし、著者が指摘するとおり12ステップに参加する人たちにはもともと治療を受けなくても大丈夫だった人も多く含まれていると思われる。
著者個人の経験談、そしてそれをもととした考察として読むとそこそこおもしろいんだけど、わたしの周囲にいる、薬物依存のある黒人女性やホームレスの人たちらの経験とはかけ離れているし、著者の言うことはあんまり当てはまらないかなあと思う。まあ著者本人も「そりゃ当てはまらないだろ」と言うとは思うんだけど、この人は脳と心のはたらきについての専門家として講演したり本を出したりできるいっぽう、わたしの周囲の人たちはそんな機会はないので、あんまり著者の発言だけが拡散されるのもつらいというか。