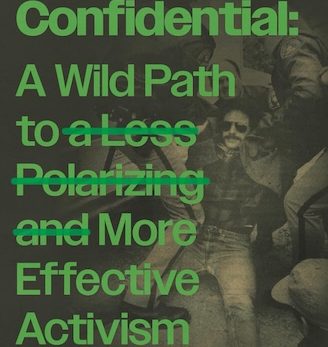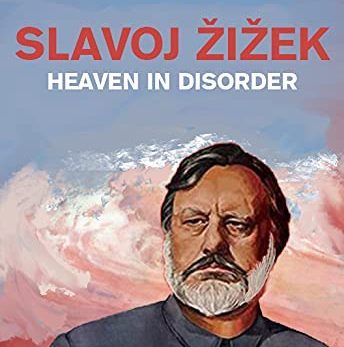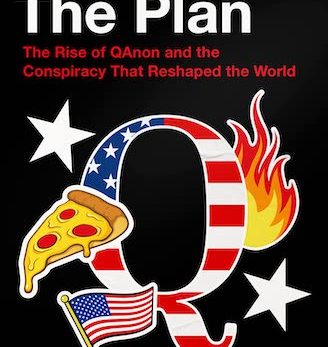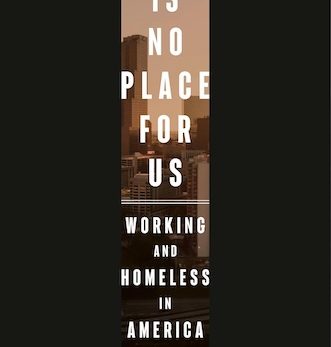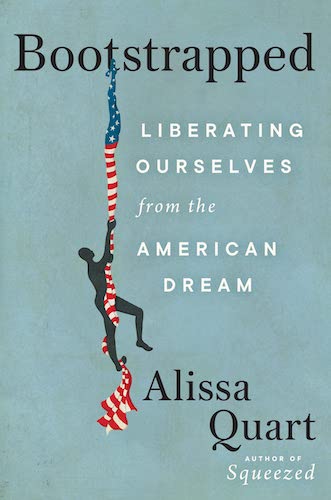
Alissa Quart著「Bootstrapped: Liberating Ourselves from the American Dream」
アメリカ社会の根本的イデオロギーである自己責任主義とアメリカンドリームの理想批判の本。著者は貧困問題について精力的に取材しているジャーナリストで、タイトルに出てくる「ブートストラップ」は靴の後ろの部分にある「つかみ革」のことで、「自分でつかみ革を引っ張って靴を履く」ことから「自力で立ち上がって成功する」という意味の慣用句としてよく使われる。
自己責任論やアメリカンドリームは現実に存在する機会の不平等をふまえない暴論であり、たまたま生まれや運に恵まれて成功した人たちを「全部自分でやった」と傲慢にさせると同時に、そのような生まれや運に恵まれなかった人たちを非難する不公正かつ社会に有害なイデオロギーである、というのは、まあこれまでさんざん議論されてきたので、はじめは本書にもそれほど期待していなかったのだけれど、序盤に書かれているアメリカに自己責任論が広がった文化的な要因とそれらへの容赦のない分析から引き込まれた。
古くはヘンリー・デイヴィッド・ソローが『ウォールデン』で描いた社会から隔絶された森の中での自給自足生活やローラ・インガルス・ワイルダーの『大草原の小さな家』に描かれた西部開拓時代の一家の暮らし、作家の名前がアメリカンドリームの代名詞になるほど貧しい少年が努力によって成功する小説を量産したホレイショ・アルジャー、そして『肩をすくめるアトラス』に代表されるアイン・ランドの作品まで、アメリカの代表的な文学作品の多くにおいては自立を称賛し政府や他者への依存を否定するテーマが繰り返し描かれる。
しかし著者は、それらで描かれた「自立した個人」やその著者たちが実際にはそれほど自立しておらず、黒人奴隷や女性や政府などへの依存が白人特権や男性特権などによって隠されていることを次々と暴き立てる。ソローは実際には周囲の人たちと交流していたばかりか母親に汚れた服を洗濯してもらっていたし、ワイルダーの一家はアメリカ政府が先住民から奪った土地の分配というアメリカ史上最大の富の再分配の恩恵を受けていた。アイン・ランドは晩年、政府の社会保障や公的健康保険を受けた。ホレイショ・アルジャーに至っては、小説の中で年上の裕福な男性に認められることで成功を掴んだ少年の話を書くいっぽう、かれ自身も少年たちを自宅に引き入れて援助していたが、かれは過去に聖職者を目指していたころ二人の少年に対して性的虐待を行ったとして教会を追放されている。
そもそも人間は生まれたときから他者に依存しなければ生きていくことはできない。2020年に起きたコロナウイルス・パンデミックではそのことがこれ以上ないほど明らかになったし、不可視化されてきた他者へのケアやエッセンシャル・ワークを負担させられている女性や貧しい人たちの厳しい境遇が注目された。「母親たちのためのマーシャル・プラン」が提唱され、バイデン大統領のBuild Back Betterアジェンダには出産休暇や育児支援など画期的な内容が盛り込まれたが、マンチン・シネマ両議員の反対によりそれらは実現しなかった。
自己責任論に基づいたアメリカ社会のセーフティネットの欠如は、「ディストピア的セーフティネット」の蔓延をもたらす。本来新たなイノベーションや特別なイベントなどの費用を募るためのクラウドファンディングサイトでは、必要な医療を受けるための患者たちの悲痛の声が日常化し、住居はもちろん恒久的なホームレスシェルターすら整備されないなか特に気温が低い夜に人々が凍死しないための一時的なシェルターが設置される。パンデミックのなか職を失った人たちは食料品のデリバリーなどで生計を立てようとするものの、最低賃金の保証すらなく怪我をしても自己責任とされる。そういうなか、企業はストレスを生みだしている根本的な原因を放置するいっぽう、マインドフルネスの講習などを行いセルフケアを従業員に義務付ける。
そうした現状に対し、著者は新たに立ち上がりつつある、相互依存を前提とした新しいアメリカンドリームに期待を寄せる。それはパンデミックのなか食料の分配からマスクの自作まで一気に認知度を高めたミューチュアル・エイド(相互扶助)の取り組みであり、労働者が運営する協同組合、美術館や有名大学ではなく一般の人たちが恩恵を受けられるような機関に資産の大部分を寄付する一部のお金持ちなど、さまざまなかたちで広まりつつある。それらの取り組みとともに、貧富の差とともに白人特権や男性特権に基づいたブートストラップの神話を解体していく必要がある。