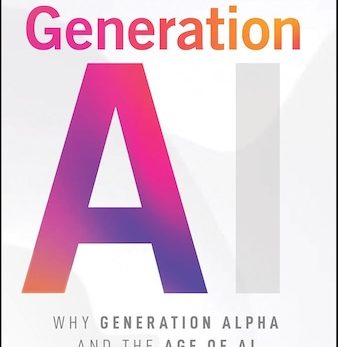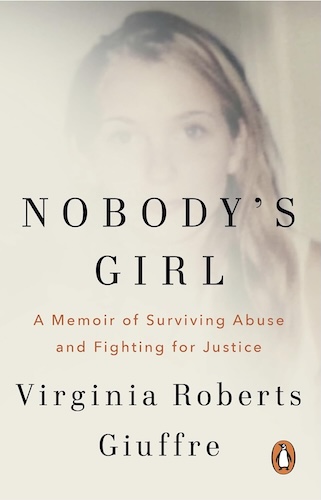
Virginia Roberts Giuffre著「Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice」
ジェフリー・エプスタインとジーレイン・マクスウェルやかれらに繋がる著名人たちによる性暴力と性的人身取引の多数の被害者の一人による自叙伝。著者は今年の4月にさまざまな要因が重なり自殺しており、四年間に渡って彼女を支えてきた協力者のジャーナリストがその状況を説明する導入部を加えたほかは著者が生前に書き終え校了した状態で出版されている。
エプスタインによる若い女性や少女に対する性虐待や性的人身取引については、わたしはあまり報道を見ないようにしてきた。かれの犯罪についての報道がはじまったのはMeToo運動が広まる以前であり性暴力被害者に対するメディアの扱いはいまより圧倒的にひどく、著者も指摘しているように勝手に被害者たちの発言や証言が捻じ曲げられて報道されていたし、エプスタインの交友関係にはビル・クリントンやドナルド・トランプを筆頭に多くの著名人が含まれていたため面白おかしくスキャンダルとして騒がれたり、さらにはさまざまな陰謀論が囁かれたりしており、被害者の生の声を聞き取ることが難しかった。また、性暴力や性的人身取引に対する正しい社会の理解やサバイバーを中心に据えた政策を推進していた立場からしても、エプスタイン事件のような特殊なケースに注目が集まることは、必ずしもより一般的な被害についての理解やそれへの対処には繋がらないという懸念も感じていた。
しかし本書を読むと、エプスタインの財力やそれが可能にする権力へのアクセスという意味では特殊だけれど、著者がマクスウェルとエプスタインの標的とされ逃げ出せなくなる経緯や、そこから自分の人生を取り戻す困難、サバイバーとして告発することで経験したことなどは、エプスタインほど財力も権力もない人たちにより性虐待や性的人身取引の被害を受けた多くのサバイバーたちの経験と共通点が多かった。親からの虐待、不良少女として送られた施設とそこからの脱走、トランプに紹介されアルバイトをはじめたマー・ア・ラーゴでエプスタインに出会うまでに、未成年でありながら複数の大人による虐待や搾取を受けていたことなど、トランプやエプスタイン、あるいは著者を性虐待したアンドリュー王子(テレビ番組で疑惑を否定したけれどそのインタビューで嘘をいくつもついていたことがのちに分かる)や某「元首相」(エプスタインと親しかった元首相といえばイギリスのトニー・ブレアやイスラエルのエフード・バラクが挙げられるが、同時に出版された本書のイギリス版では「首相=プライムミニスター」ではなく「閣僚=ミニスター」と書かれているらしく、何に対する配慮なのか憶測を呼んでいる)という特異な登場人物を除けば多くのサバイバーたちの経験と共通している。
エプスタイン事件に特有の要素だけれど、Lucia Osborne-Crowley著「The Lasting Harm: Witnessing the Trial of Ghislaine Maxwell」(アメリカでは未だに出版されてないの?なんで?)でも書かれていたジーレイン・マクスウェルの役割はやはり重要。はじめて半裸の男性がベッドで待っている部屋に連れてこられた著者がすぐに逃げ出さなかったのは、マクスウェルが同席してマッサージのお手本を見せると言って彼女をコーチングして安心させたからだし、彼女の指導によって本来なら拒んだエプスタインとの接触を「これはマッサージだから」と自分に言い聞かせることができた。著者やその他の少女たちをリクルートしてくるのもマクスウェルが中心だったし、そのうちマクスウェルは著者にも同じようにエプスタインの好みの少女を見繕って勧誘するよう強要したが、当時の状況でほかに選択肢がなかったとはいえ、彼女の言うままに他の少女たちをエプスタインのもとに引き込んでしまった責任を著者はずっと感じることになる。
著者がエプスタインから離れることを決意したのは、エプスタインの子どもを妊娠するよう求められたとき。ただでさえ他の少女たちの勧誘に加担していたことに罪悪感を感じていたなか、子どもの権利を全てエプスタインに渡し母親であることを秘密にするという契約書への署名を求められた著者は、もし自分の子どもが女の子だったら、というおそろしい考えに取り憑かれ、ついに離脱を考える。エプスタインは少女が大人の女性になると興味を失い手放すことが多いので自分もそうなると考え、子どもを作るのはいいけどそのまえに本当のマッサージ師の資格を取りたい、と言った彼女をエプスタインはタイにある有名なタイ式マッサージの学校に送る。そこで著者は彼女のことを受け入れてくれるオーストラリア人の男性と出会い、衝動的に結婚、エプスタインの元には戻らないと宣言する。しばらくエプスタインからは何の連絡もなかったのだけれど、エプスタインに対する捜査がフロリダ州ではじまると、どこでどう連絡先を知ったのか、マクスウェルやエプスタインから捜査に協力しないように脅すかのような連絡が入るように。最初の刑事裁判がエプスタインに対してやけに甘い司法取引で終わると、自分の被害をエプスタインとマクスウェルらに認めさせるため、そしてかれらによるさらなる加害行為を阻止するために著者はその犯罪を告発し、裁判に訴える。
せっかくエプスタインから逃れたのに、著者と一家はメディアによって追い回されあることないこと書かれたり、エプスタインやアンドリュー王子の関係者や私立探偵に脅される。そんな大事に巻き込まれる準備ができていなかった著者は、いくつも戦略的なミスもおかしたし、証言にも細かい部分で記憶違いや意図的に隠したことがあった。家族が危険に晒されたり子どものケアに気を配る余裕がなくなったりして、家族を守るのとエプスタインの責任を問うのとどっちが大事なのだ、と夫に言われたりもした(いやいや妻を含めおめーが守れよ)。本書はそうした間違いについても正面から開示し、サバイバーは完璧ではないこと、完璧なサバイバーしか正義を求めることができないという考えはおかしいことを訴える。
著者はその後、エプスタインによるほかのサバイバーたちとも繋がり、性暴力の被害者を支援するための非営利団体を設立(のちに名前がプロフェッショナルな非営利団体風に変わったけど、わたしは最初に彼女が名付けた「Victims Refuse Silence」という団体名が好き)。エプスタインが二度目の逮捕後、獄中で自殺した(とされているけれど陰謀論もあり、そこそこ他殺の可能性もなくはなさそうな感じ)あと、エプスタインの裁判を担当していた裁判官が被疑者死亡で裁判を即打ち切るのでなく、その前に被害者たちに法廷での発言の機会を与えたのは英断。証言した被害者たちの発言や彼女たちとの別室での会合とその後の繋がりについて書かれた部分は一番心を揺さぶられた。
著者が最後まで隠していたのは、タイで出会った夫による暴力だった。本書を執筆中に暴力はすでにはじまっていたけれど、当時彼女と夫はなんとかやりなおそうと努力していて、原稿のなかでは常に優しく彼女を尊重する夫として描かれていたが、校了後に暴力は悪化し、夫とは別離、著者は自殺するまえにそのことを公開したが本文が変更されることはなく、協力者による導入部で説明されている。著者の自殺の責任のすべてがエプスタインにあるとは言えないし、父親や夫、政界・学界・経済界・芸能界の有力者を含めた彼女を虐待・搾取してきたその他の人たちや、メディアや司法の人たち、その誰の責任とも言えないけれど、かれらが総体として性虐待や性的人身取引を許容し、なんとか生き延びたサバイバーたちを殺しつづける社会を温存しているのは確実。エプスタイン事件の特異性とともに、多くのサバイバーがMeTooを経ても少しずつしか変わらない社会で経験している普遍的な困難を感じた。
なお本書には性虐待の具体的な描写があるほか、著者が物理的な侵害より辛かったという精神的な支配やマニピュレーションの描写や、サバイバーに対する社会の無理解や理不尽な仕打ちの描写があるので、サバイバーの人は調子が良いときにサポートしてくれる人や動物にアクセスできる状態で、体を暖かくして読んでください。