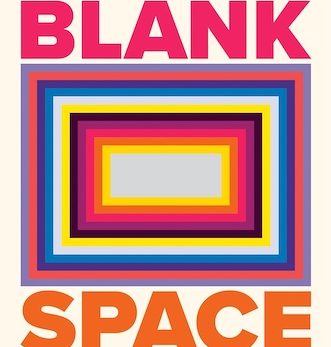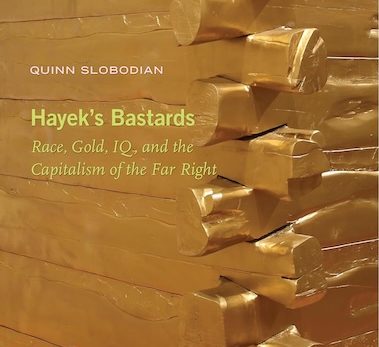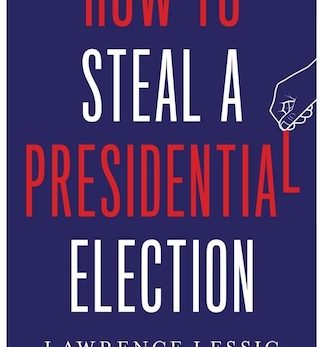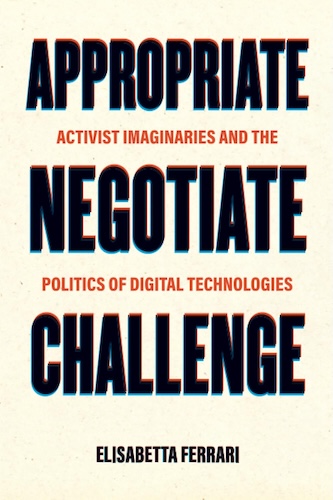
Elisabetta Ferrari著「Appropriate, Negotiate, Challenge: Activist Imaginaries and the Politics of Digital Technologies」
ハンガリー・イタリア・アメリカ(フィラデルフィア)の三カ国の2010年代後半の左派的な社会運動の参加者たちへの調査をもとに、テクノロジーとそれがもたらすイマジナリー(想像性)を社会運動がどう捉えているのか論じる本。タイトルは「盗用、交渉、抵抗」の意味であり、三カ国の運動がそれぞれ三つの異なるパターンに分類されるのかと思いきや、後述するようにそうでなかったりする。
著者が取り上げるテクノロジーのイマジナリーとは、ただ単にこれらの運動がどのようなテクノロジーを使っているか、どのように使っているかというだけの意味ではない。カリフォルニア・イデオロギーと呼ばれシリコンバレーのテック企業に代表されるテクノロジー観、すなわち個人主義・メリトクラシー信仰・技術解決主義などの新自由主義的な想像性に対して、社会運動の側がどのように接するか、どのような想像性を打ち立てているかが本書のテーマとなっている。
イタリアやアメリカの左派運動ではテクノロジー業界の新自由主義に対する否定的な考えかたをする人が多く、しかしソーシャルメディアをはじめとするテクノロジーが生活の重要な一部となっており人々に呼びかけるためにはテクノロジーを利用しない選択肢はないという判断が主流。しかしソーシャルメディアはあくまで人々が運動につながるための入口であって運動そのものではなく、運動はそこでつながった先にあると考えられている。「フェイスブックはテレビみたいなものだ」というイタリアの活動家の発言は、そのテレビが長年にわたってベルルスコーニによって右翼扇動の道具となってきたことを考えると深い。
いっぽう一世代前に共産主義から脱却したばかりであり、新自由主義よりも権威主義的な保守主義による脅威を人々が感じているハンガリーでは、新自由主義は便乗し利用するリソースだと活動家たちにみなされている。しかし本書が主に取り上げているハンガリーの例は2014年のインターネット税反対運動であり、まだBrexitやケンブリッジ・アナリティカの事件によってテクノロジー企業に対するバックラッシュが激しくなる前なので、いまハンガリーで国民的な運動が起きたらその想像性はまた異なるものになる可能性もある。
著者ではもともと、テクノロジーがもたらす想像性に便乗や利用するのではなく拒否する路線についても取り上げるつもりで本書の研究をはじめたのだが、実際のところテクノロジー企業に批判的な活動家たちもその利用が避けられないことは理解しており、全面的に拒絶するパターンは見つからなかったし、あまり必死になって探し出したところでそれは一般的なケースだとは言えなくなるのではないかという考えから、あえて取り上げていない。せいぜい「デモに参加するときは警察によって位置情報を監視されないようにスマホは家に置いていけ、非暴力抵抗の一環で違法行為に及ぶ場合は一切スマホで連絡するな」くらいの話。そのあたり肩透かしなんだけれど、テクノロジーがもたらす想像性に反発しつつもその利用が避けられないというのはリアル。