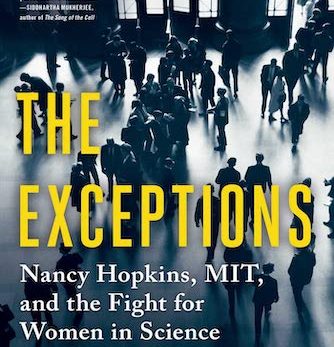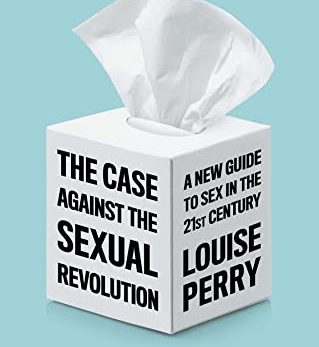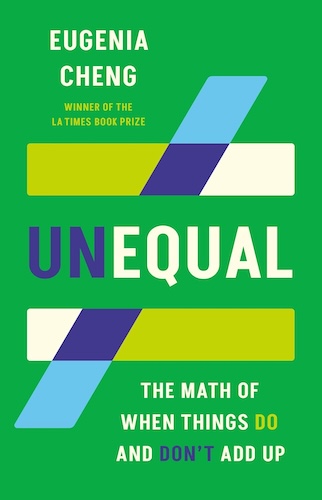
Eugenia Cheng著「Unequal: The Math of When Things Do and Don’t Add Up」
数学の概念と社会問題を重ね合わせて語る著書で知られるイギリス出身のアジア人女性数学者による新作。
前著「x+y: A Mathematician’s Manifesto for Rethinking Gender」では「男性的/女性的」という対概念を数学的に言い換えることで社会的ジェンダーを身体から引き剥がした独自のフェミニズム理論を展開したが、本書は「等しい・等しくない」という概念が数学のさまざまな分野でどのように使われているか紹介し、それらが簡単に切り分けられるものでないことを示すとともに、それをジェンダー・セクシュアリティや人種といった社会的問題に引きつけて論じる。
1=1という数学の表記はもちろん正しいが、それだけではなんの面白みもない。しかし数論や論理学、位相幾何学など数学のさまざまな分野において何が等しいとされ何が等しくないのか、それがどういう意味を持つのかといった話を通して、社会問題における平等と不平等や政治的主張の正しさなどについて論じていく。正直なところ、数学的な概念を持ち込むことで社会問題についてより優れた見解が導き出せるようにも見えないし、逆に社会問題を絡ませることで数学に対する興味や理解を広めることになっているようにも思えないのだけれど、数学者には社会問題がこのように見えるのかもしれない、という方向から読むととても興味深くはある。一応、一番きれいに数学の話と社会問題の話が接続されているのは、まあそりゃそうだなと思うと思うけど、社会問題をめぐる論争について論理学から分析する部分。とくに、よく言われる「誤った等価関係」(false equivalency)という論理的誤謬についてメタ的に分析している部分はちゃんと参考になる。
しかし著者が専門としている高次圏論についての話はわたしにはさっぱり理解できなくて、でも著者がこんなに楽しそうに語っているのだからその魅力を知りたいと思って少し調べてみたけれど、やっぱり分からなかった。ていうか生成AIにもっとわかりやすく説明して、とレベルをどんどん下げてもらったところ言っている内容は理解できたのだけれど、こんどはそれが著者が言っていることとは繋がらなくなり、だからなんなのですか?という感じになってしまった。といって高次圏論を理解している人がこれを読んだとして何かを得られるとは思えないので、残念ながら、「圏論を理解できる数学的素養はあるけれど知らなくて、社会問題にも関心のある人」という限られた層の人(か、分からないものを分からないまま雰囲気だけで楽しめる人)にしかヒットしない本になってしまっている気がする。