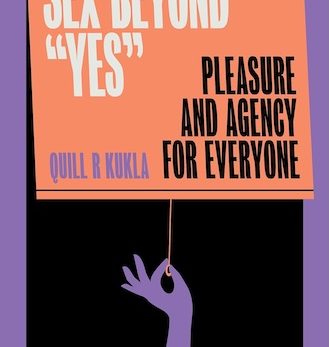Karen Elliott House著「The Man Who Would Be King: Mohammed bin Salman and the Transformation of Saudi Arabia」
まだ国王になってもいないのにサウジアラビアの最高権力者として国家改革を進めるMBSことムハンマド・ビン・サルマーン王太子についての本。以前の王太子を軟禁して交代させたり、ジャーナリストのジャマル・カショギ氏の暗殺や対抗する王族や指導者らの迫害、政治的自由の弾圧など強権的な側面にも触れつつ、宗教的規範の緩和、女性の社会進出の推進、アニメやスポーツ・ゲームなどの解禁と観光産業化などMBSが進める改革を中国の鄧小平やシンガポールのリー・クアンユーなどになぞらえ評価する内容。
サウジアラビアといえば9/11同時多発テロ事件を起こした実行犯の大部分とその親玉オサマ・ビンラディンを輩出した国であり、車を運転する自由を求めた女性が逮捕・投獄されたり、カショギ氏が暗殺されたりと、アメリカ人にあまりいいイメージを持たれていない。政治的な自由が存在せず強権的な政権が存在することは以前と同じだけれど、MBSが宮中クーデターで権力を握り大勢の王族や宗教指導者らを迫害した結果、サウジアラビアは国王を中心とした合議体制から世界中から裕福な観光客を集めることを目指すソフトな独裁国家へと変貌した。欧米のスポーツ球団を買収したりテニスやゴルフの大会を主催し、大金を投じてeスポーツを含む国内のスポーツに海外の有名選手を集めているのは有名な話だし、砂漠の中に快適なリゾートを開発したりもしている。
また、それまでは教師か医療関係者くらいしか就職の機会がなかった女性たちにも活躍の場が与えられるようになっている。MBSが女性の社会進出を推進したのはあくまで経済政策としてそれが有効だったからであり女性の権利を支持しているわけではないが(だから女性の権利を主張すると弾圧の対象となる)、それでもそれまで宗教警察を恐れて行動の制約が多かった女性たちが新たに得た自由と機会を歓迎している。
MBSは外交・軍事面でもサウジアラビアを大国とすることを目論み、これまでのようにアメリカによって保護される国でなく、ロシアや中国、イスラエル、イランなどとアメリカの間を取り持ち影響力を持とうとして、ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁には加わらずロシアの原油を輸入して中国などに横流ししたり、ロシアとウクライナの和平交渉で主役を努めようともしている。10/6のハマスによるイスラエル攻撃は、当時進行中だったイスラエルとサウジアラビアの国交正常化交渉を潰すことが目的だったという説もある。またMBSは地域のライバルであり国内でのシーア派弾圧やイエメンへの侵攻などによって悪化したイランとの関係も改善させている。
サウジアラビアは20世紀ずっとその経済を原油輸出による利益に依存していて、その収入を国民に分配するとともに、多数の外国人労働者を導入して社会基盤を維持してきた。もう何十年もまえから石油資源の枯渇や温暖化による代替エネルギーの登場により財政がたち行かなくなる危機が論じられており、さまざまな計画が立案されたものの、どれも実現には至っていない。MBSが進める観光立国の方針も、現状は石油資源による収入によって賄われているのが現実で、原油価格が暴落すると建設が遅れ、最悪の場合中止に追い込まれるおそれもある。また温暖化によりもともと高温だった国内の平均気温も上昇しており、実際の建設を行う外国人労働者の犠牲が増えるだけでなく、そもそも海外の金持ちが遊びに来たいと思えるような環境が維持できるかも不透明。
著者はMBSが率いるサウジアラビアは確かに反民主的だし独裁的だが、アメリカ人は同盟国だからといってサウジアラビアに高い基準を求めすぎではないか、と繰り返し問う。要求する基準が高いというよりは、アメリカはいまだにサウジアラビアをアメリカの保護を必要としている後進国だと思い込んでいるような気がするけれど、そうしたアメリカの姿勢はサウジアラビアをロシアや中国とのより深い関係に追い込んでいると著者は言う。てゆーか最近「アメリカが認めなければ中国やロシアに先を越される」って話ばかりだな… これが覇権を失いつつあるということなのか。