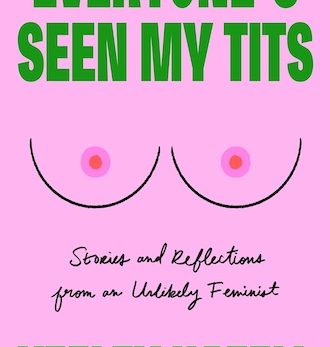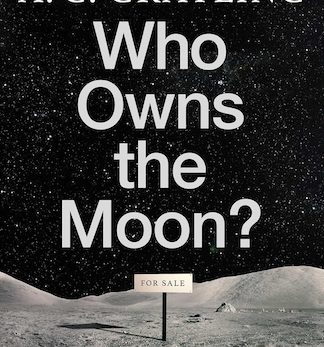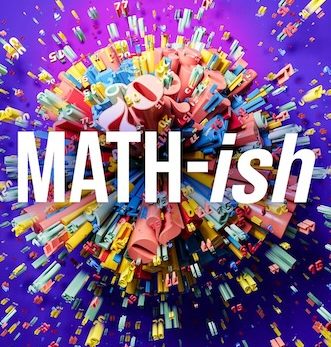Eliza Filby著「Inheritocracy: It’s Time to Talk About the Bank of Mum and Dad」
社会における経済格差が広がり若い世代の社会階層上昇が難しくなるなか、両親からの支援を受けられるか受けられないかによって得られる機会の格差がますます拡大している事実を告発する本。著者はイギリスの人なので事例やデータはイギリスのものが中心だけれど、アメリカの文脈で考えても違和感なく読めた。イギリス国内の地域格差については「へえ」と思ったけど。
親の、というより一家の資産によってアクセスできる機会に格差があるというのは、言うまでもなくいまに始まった話ではない。しかし大卒でなくてもそれなりに豊かな暮らしを送れる収入が得られる職が激減し、教育や住居にかかる費用が高騰したことで、学業や仕事を通して社会階層を上昇することが困難になったいま、生まれついた立場の格差は生涯を通して拡大するばかり。有名大学や大学院への進学はもちろん、良い仕事が見つかるけれど物価も高い都市部に住むにも、はじめての家を買うにも親からの支援が物を言うほか、子どもが生まれたときに面倒をみてくれる余裕のある親がいるかどうかは特に女性のキャリア形成に大きく関係する。
また女性の地位向上が進んだ結果、資産のある家に生まれた女性も有名大学に進学し一流企業で働くようになったばかりか、両親の財産の生前贈与や遺産も男性と対等に受け取ることができるようになり、資産のある男女がお互いと結婚してさらに資産を大きくするのが当たり前になったことも、資産を持たない男女が上昇する機会の消滅と格差の拡大に繋がっている。しかし家事や育児については男性も年々分担するようになってきたもののまだ女性のほうが多く負担しているし、双方の両親らお年寄りのケアはいまだに圧倒的に女性に丸投げされているのが実情。
お年寄りのケアはベビーブーム世代がケアを必要としだしている今とくに切実な問題だけれど、資産がある家庭のお年寄りのケアとなると遺産がチラつくのでまた別の意味合いを持つ。お金があればお手伝いさんを雇うのは簡単だけれど、それでは「あいつは親不孝者だ」として遺産の分配を減らされる可能性があるので頻繁に訪ねるなどのメインテナンスも必要だし、離婚・再婚が多くなった現代では遺産の分配も複雑。税法的にも周囲の気持ち的にも生前から(法的に贈与とみなされない、あるいは脱法的に)自宅の敷金やローンを負担してもらうといった形で分けてもらうほうが有利だけれど、親の側はそれに抵抗を感じたりもするのでドロドロ。だからといって別に金持ちに同情する気は起きないけど。
とにかく社会階層上昇の機会が失われたまま資産がますます一部の人たちのあいだだけに集中していくのは不公平だし社会にとってもよい状況ではないので、資産家からはちゃんとそれなりの税金を取って、それを教育機会や子育て支援、住居支援などに割り当てることが必要、というとても順当な結論。そりゃそうだわ。