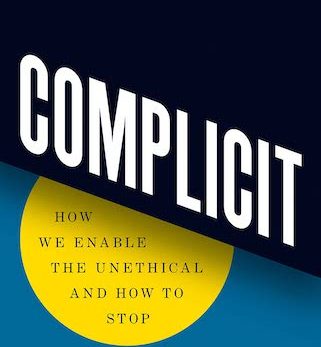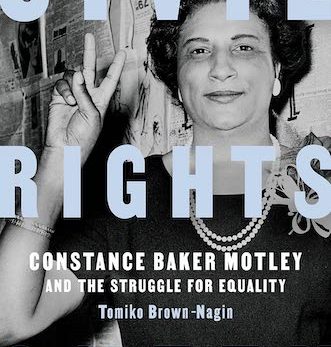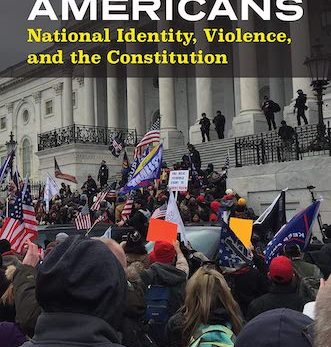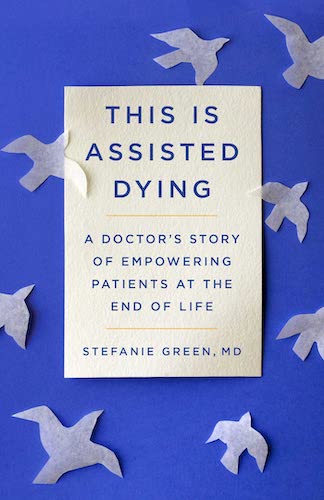
Stephanie Green著「This Is Assisted Dying: A Doctor’s Story of Empowering Patients at the End of Life」
カナダで2016年に医師によるいわゆる自死幇助(medical assistance in dying = MAID)が合法化されていらい第一線でMAIDの実践を続けてきた医者が自身の経験を綴った本。死期が近づき、身体的・精神的苦痛に苦しめられるなか、家族や友人など親しい人たちに囲まれて、きちんとお別れをしたうえで死にたい、という患者の訴えに応えるために成立した制度で、その現場が実際にはどのようなものか、患者本人や家族・親族とどのようなやり取りがあるのか、というその場にいた人にしかわからない話がたくさん紹介されている。
制度の濫用や悪用を防ぐため、患者がほんとうに末期であり苦痛を感じているかを複数の医者が確認するのはもちろんのこと、MAIDを利用すると決断してから実際に受けられるまで10日間の待機期間があり、当日また最終的に本人の意志を確認する必要がある。ところが決断から当日までのあいだに症状が悪化して、当日に意思確認ができなくなる場合もあり、そうすると本人もすでに決断していて家族もそれを受け入れる準備ができているのに、中止せざるを得ないことに。また、かなりの苦痛を感じているのに、鎮痛剤の量を増やすと精神的に朦朧として最後の最後で意思を表明できなくなるおそれがあるからと、待機期間のあいだ必要以上の苦しみを経験する人も。
それでも待機期間中にお別れパーティを開いたり、家族や友人が病室に訪れてお別れをしたうえで、親しい人たちに囲まれて息を引き取ることができるのは、本人だけでなく周囲の人たちにも患者の死を受け入れる機会として羨ましくもある。近年多くの人が自宅やコミュニティではなく病院で亡くなるようになり、それまで身近にあったはずの死が物理的に隔離されるようになったことを思えば、新しいようである意味古い死の経験であるのかもしれない。
カナダのMAID関連法は、もともとは合法的な自殺幇助を求める患者が裁判で勝訴したことをきっかけで制定された法律。その患者は、自分は末期症状になり苦しみが今より強くなったら自死したいけれども、そこまで症状が悪化してしまったら自分の手で自死できるかどうかわからない、そうなった時に自死幇助してもらえないのだとしたら、自分の手で自殺できるうちに自殺しなければいけなくなり、それはいま自分が生きる権利を奪うことになる、という論理で法廷を説得したのだけれど、その結果カナダでは自死幇助を受ける権利が「患者がより良く生きるための権利」の一部として保証されることになった。住民投票で自死幇助を合法化したアメリカのオレゴン州などと比べて、より患者の権利を中心に据えた仕組みになっているのはそのためだ。
紹介されているエピソードのうち一番響いたのは、55年間寄り添った夫婦の夫がMAIDで死を迎える決断をした話。患者である夫は医者に対して妻と長年寄り添えて幸せだった、彼女に感謝している、という言葉を告げるのだけれど、妻は実際の死に立ち会うのを拒否して、そのあいだしばらく散歩することに。愛する人が亡くなる瞬間に立ち会いたくない人もいるので彼女もそうなのだろうと思っていたけれど、夫が亡くなったあとに妻が帰ってきて、夫が本当に死んだとは信じられない、と言い出す。聴診器を聞かせるなどして夫の死を受け入れさせようと医者は奮闘したけれど、あとになってあれはなんだったんだろうと同僚に相談したところ、「彼女は夫のドメスティックバイオレンスを長年受けていたのではないか」と言われる。夫の言い分を聞く限り長年愛し合ってきた仲良し夫婦にみえたけれども、妻の立場から見ると長年自分を苦しめてきた夫が本当に死んだ、もう苦しめられることはない、という事実を受け入れるのに時間がかかったのではないかと。実際のところなにが真実かはわからないけれども、ありそうな話だと思った。
この本ではほかにもさまざまな患者や家族たちのエピソード(プライバシーを守るために名前やディテールは改変してあるが、エピソードの本筋はすべて事実とのこと)や、著者自身の両親が(自死幇助を受けずに普通に)亡くなったときの経験なども綴られ、とても考えさせられる。親しい人たちに囲まれて見送られる人たちの話を読むとわたしもそういうふうに死にたいと思ってしまうのだけれど、最終的に死ぬときはそれでいいとしても、それまでのあいだ親しい人たちに囲まれて楽しく生きたいという思いも強くした。生と死の最前線でいろいろな悩みと向き合いながら「よりよく生きること」の一環としてよりよい死のあり方を問いかける良書。