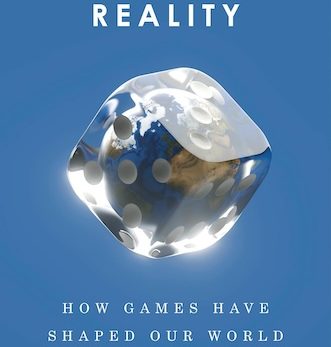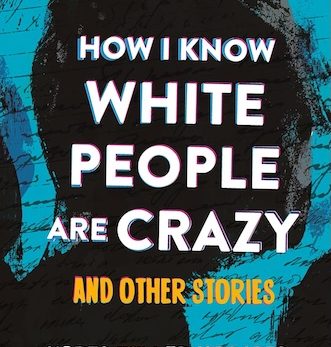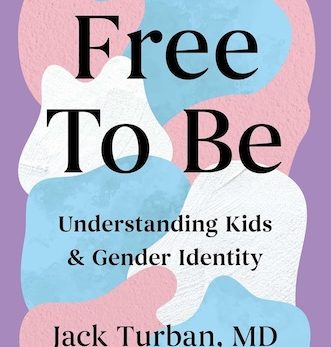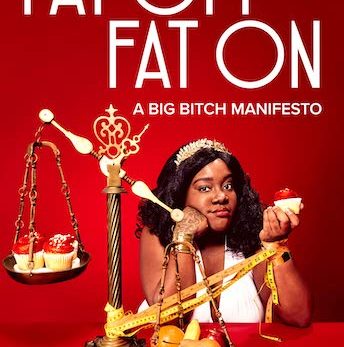Ingrid A. Nelson著「Yet Another Costume Party Debacle: Why Racial Ignorance Persists on Elite College Campuses」
ある小さなリベラルアーツ・カレッジで繰り返し起きた「人種差別的なコスチューム・パーティ」とそれをめぐる大学当局や学生たちの反応について取り上げ、どうして同じ問題が全国の大学でこれほど繰り返されるのか論じる本。ちなみにこの学校、昔まだ無名だったAni DiFrancoのライヴを見るために行ったことがある。
人種差別的なテーマを掲げるパーティをめぐる論争は、2010年代のアメリカでは各地の大学で頻繁に勃発した。差別的なテーマとは、「インディアンとカウボーイ」のようなテーマで白人の学生たちが先住民の仮装(とかれらが思っているもの)をして参加するものや、ギャングやラッパー、売春婦といった黒人文化のステレオタイプをテーマとしたコスチューム・パーティ、ソンブレロを被りテキーラを飲むメキシカン・フィエスタをテーマにしたものなど様々で、少し前までは白人が顔を黒く塗ってデフォルメされた黒人の物真似をするブラックフェイスなども当たり前に行われていたが、バラック・オバマ大統領の当選とそれでも解決しない警察による黒人の市民の相次ぐ殺害などの問題に対抗するブラック・ライヴズ・マター運動の登場を経て、そうした差別的なテーマを掲げる学内パーティは2010年代前後からとくに批判を呼ぶようになる。
本書の舞台であるボードウィン・カレッジはメイン州にある小さなリベラルアーツ・カレッジで、お金持ちの子どもが多く通うエリート校とされている。もともと白人人口の比率が高いメイン州のなかでも同大学の学生はさらに白人の比率が高かったが、ある時期からある程度多様性があることが大学のステータスとされるようになり、主役である白人の学生たちにより優れた学習環境を与えるための施策の一環として黒人やアジア人など非白人の学生が集められた。しかし高校の時点からエリート進学校に通っていた仲間とともに進学してきた白人学生たちに比べ非白人の学生たちは数が圧倒的に少なく、より多くの白人学生たちの周囲に非白人の学生を配置するために非白人の学生同士は離れた学生寮に入れられ孤立を強いられた。
そういうなか、この大学ではある年度に立て続けに先住民や黒人に対する差別的なパーティが相次いで開催される。はじめ大学当局は無視しようとするが、人種差別的なパーティが行われ一部の学生たちが抗議していることが地元のメディアに報じられると、そうしたパーティを企画・主催した学生や実際に差別的なコスチュームを着た学生たちが警告を受け、また学生たちに人種差別や文化の盗用について学ぶ機会を提供するなどの対応が取られた。そのなかで非白人の学生たちは、お互いを理解しあうための文化間対話に参加するよう要請される。
問題となったパーティのうちの一つはキャンパスで重要な役割を持つスポーツチームによって開催されたもので、差別的なコスチュームを着ていた学生のなかにも選手がいたため、チームの責任が問われ、選手たちはとくに問題を再発させないための指導を受けた。しかしそうして一旦落ち着きかけたキャンパスで、ふたたびメキシコ人に対するステレオタイプ的な表象をテーマに掲げ、しかも文化の盗用に対する批判をからかうようなタイトルがつけられたパーティが開催されてしまう。あれだけ求められるまま対話に応じてきたのに何の意味もなかったと非白人の学生たちは失望したが、学生自治会の役員のなかにそのパーティに参加した人がいたことが分かり、かれらを罷免しようという運動が起きる。しかしそれが今度は右派メディアによって注目され、「行き過ぎた『政治的正しさ』によって学生の自由が脅かされている」と騒がれ、また大学への寄付を通して大学運営に強い影響力を持つお金持ちの卒業生から学生の処分を止めさせろという圧力も引き起こしてしまう。
結局のところ、こうした大学はそれ自体が白人至上主義と人種資本主義のもとに成立したものであり、非白人の学生の扱いがはじめから差別なものであったことと向き合わず、個々の学生による差別的な行為だけを問題行為として扱った結果がこの事態だ。差別的なパーティをめぐる大学の対応では白人至上主義や構造的人種差別といった言葉は一切使われず、冷静な対話と相互理解を求めるばかり。そして個人として責任を問われた学生は右派メディアや大手寄付者など外部の権力に頼ることで大学当局を味方に付けることに成功した。
まあ目も当てられないほどの迷走と徒労の記録なのだけれど、同じような小さなリベラルアーツ・カレッジに通った経験があるわたしにとってもいろいろ悪い思い出を想起させられる内容。しかしキャンパスで「白人至上主義」や「構造的人種差別」といった言葉を使ったり、黒人やその他のマイノリティの学生を支援する部署を設置すること自体が連邦政府によって問題視され助成金停止の理由とされている現在から見ると、あれでもまだマシだったのかなあと思えてしまえるところがやばい。