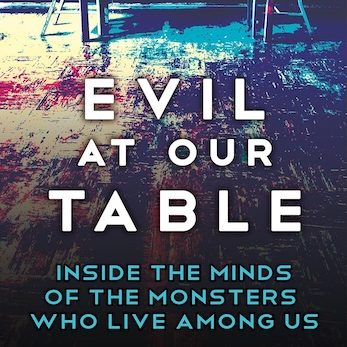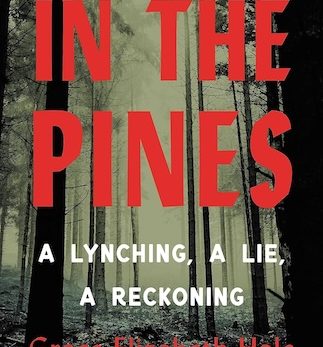Alan Siegel著「Stupid TV, Be More Funny: How the Golden Era of The Simpsons Changed Television—and America—Forever」
わたしも昔は全エピソードを必ず見てたけどいつの間にか意識しなくなり、36シーズン目となるいまもまだ続いていることを知って驚愕している大人向け(エロい意味じゃなくてユーモアが)アニメ「ザ・シンプソンズ」の黄金時代についての本。
3大ネットワークに何十年も遅れた後発の弱小テレビネットワークFOXのコメディ番組内で繋ぎのミニアニメとしてはじまった「ザ・シンプソンズ」が独立。当時のアメリカでは珍しかった大人向けの、しかもよくあるドタバタではなくシットコムの形式で作られたアニメが大人気となり、1992年にはブッシュ(父)大統領が選挙戦でアメリカ家庭の退廃の象徴として名指ししたり(絶対これ、戦略的には間違っていたけど)、「レインマン」で注目された当時ののダスティ・ホフマンや児童虐待疑惑が公になる前のマイケル・ジャクソンらが登場するなど、エンターテインメントの枠を超える影響を持ち、続く大人向けアニメ(「キングオブザヒル」「サウスパーク」「ファミリーガイ」など)の発展にも貢献した。子どもは子どもでバートの口癖を真似て楽しめる、大人は深い意味まで理解してもっと楽しめる内容はキレッキレで、わたしにとっても思い出深いエピソードが多数言及される。
1990年代から2000年代にかけての「ザ・シンプソンズ」は、同じ時期に人気を博したパロディ新聞の「The Onion」(Christine Wenc著「Funny Because It’s True: How The Onion Created Modern American News Satire」参照)やジョン・スチュワートらのニュースコメディ番組(Dannagal Goldthwaite Young著「Irony and Outrage: The Polarized Landscape of Rage, Fear, and Laughter in the United States」参照)と「リベラルな価値観を持つ高学歴白人男性によるアイロニカルなコメディ」という点で共通していて、だからこそインド人コンビニ経営者・店員アプーのステレオタイプ的な描写がのちに批判を集めるなど限界もあった。
今思いだすといろいろ不満も浮かぶわけだけど、当時としてはゲイやレズビアンが普通に登場してかれらではなくホモフォビックな異性愛者の側が笑われるパターンの描写はアツかったし、政治やメディアに対する皮肉や、原子力発電や産業畜産のプロパガンダを描くシーンなどアニメだからこそできた内容もあった。てゆーかシーズンを重ねるごとにどんどんアホになっていくホーマーが原子力発電所の安全担当だし、発電所のそばには目玉が3つある魚が泳いでいるし。最後にとにかく家族が仲良くほっこりすれば過程では何をやってもいい感じがすごかった。
ちなみにわたしの推しキャラはサイドショー・ボブです(次点、パティおばさん)。でもそうねえ、最後に裁判官によるメタなギャグで全部なかったことにされたけど、スキナー校長のあの話はないよねやっぱり(伝わる人に伝われ)。最近どんな感じになってるのか、ちょっとだけ観てみたい(ディズニー+入ってないけど)。