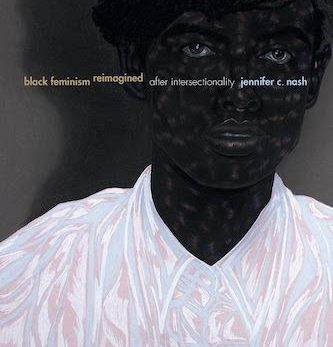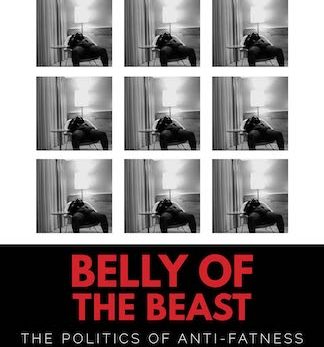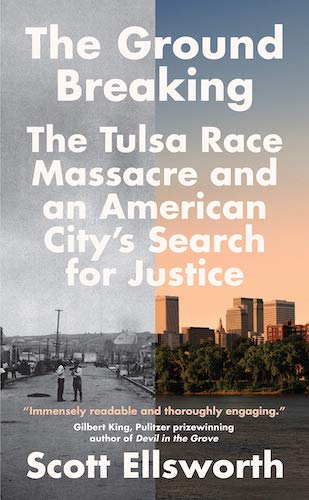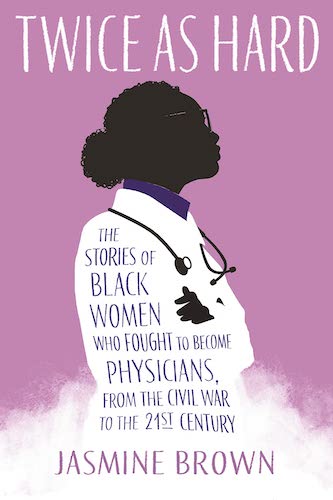
Jasmine Brown著「Twice As Hard: The Stories of Black Women Who Fought to Become Physicians, from the Civil War to the 21st Century」
差別や偏見、経済的困難などと闘いながら道を切り開いてきたアフリカ系アメリカ人女性医師たちの歴史を記録する本。著者はローズ奨学金を得て科学史の学位を得たあと、ペンシルヴァニア大学医学部に入学した現役医大生のアフリカ系アメリカ人女性。
本書でプロファイルされるのは、リンカーン大統領の奴隷解放令からたったの14ヶ月後にアフリカ系アメリカ人初の医師となったRebecca Lee Crumplerさん、ハーレム・ルネサンスに湧くニューヨーク・ハーレムで音楽から医学に転身して黒人の患者たちが必要な医療や検査を受けられるよう尽力したMay Chinnさん、南部で小作農として働いており雇用主によってクリニックに行くことを止められていた黒人たちに医療を届けるために車で農場を巡回する移動クリニックを発明したほか黒人女性の団体を創設し公民権運動に参加したDorothy Ferebeeさん、南部の白人専用だった医大に白人至上主義者たちの脅迫を受けながらたった一人の黒人学生としてはじめて入学し卒業しのちにアメリカ医学会の会長にもなったEdith Irby Jonesさん、小作農の子どもとして農場で働きながら勉強に励みクリントン政権で黒人として初の医務総監(女性としては二人目)となったJoycelyn Eldersさんら。Eldersさんについては彼女が書いた自伝を読んで知っていたけど、ほかは恥ずかしながら知らなかった人ばかりで、めっちゃカッコよくてすごく元気をもらえる。
と同時に彼女たちの成功の裏には、過酷な差別やその他の困難と同時に、彼女たちを支えた多くのほかの黒人たちや一部の白人たちの支援やかれらとの偶然のめぐりあいがあったことも見過ごせない。ほかの教師は誰一人なんの期待をしていなかったのに一人だけ努力を認めて大学進学の道を開いてくれた先生、自分たちが着る服も満足に買えないくらい貧しいのに奨学金をもらって進学する村の少女が大学に行ったときに恥をかかないようにとよそ行きの服を買ってくれた近所の黒人家庭、学費を払えない学生に仕事を与えてくれた歴史的黒人大学の学長など、多くの人たちの助けがあってこそ彼女たちは実力を発揮することができた。そして、だからこそ彼女たちは自分の成功は自分だけの努力によって成し遂げたものだと考えずに、ほかの黒人たちや移民などそれ以外のマイノリティの人たちがより良い医療にアクセスできるように尽力した。
先に書いたとおり著者は現役の医大生だけれど、彼女の同級生160人のうち黒人は23人でそのうち10人が黒人女性。でも実際には黒人学生にはアフリカからのエリート留学生やアフリカやカリブ海からの移民が多く、アフリカ系アメリカ人家庭に育った黒人女性は学年で彼女一人だった。大学や医学界で人種差別や性差別に直面することはアフリカやカリブ海出身の黒人女性もアフリカ系アメリカ人女性も同じだけれど、そこにたどり着くまでの社会的・経済的な状況は大きく違う。彼女のようにローズ奨学金を獲得するほどの優等生でも、アフリカ系アメリカ人女性であるというだけで「アファーマティブアクションによって本当に入学するはずだった白人男性から席を奪ったのだろう」と噂され、アフリカ人の学生たちからも「あなたはローズ奨学生だからアフリカ人と同じくらい勤勉なんだろう」と、まるで彼女だけが例外であってアフリカ系アメリカ人は一般に怠け者だと見下すようなことを言われる。
そういう環境にあるからこそ、著者は科学史の専門性を活かし、19世紀から現代まで彼女自身やほかの若いアフリカ系アメリカ人女性たちのロールモデルとなるようなアフリカ系アメリカ人女性医師たちの歴史を掘り起こし、この本にまとめたのだろう。わたし、以前インターセックス医療の問題に深く関わっていたときに、小児内分泌科を専門とするJoycelyn Eldersさんがインターセックス(性分化疾患)の子どもの治療についておかしなことを書いていることを彼女の目の前で批判したことがあるのだけど、あれはちょっとまずかったかなと今更ちょっと反省してる。当時彼女の伝記を読んだときはインターセックス関連の記述だけに注目して怒ってたけど、いま思うと彼女に対してリスペクトを欠いていましたごめんなさい。めっちゃおもしろいからみんな読んで!(Eldersさんの自伝も読み直さないとなあ…)