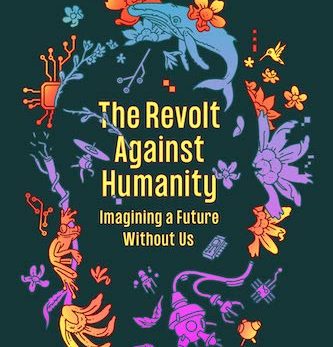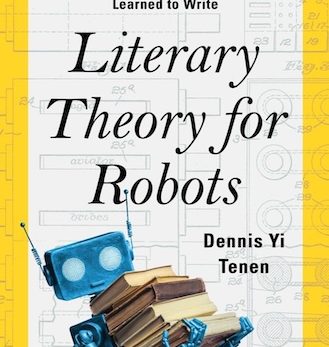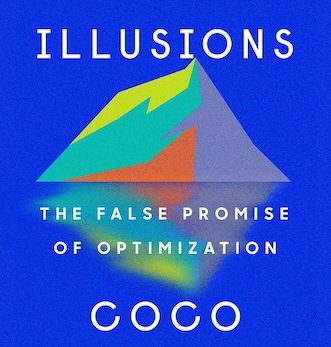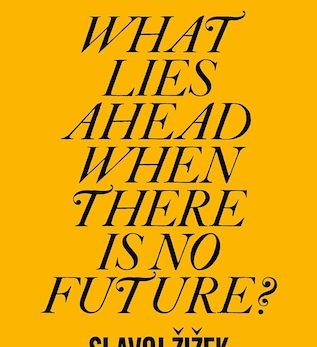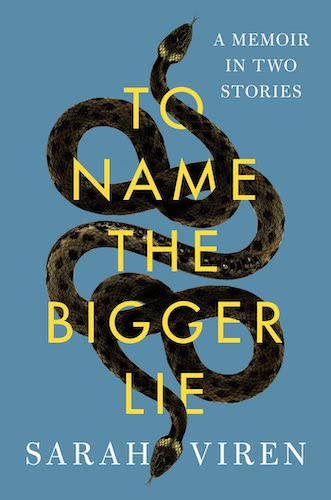
Sarah Viren著「To Name the Bigger Lie: A Memoir in Two Stories」
ミシガン大学に就職が決まりそうなタイミングで別の最終候補者の一人によって同性(女性)のパートナーともども虚偽のセクハラ疑惑をでっちあげられた経験について書いたエッセイが2020年にニューヨーク・タイムズ・マガジンに掲載され大反響を呼んだ著者が、その事件と事件が起きた当時書こうとしていた別の本を組み合わせ、プラトンの「洞窟の比喩」を絡めて真実の追求について論じる。
本書は著者が高校時代に受けた、カリスマ的な哲学教師の授業の思い出からはじまる。何が真実なのか、真実とは何なのか、そしてわたしたちはそれをどのように知るのか?懐疑論者であった教師は、文学や哲学を通してそれまで生徒が疑いもしなかった現実の認識そのものに疑問を抱かせ、挑発し、自分自身の頭で考えることを強い、多くの生徒たちの人気を得るとともにかれらに一生残る影響を与えていた。しかし著者が二年生になった年、夏休みのあいだに教師はカトリックに改宗して再登場、授業のなかでさまざまな陰謀論を語るようになったあげく、ホロコースト否定論者のビデオを生徒たちに見せるようになる。
トランプが差別的な嘘や陰謀論を撒き散らしながら大統領に当選し、かれを支持する極右によって反ユダヤ人的な嘘や陰謀論がメインストリーム化されるなか、著者は高校時代の人気教師の豹変を思い出し、あらゆることを疑え、鵜呑みにするな、自分で考えて判断しろ、というクリティカル・シンキングが、結果的に「大手メディアはユダヤ人に支配されていて信用できない、経済も政治も裏の勢力によって牛耳られていて自分たち一般市民は騙されている」という陰謀論の拡散に加担してしまっているのではないか?という疑問を解明するために、著者はかれの生徒だったかつてのクラスメイトたちに取材を開始する。元生徒たちの多くは、かれが本当に陰謀論を信じていたのか、それともかれ特有の生徒を挑発して自分の頭で考えるよう促すための手段だったのか、いまだに結論を出せないでいるが、いずれにせよユダヤ人の元生徒のように直接そうした陰謀論の対象とされた人たちが負ったダメージは深い。
その取材をするなか起きたのが、冒頭で言及したニューヨーク・タイムズ・マガジンの記事の事件。ミシガン大学での採用が内定し、パートナーもできれば教職、そうでなくてもなんらかのポジションで大学に職を得たいという希望を出した著者は、ネットにパートナーに対する匿名のセクハラの告発が書かれたことを知る。さらに現在二人が働いている大学にも匿名の告発があり、大学は調査を開始。告発によればパートナーは自分が指導する女性の学生を夜のオフィスに呼び出すなど執拗に誘い、性的関係を迫ったという。パートナーはまったく身に覚えがないと言うし、客観的な状況からも告発は事実ではないと信じる著者は、それでもそういった告発を受けるだけのなんらかの理由はあるのではないか、あるいは不満を持たれているのではないか、という不安を感じる。
ミシガン大学からの正式な採用通知とパートナーへの職の斡旋を待つなか、大学にはまた別の学生を名乗る匿名の告発が。著者とパートナーは自宅でクィアな学生を集めたパーティを開いて学生を酔わせ、パートナーが部屋に飾った絵を見せたいと学生の一人をベッドルームに連れ込むと、上半身を露出した著者が待っていて、胸を触らさせられた、というのがその内容。もちろんそんな事実はないし、パーティを開いたこともないけれど、大学の調査員に胸を露出したか、触らせたかと問い詰められた著者は屈辱感を覚える。いっぽうミシガン大学にはいま働いている大学の同僚を名乗る人物から「あなたたちが採用しようとしている教員は現在セクハラで調査を受けている、セクハラ事件を起こした教員が何もなかったかのように別の大学に移籍してまた別の学生を傷つけるのを許してはいけない」というメールが。
このあたりの展開は恐怖でしかないのだけれど、詳細は本書やNYTに掲載されたエッセイに譲るとして、犯人は著者とともにミシガン大学で最終候補者の一人として残っていた男性だった。かれは、著者がミシガン大学で採用されなければ自分が採用されると信じて匿名でセクハラの告発を送るとともに頻繁に著者に連絡して様子を探っていたが、共通の知人に著者について根掘り葉掘り聞いていたことや本来部外者には知られるはずのないセクハラの調査について知っていたことなどから早い段階で著者はかれの関与を疑い、その後ネットでの告発やメールの送信に使ったインターネットプロバイダへの情報開示請求が通ってかれの犯行であることが確定した。
真実がどのように社会的に作られるのか、すべてを疑うこととセクハラや性暴力のサバイバーを信用することはどう折り合いをつけるのか、陰謀論や歴史否定論などは議論の対象となるのか、といった難しい問題を、著者はときにソクラテスに習ってカメと会話しながら考えていく。すでにNYTに掲載された衝撃的なエッセイを読んでいたわたしはその事件についてもっと詳しく知りたいと思ってこの本を待ち望んでいたけれど、それ以外の部分も抜群におもしろくて考えさせられた。