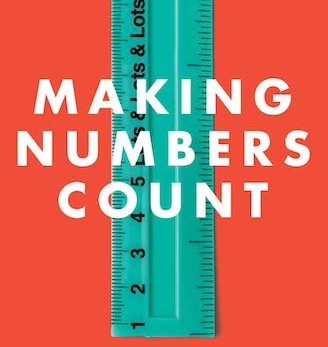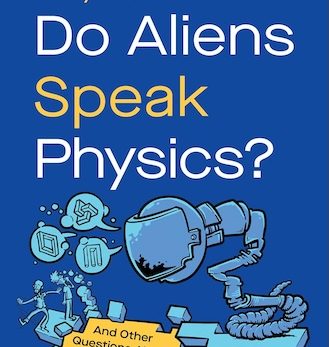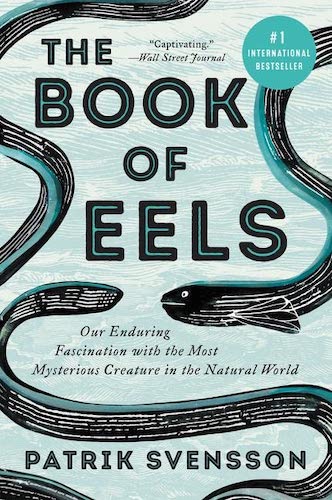
Patrik Svensson著「The Book of Eels: Our Enduring Fascination with the Most Mysterious Creature in the Natural World」
タイトルのとおり、ウナギの本。原著はスウェーデン語で書かれており、著者はスウェーデンのジャーナリスト。そういうこともあり序盤はヨーロッパウナギの話が中心なのだけれど、次第にアメリカウナギやニホンウナギの話も出てくる。ウナギは世界中で狩猟され食べられていたけれども、魚なのか爬虫類なのか両生類なのか、どこでどのように繁殖するのかなど生態に謎が多く、西洋では昔から「ウナギ問題」として哲学者や科学者たちにあれこれ論じられてきた。生殖が確認できないどころか解剖しても生殖器すら見つからないため、アリストテレスがウナギは泥から生じると推定したくらい。また学生時代のジークムント・フロイトは指導教官の指示でウナギの精巣を発見しようと400匹を超えるウナギを解剖したけれど結局見つからなかったとか。
ウナギの生態について詳しくはこの本を読むかウィキペディアで調べればいいのでここでは詳しく書かないけれど、ヨーロッパウナギとアメリカウナギというそれぞれ違った種が大西洋の同じサルガッソ海で生殖して、新しく生まれた個体がそれぞれちゃんとヨーロッパとアメリカに帰っていく(かといって親と同じ川に戻るというわけではない)こととか、生殖に適さない環境では性成熟を何年も遅らせることができたり、食料がなくても仮死に近い状態で長いあいだ生き延びるなど、謎が多い。まあ謎が多すぎるせいで商業的な完全養殖がいまだに実現しておらず、養殖のために必要な天然の稚魚の乱獲による絶滅が恐れられているわけだけど。
『沈黙の春』を書いて環境保護運動のきっかけを作ったレイチェル・カーソンも生物学者を目指していた時期にはウナギの研究をしており、のちに雑誌に寄稿した一般読者に海生生物の生態を紹介する記事ではウナギを擬人化してストーリー仕立てにしてみせた。もちろんカーソンはウナギが人間と同じような感情を持たないであろうことはわかっていたけれど、擬人化してみたくなるほど親しみを感じていたのだろう。
著者は本を通して父親とともにウナギを捕りに行った思い出を語っており、時には子どもらしくウナギを残酷に扱って叱られたり、時には小さなウナギを自宅の水槽で買おうとしたところ食事もせず動かなくなってしまったために川に返しに行ったりと、ウナギとの関わりを通して自然に対するリスペクトと感謝を父に教わったことを記している。エピローグでは病気になり亡くなった父の葬式のあと、ウナギと対面し見つめ合うシーンがある。カーソンと同じく、ウナギはかれの父親が亡くなったこととか、かれと父親との関係にウナギが関係していることなんて知るはずもないけど、そこに意味を感じてしまうのがおもしろい。
David Shiffman著「Why Sharks Matter」でも算出方法が詳しく説明されていたIUCNレッドリストでは、ヨーロッパウナギが「絶滅寸前」、アメリカウナギやニホンウナギも「絶滅危惧」とされており、保全の取り組みが叫ばれている。本書ではその原因として乱獲のほかにもダムの設置など開発によってウナギの移動が妨げられていることや水質汚染、養殖環境における寄生虫蔓延、気候変動などの要因が指摘されているが、稚魚の密猟が横行しているのがやはり一番の問題。