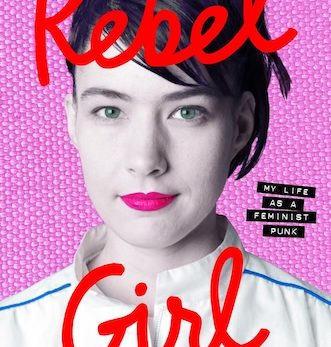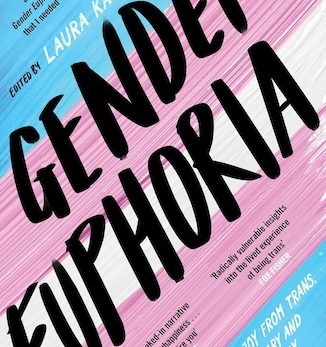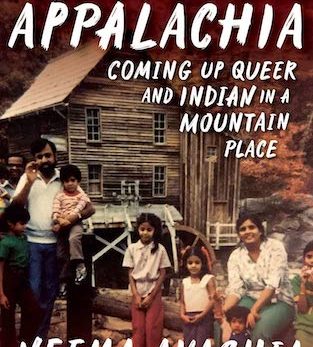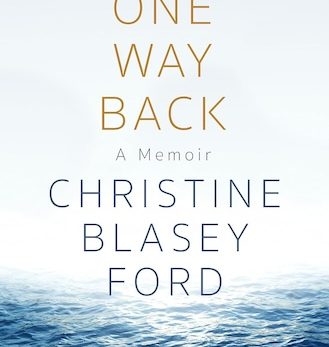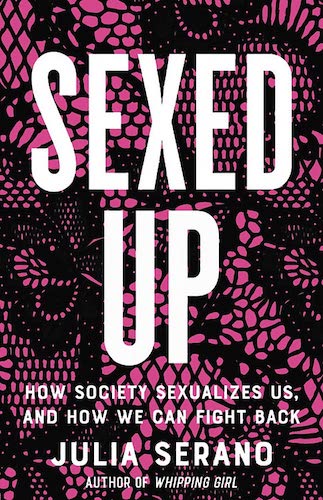
Julia Serano著「Sexed Up: How Society Sexualizes Us, and How We Can Fight Back」
トランス女性の立場からフェミニズムを論じたデビュー作「Whipping Girl」の日本語版がクラウドファンディングによって近日出版される著者ジュリア・セラーノの新著。サブタイトルにある「sexualize」(無理やり訳すと「性化」)とは一般的には性的対象化する、他人やその身体を性的な道具としてモノのように扱う、という意味でフェミニストたちがよく使う言葉だけど、著者はこうした解釈は性化の一面でしかないと指摘、性的対象化とともに性的スティグマ化に注目する。
著者は自身が男性から女性にトランジションした際、それまでも女性が日々経験しているセクシズムや性的対象化について理解はしていたつもりだったけれども、実際に自分が女性と見做されるようになって経験したそれは予想以上だったと語る。しかしそのうちに彼女は、見知らぬ男性が彼女に投げかける(彼女が男性として生きていた時には一切経験しなかった)性的な発言や失礼なジョーク、意味のない干渉を動機付けるものが彼女に対する性的な欲望だけではなく、彼女を恥ずかしがらせたり、困惑させたり、反応させようとするものが多いことに気づく。そしてそれは、彼女がまだ男性と見られていた時に「男らしくない男」として受けた嫌がらせと通ずるものだった。
著者は女性だけでなくゲイ男性、トランスジェンダーの人たちなど多くの人たちが経験する、こうした「必ずしも欲望に基づかない性的な嫌がらせ」を説明するためには、フェミニズムが伝統的に採用してきた性的対象化(=女性を性的欲望の対象とみなしてモノのように扱うこと)の論理では不十分だと主張し、彼女の言うところの「性化」には性的対象化だけでなく性的スティグマ化も含まれる、と主張する。彼女の言う性的スティグマ化とは、他者や集団を性的に異端で穢れた存在として規定し一人の人間としての尊厳を否定することであり、性的欲望の対象として扱うことはその一部に過ぎないとする。ほかにも、特定の集団を性的に過剰だとみなしたり逆に非性的な存在と決めつけたり、あるいは危険視したり常に性的に手出しできるとみなすなどが含まれ、女性だけでなく被白人の各人種に対するジェンダー的なステレオタイプや障害者、トランスジェンダー、性労働者などさまざまな人たちに向けられる差別的な扱いを、著者は「性化」という言葉に含めて使っている。
フェミニストによる「性的対象化」の論理は「欲望に基づく不当な扱い」だけに限られており不十分だ、とする著者の主張は「性暴力は欲望ではなく権力に基づくものである」と主張してきたラディカルフェミニズムの伝統を無視しているのではないかと思うけれど、さらに著者は、反ポルノ運動を展開してきたラディカルフェミニズムは女性差別の根源を性的対象化に見出してしまったために、性的対象化が行われる文脈や人々の多様な経験を無視して、それを全面的に否定してしまっている、と論じる。たとえば道端で見知らぬ男性に性的な言葉をかけられることと性的パートナーに見せるためにあるいは自分自身の好みでセクシーな下着を身につけることは違うはずなのに〜と著者は言うが、フェミニストによる反ポルノ運動はポルノを単なる性的描写という意味ではなく特定の文脈において作られ消費される描写として定義しているし、ラディカルフェミニストたちが大量の性的欲望表現を生み出しているのだけれど。
著者は序盤で「インターセクショナリティ」の概念を紹介し、のちの2つの章で自分はフェミニズムにおける「性化」の議論をインターセクショナルに拡張するのだ、と主張している。これまでのフェミニズムの議論では「女性」という単一のアイデンティティをめぐって「性的対象化」が議論されてきたが、自分は「性的スティグマ化」を射程に入れることで人種・階級・セクシュアリティ・ジェンダー・障害などさまざまなアイデンティティ及びそれらの相互作用を考察に入れているのだ、と彼女は言いたいようなのだけれど、これまでのフェミニズムが「女性」だけを問題としてきた、という認識はどうか。著者はインターセクショナリティという言葉を説明する際、その言葉を生み出した黒人女性フェミニスト、キンバリー・クレンショーの名前をなぜか出していないが、彼女や他の非白人女性フェミニストたちがフェミニズムの中で交わしてきた議論を忘却したうえで彼女たちの主張を「これまでのフェミニズムになかった自分の考え」として提示するのは非常に疑問。また、著者は他者の性的欲望を理由とした差別や非難のおかしさを指摘するため、食生活に例えて「好みの違いを理由に否定されることはないのに」と論じるが、Psyche A. Williams-Forson著「Eating While Black: Food Shaming and Race in America」にも書かれているように、黒人など周辺化された人たちの食生活や食文化を理由とした深刻な差別や暴力は存在する、というインターセクショナルなフェミニズムの視点を欠いているように見える。
女性が経験している性的対象化についての議論を広げて非白人やゲイ、トランスジェンダー、障害者、性労働者などさまざまな人たちが経験している多様な「性化」のパターンを包括した論理を打ち立てよう、という著者の考えはわかるのだけれど、広げすぎた結果「みんなお互いを個人として尊重しよう」的に薄ぼけた感じになってしまっている気もする。また、性暴力をふるう人のことを「モンスター」扱いするべきではないというのは、実際の性暴力の大半は見知らぬ第三者ではなく信頼された身近な人間によって起こされるものだという意味では正しいと思うけれど、「乱暴な運転をする人」にたとえるのはさすがにどうかと。著者が言わんとするのは「乱暴な運転をする人も、運転している時以外は普通の家族や友人や隣人だったりする、しかしかれらがルール違反を犯すことは重大な危害に繋がる」ということらしいのだけれど、彼女自身が二度経験したデートレイプ未遂の話をしたあとで性暴力被害を「ルールを破ったせいで結果的に起きてしまった事故」みたいに扱うのは正直理解できない。
てゆーかもっと言うと、正直わたしは「Whipping Girl」も出版された当時それほど評価してなかったのだけれど、それでもその本が「トランスミソジニー」や「シス」という言葉を一般に広め、トランスジェンダーの権利を守るのに大きく貢献したことは認めざるをえないわけで、本書ももしかしたら性暴力やハラスメント、性的スティグマ化を減らすきっかけになるかもしれないとは思うし、密かに期待はしている。