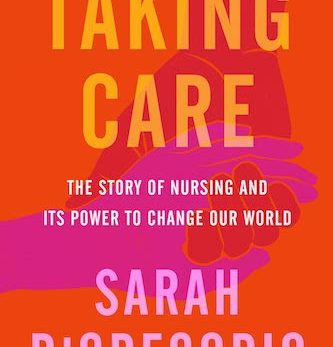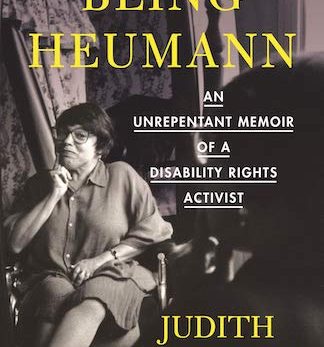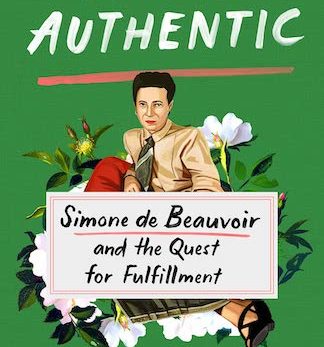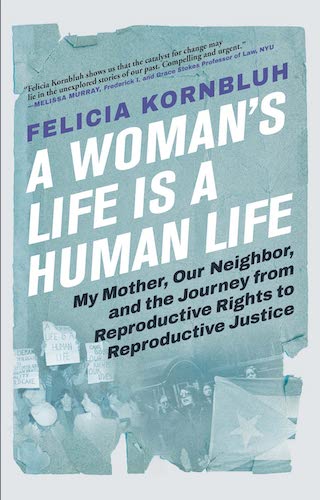
Felicia Kornbluh著「A Woman’s Life Is a Human Life: My Mother, Our Neighbor, and the Journey from Reproductive Rights to Reproductive Justice」
フェミニスト歴史学者の著者が、1973年に最高裁がアメリカ全土で妊娠中絶を合法化する以前のニューヨーク州で他州に先駆けて妊娠中絶合法化の法案を起草した法律家の母親と、当時彼女たちと同じアパートの向かい側の部屋に住んでいたプエルトリコ出身の女性医師・活動家の生涯を対比させながら、妊娠中絶合法化運動と強制的な不妊手術反対運動がそれぞれ別個に発展し、対立しながら、現代のリプロダクティヴ・ジャスティス運動に繋がった様子を追った本。
舞台は1970年代初頭のニューヨーク。女性解放運動の高まりとともに、女性が教育や就業における平等の権利を行使するには妊娠・出産の選択を自分の手に取り戻さなければいけないという意見が広がり、全国女性機構(NOW)をはじめとする女性団体は妊娠中絶合法化を強く訴えるようになる。そうした声は、教育や就業の機会が開かれつつある白人中流女性たちのあいだで特に強く共有された。人種や階級による格差についても一応認識していて、自分たち白人中流女性は必要とあらばジェーン・コレクティヴなど地下ネットワークを頼ったりイギリスや日本など合法的に中絶手術が受けられる外国に旅行することもできるけれど、それができない貧しい非白人の女性たちのためにこそ中絶合法化は必要である、と主張した。また女性が自立するためにはあらゆる避妊の手段を女性が選ぶことができるべきだと主張し、本人の意思によって不妊手術を受ける権利もそれに含まれるべきだと訴えた。
一方著者が子どものころお向かいに住んでいたプエルトリコ系女医エレン・ロドリゲス=トリアス氏は、プエルトリコで顕著な本人の同意を得ない不妊手術を禁止する運動に取り組んでいた。プエルトリコは当時はもちろん現代に至るまでアメリカ領だがその住民たちは大統領選挙への投票権など一部の権利を持たず、アメリカ本土とは違った制度や慣行によって人々の人権が制限されていた。そういうなか、多くの女性たちは白人が運営する病院によって、本人が知らないうちに不妊手術をうけさせられており、一時は現地女性の3割もがそうした措置を受けていた。これは規模の違いこそあれ南部の黒人女性たちや米軍の運営する病院にかかっていた先住民の女性たちにも共通する経験であり、非白人女性たちにとっては妊娠中絶する権利・避妊する権利よりも優生主義的な政策や慣行を通したジェノサイドから子どもを産み育てる権利を守ることこそが重要課題だった。
著者はこうした齟齬について当時の白人フェミニズムの問題点を批判しつつ、母やその仲間たちがどのような困難な状況で戦ってきたか、そして女性の権利を拡大してきたかも共感的に記述する。そして非白人女性たちの運動が当時のブラックパンサー党やヤングローズ党(プエルトリコ系ギャングを前身とする反差別運動組織)による医療大衆化運動と共鳴しつつ、「いつ、どのように、どうして」生むのか、そして生まれた子どもと母親が健康に生きる権利を広げようとするリプロダクティヴ・ジャスティスの運動に発展したか、それをようやく白人フェミニストたちも受け入れるようになりつつあるのか、紹介する。ヤングローズ党がニューヨーク市に対してサウスブロンクスのプエルトリコ系コミュニティで結核検診をするために市の公共衛生バスを貸し出せと要求し断られた際、バスを盗んで勝手にプエルトリコカラーに塗り替えてコミュニティで検診を行ったというエピソードとか、当時の運動がどれだけ大きな力を持っていたかよく分かるすごい話も。
去年は50周年を目前にして妊娠中絶の権利を認めた歴史的な最高裁判決が破棄されてしまったが、Becca Andrews著「No Choice: The Destruction of Roe v. Wade and the Fight to Protect a Fundamental American Right」などここ数年に出版された妊娠中絶問題に関する本では、これを機に「個人の自由として中絶する権利」だけを守ろうとする「プロ・チョイス」運動の限界を認め、より広範な自由と平等を求めるリプロダクティヴ・ジャスティスの運動に全力で移行すべきだという議論が高まっている。1973年判決がなまじ画期的であったためにそれを守ることが焦点となってしまい、それ以外に目を向けることは「敵を利する」ことであるかのように錯覚してしまった人も多かったが、ようやくその間違いが広く共有され、より多くの人たちが共感し参加できる運動が展開されつつある。まさしくこの本はそういう意味で、Roe v. Wade判決の前史でありながら、同時にその廃墟のあとに待つ未来の話だと言える。