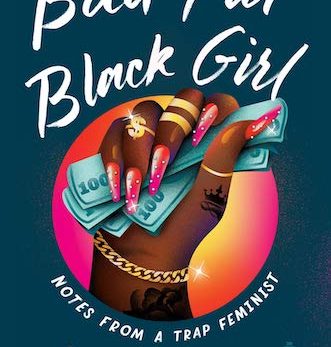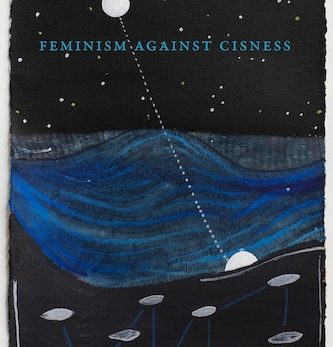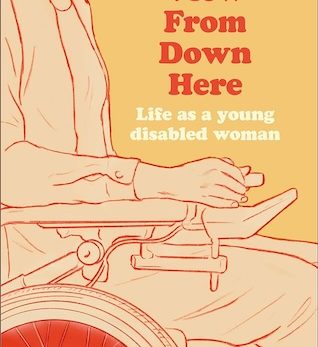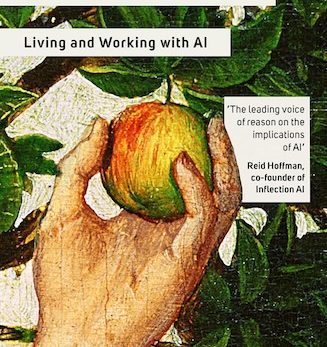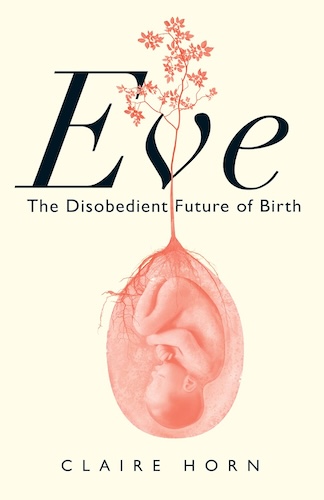
Claire Horn著「Eve: The Disobedient Future of Birth」
人工子宮の研究がリプロダクティヴ・ライツやリプロダクティヴ・ジャスティスに与える影響について社会的再生産フェミニズムの立場から考察する本。
社会主義フェミニズムの旗手シュラミス・ファイアストーンが1970年の「The Dialectic of Sex」で妊娠・出産の体外化・機械化を主張し、フェミニスト作家マージ・ピアシーが1976年のSF小説「Woman on the Edge of Time」で子どもが人工子宮によって体外で生み出されジェンダーがさまざまな3人の大人によって育てられる社会を構想したように、人工子宮の開発によって女性を妊娠・出産から解放するという思想は1970年代の第二波フェミニズムのなかで一定の支持を得た。いっぽうナチスが台頭した1930年代にオルダス・ハクスリーが書いたディストピア小説「The Brave New World(すばらしい新世界)」でも同じように人工子宮によって子どもが生み出される設定が採用されたが、ハクスリーが描いたのはフェミニストたちが求めていたような、性別と関係なく大人たちが自由に生き、子どもたちが多様なジェンダーの大人たちによって大切に育てられる社会ではなく、子どもが国家の所有物として扱われ、知能によって階級に分けられたうえで洗脳が行われる社会だった。このように人工子宮というテクノロジーの社会的な意味や影響は、それが開発される社会の状況に大きく左右されると考えられる。
医学や発明の分野でも古くから人工子宮の研究は行われてきたが、その動機は女性の自由を拡張するためではなく、次世代の再生産を国家あるいは医療の管理下に起くことで、より質の良い子孫を増やし、質の悪い子孫を根絶やしにしようという優生主義に基づくものだった。第二次大戦後には優生主義的な考えはおおっぴらに主張することがはばかられるようになったが、人工子宮の研究のなかで早産児のための保育器という実用的な設備が開発され、より早い段階で生まれた子どもを生かせるようにと保育器をより高性能化していく延長線上に、究極的には受精卵の段階から赤ちゃんを生み出せる人工子宮が最終目標として掲げられた。
保育器がなければ生きることができないほど未熟な状態で子どもが生まれてしまった親にとっては保育器の存在はありがたいし、産みたくても産めない事情があって人工子宮の完成を待望している人も多いだろう。しかし現実の世界において、保育器の恩恵にあずかれるのは先進国に生き経済的な余裕のあるごく一部の特権層だけだ。途上国では先進国に比べ早産児の死亡率は圧倒的に高く、早産児でなくても死産の割合や新生児が生後すぐ死ぬ確率、出産した親が死ぬ確率など軒並み高い。また先進国の中でも、人種的マイノリティや貧困層のあいだでは同じように新生児や親の死亡率が高く、アメリカでは格差が近年さらに広がりつつある。もし仮に途上国に保育器を無償で提供したとしても、安定した電力や安全な水の供給、十分な医療スタッフその他のリソースがなければ保育器のような複雑で専門知識のあるスタッフが必要な設備は運用できないし、食糧事情や衛生状況、環境破壊などさまざまな問題が解決されなければ子どもの死亡率を下げることはできない。結局、保育器のように初期投資だけでなく運用にも多額のお金がかかり大量のリソースを必要とする設備は、すでにさまざまな面で特権的な地位にある先進国の一部の人たちをさらに特権化してしまう。
人工子宮の開発をめぐってはこのような既存の経済格差・医療格差を拡大する問題に加え、さらに深刻な危険が存在する。それはただでさえ「胎児の保護」を理由として子どもを妊娠している人たち、主に人種的マイノリティや貧困層の女性たちが社会的な監視を受け、飲酒や「望ましくない」食生活や仕事などによって胎児を危険にさらしたという理由で拘束されたり罪に問われたりしている社会において、かれらの自由を奪う新たな道具にならないかという懸念だ。先進国の裕福な人たちのあいだでは人工子宮は一つの選択肢としてポジティヴに捉えられうる一方で、それ以外の人たちにとっては国家や医療が個人から選択肢を奪うために人工子宮が使われる可能性は高い。
さらに問題なのは、倫理哲学者ピーター・シンガーが1970年代に発表した論文をはじめ、多くの生命倫理学者らが人工子宮の開発を「中絶をめぐる論争への最終的な解決」と捉えている点だ。妊娠中絶をめぐる政治的な論争を「自分の身体で妊娠継続を強制されない権利」と「胎児の生きる権利」の対立だと考える人たちは、人工子宮が完成されれば妊娠の継続を望まない人は胎児を摘出して人工子宮に引き渡せば良く、どちらの権利も守られると主張するが、これは妊娠した人の立場に立った考え方ではない。自分の身体で妊娠継続を強制されるよりはマシかもしれないが、自分の意志に反して胎児を生きたまま摘出され人工子宮で育てられるというのは本人の選択肢を奪っていることでは変わらない。人工子宮が完成していない現代でさえ、早産児のための保育器の機能が向上するとともに、「体外でも生存可能になったから」という理由で合法的に妊娠中絶できる期間が短縮化されてきているのが現状だ。そうして自分の意志に反して自分の子どもが生まれてきたとして、その子との関係はどうなるのか、中絶できていれば生じないはずのさまざまな問題が生まれてしまう。また、一部の論者は人工子宮が開発されれば男性と女性は出産をめぐって対等となり、したがって生むか生まないかの決定権は両者に平等にあるべきだと主張しているが、これも妊娠する人たちの持つ決定権や選択肢を狭めるものだ。
本書がさまざまな側面から描き出すのは、テクノロジーだけでは社会的問題を解決することはできないということだ。女性やそれ以外の妊娠する人たちの権利を尊重し、人種や階級による格差をできる限り減らそうとする社会においては人工子宮の開発は人々に新たな選択肢とともに自由を与えるが、性差別や優生主義、人種差別や経済格差などが深刻な社会においては新たなテクノロジーの登場はさまざまな格差をさらに拡大してしまう。人工子宮が動物実験においてそこそこの成功を修め、ヒトによる研究も行われようとしているいま、とても重要な議論。