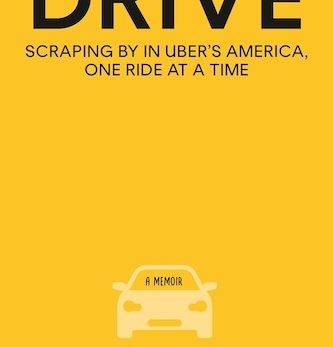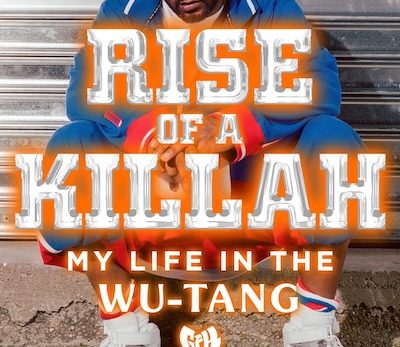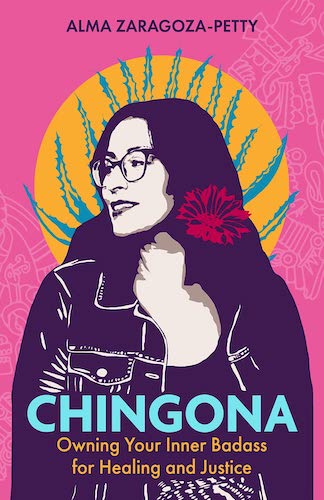
Alma Zaragoza-Petty著「Chingona: Owning Your Inner Badass for Healing and Justice」
メキシコ系移民の娘としてロサンゼルスで育った活動家で教育者の著者が、自らの半生の語りを通して社会的公正への取り組みと自身と似た境遇の女性たちが自分の生き方を自分で決めることの大切さを訴える本。タイトルの「チンゴナ」はスペイン語で本書の意図としては「bad ass women」の意味で、日本語だと最近流行った「わきまえない女」という言葉を思い出したけれども、メキシコ文化において同じ言葉の男性形である「チンゴン」は自分の意思を通せる強い男として肯定的な意味で使われるのに対し、女性形の「チンゴナ」は親や社会が期待するおしとやかな女性像に反する女というネガティヴなニュアンスを伴う。
本書で一番印象に残ったのは、著者が中学生時代に短期間だけストリートギャングに加わった時期の話。当時彼女が住んでいたロサンゼルス郡ハンティントンパークは失業率や貧困率、健康格差などの指標によりアメリカで最も絶望的な街の一つとされており、いくつものストリートギャングが抗争を繰り広げていた。著者の両親は教育熱心で、著者が良い成績を取ってそこから抜け出し良い仕事を得て成功することを願っていたが、どのギャングにも関わっていない子どもは暴力の対象となる危険な状態だった。そういうなか著者はギャングのメンバーだった同年代の女の子とともだちになり、その関係を通してギャングに加入したとみなされるようになる。それでも彼女は親に言われたとおり勉強に励み、テストで良い成績を取ったのだけれど、そのことをギャングのリーダーに知られると、なに良い成績取ってんの?的にからかわれる。「悪い成績を取ったらお父さんに叱られるから」と釈明する著者に対して、そのリーダーは「子どもの成績を気にする親なんているんだ」と驚き、その反応を見て「親が子どもの成績を気にする」ということが当たり前でなかったことにはじめて気づいた著者も衝撃を受ける。
その後彼女がギャングに加わったことが学校の教師たちに知られたけれど、彼女が教育熱心な家庭の子どもであり成績優秀であることを知っていた教師たちがそのギャングが抗争を起こす日に彼女を学校に一日中拘束するなどの介入があり、彼女がギャングに加わるような子どもでないことを理解したリーダーも彼女の脱退を認めることになる。このリーダーも、そしてほかのメンバーたちも、著者と同じ十代前半のラティーナの女の子たちだったけれど、著者と違い彼女たちは、家族に恵まれず社会からなにも期待されず見捨てられていた。著者はそこから一般社会への復帰のチャンスを与えられたけれども、同時にそれは親や学校の言いなりに「良い大学、良い会社」を目指す生き方に対する疑問も植え付けた。彼女はギャングを脱退してからも、恵まれない女の子たちの自助組織としての、そして社会の目を気にせずに自分の意思を通すためのストリートギャングの魂は持ち続けたし、それが彼女がチンゴナとしての自分を形作る一部にもなっている。
本書ではほかにもさまざまなエピソードを通して、彼女が考えるチンゴナとはどういう存在なのか、という話が展開される。チンゴナはこうだ、という書き方はされているけれども、自分はこう生きたい、このようにありたい、という意思と希望を全部チンゴナというアイデンティティに詰め込んだ感じ。わたしにとってチンゴナという言葉は一応知ってはいたけど身近な言葉ではないし、なにより周囲によって「チンゴナにだけはなるな」的な抑圧を受けた経験はないので、進んでチンゴナのアイデンティティを主張したいとは思わないのだけれど、彼女の姿勢には共感できる点がたくさんあった。Tanya Katerí Hernández著「Racial Innocence: Unmasking Latino Anti-Black Bias and the Struggle for Equality」に詳しいラティーノ社会における複雑な反黒人主義の話も書かれている。