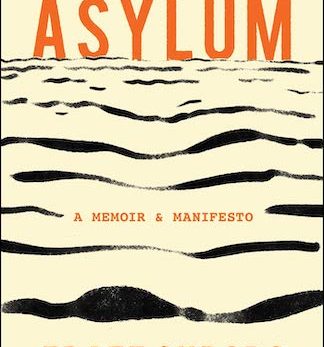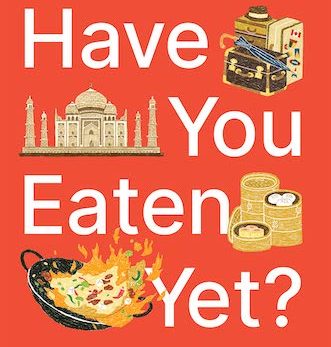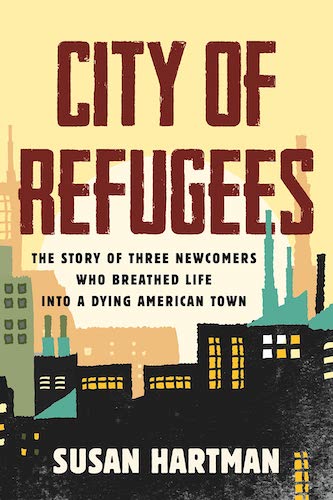
Susan Hartman著「City of Refugees: The Story of Three Newcomers Who Breathed Life into a Dying American Town」
かつて家電製品などを作る工場が建てられ栄えたが産業が海外に流出し荒廃が進むニューヨーク州の地方都市に移住した難民たちとかれらを取り巻く環境を長期にわたって取材した本。この街では第二次世界大戦後、アメリカの軍人がアジアに残した子どもたちの米国移住を支援する組織が立ち上がり、それをきっかけに世界各地の紛争で故郷を追われた難民たちが集まるように。この街のように第二次産業が衰退し人口流出が続く地域にとって、難民の受け入れは人道的に正しいだけでなく、経済の活性化をうながし、地元の人口と経済規模を維持するために必要な手段にもなっている。トランプ政権が難民受け入れを厳しく縮小した際には、アメリカに移住するはずだった難民たちの計画が狂っただけでなく、これらの街の人口や経済規模にも悪影響があったくらい。
この本ではとくに、ソマリア紛争で余所者として迫害されたバントゥー系ソマリア人の少女、イラク戦争でアメリカのメディアの通訳を務め殺害予告を受けたイラク人男性、そして旧ユーゴスラビアでの民族浄化を逃れてきたボスニア人女性の3人の人物と、かれらの家族やコミュニティを何年にもわたって追い、かれらがどのようなトラウマを抱え、どうアメリカでの生活に順応しようとしているかが語られる。家族に期待される伝統的な女性としての生き方とアメリカ人のともだちに影響されてモデルを目指すなど自由に生きようとする少女や、殺害予告から逃れて移住してきたのにどうしても祖国に帰りたくなって再び通訳の仕事でイラクに渡った男性、ヨーロッパ風のカフェを開こうと必死に働くけれども不良物件を掴まされたり一部の同胞の嫉妬の対象となり苦労する女性など、それぞれのストーリーは共感できるものが多い。生まれてはじめて使うガスレンジやはじめてついた担当医に戸惑ったり子どもの公立学校への受け入れで苦労するなど日常の大変さも含め、難民たちが移住したあと実際にどのように暮らしているのかという話はもっと知られるべき。
制度の問題として考えさせられることもいろいろ。たとえばまだ幼い子どもは比較的容易に英語を習得してクラスメイトに追いつくことができるけれども、より年上の子ども、とくにそれまで学校教育を受けていなかった場合は、数年のあいだに高校卒業相当の学力を身につけるのは難しい。ドロップアウトする生徒が増えると学校や教師が「無能」と判断されてペナルティを受け、予算を減らされたり解雇されたりするので、学校は水際作戦で生徒の入学を阻止しようとする。この問題は裁判となり、当たり前のことだけれど「教育を受ける権利の侵害」だとして入学阻止をやめるよう学校側は命じられたけれど、学校や教師の予算や待遇に影響する基準が「生徒のなかには難民の子どもがいること」を想定しておらず、十分な支援を与えるだけの予算がないばかりか、その責任がたまたま難民が多い地域の学校や教師に押し付けられることが問題。
また、難民に対しては医療をはじめさまざまな形で連邦政府による定住支援が提供されているけれど、1990年代の福祉制度改革いらい連邦政府による支援から見放された貧しいアメリカ人たち、とくにアメリカ生まれの黒人などマイノリティの人たちから見ると、外国生まれの難民のほうが優遇されているようにも見える。教育の質を向上するための制度や難民の定住支援の制度など、それぞれ合理的だし必要な措置がそれぞれ個別に存在していて、全体としてすべての人に生活や機会を保証するようにできていないという大きな問題が見えてくる。