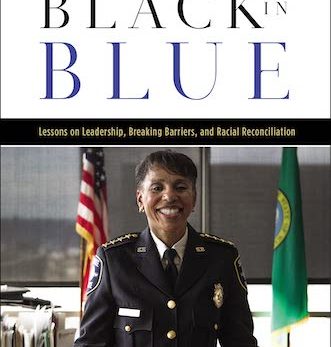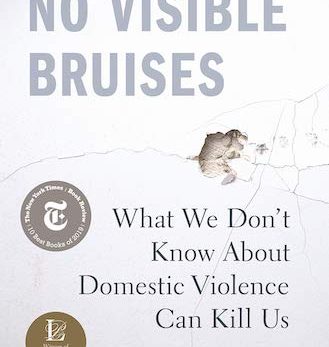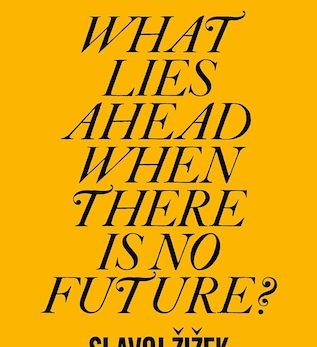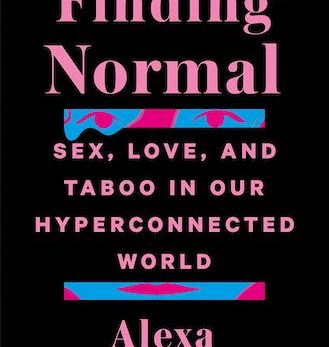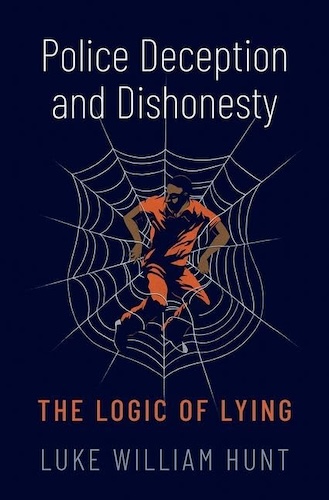
Luke William Hunt著「Police Deception and Dishonesty: The Logic of Lying」
FBI捜査官から哲学教授に転身した異色の経歴を持つ著者が、警察が日常的に使っている嘘や騙しを批判し制限を設けようと哲学的にアプローチする本。
警察が裁判で嘘の証言をすることは(めったに処罰されることはないとはいえ)もちろん違法だが、本書が扱っている嘘や騙しはそうした公の場面ではなく、捜査や取り調べの場面が大半。たとえば実際にあった例では、麻薬所持の容疑で捕まった女性に対して、実際にはそんな刑期ありえないのに最大で禁錮40年の刑になると脅して協力者に仕立て上げ、警察が捜査のターゲットとしている男性とオラルセックスをして口に出された精液を証拠として警察に提出するよう強要された事件がある。この事件では警察が女性を騙して性行為を強要したことが性暴力かどうか裁判に問われた結果、クオリファイド・イミュニティの原理により警察官は罪に問われなかったが、一般人の感覚としては許せない不正に見える。
セントラルパークでジョギングしていた女性をレイプしたとして5人の黒人少年たちが有罪判決を受けたがのちに冤罪であることが判明した有名な事件では、容疑者をそれぞれ別個に尋問中、捜査官は「ほかの少年は既に自白した」とか「もし無実だというならどうして被害者の体からあなたのDNAが出てきたのだ」と嘘をついて追い詰め、無罪を主張しても認められずかえって重い刑罰を受けると思った少年たちは無実なのに自白せざるを得なかった。このように、警察による嘘によって身に覚えのない犯罪を自白させられたり、あるいはたとえば「ポケットから麻薬の入った袋を落とした」として緊急逮捕や捜索の口実とするなど、家や車を捜索するのに必要な礼状を持たない警察官が嘘の理由をでっち上げて憲法上保証された権利を無視する例も多い。
カント哲学では嘘をつくことは常に悪だとされるかもしれないが、殺人犯に追われている知人を家に匿い、迫ってきた殺人犯に嘘をついて知人の命を守ることのように、本当に誰かの命や安全が脅かされているような場面において嘘が必要とされるという考え方には多くの人が納得するだろう。また、犯罪組織に潜入捜査している警察官が「お前は潜入捜査官か?」と聞かれて正直に答えなくてはいけないなんてルールがあったら、そもそも潜入捜査自体がなりたたない。しかしだからといって犯罪組織でもない普通の企業や団体に捜査官が送り込まれて組織内の誰も信用できないような社会に住みたいと思う人はいない。要するに、嘘や騙しを全面禁止するのは行き過ぎだけれど、現在のアメリカ社会においては警察は嘘や騙しを大した理由もないのに日常的に使いすぎており、それが黒人コミュニティをはじめ多くのコミュニティから警察が信用されない理由になっている。
被害者を追いかけている殺人犯は嘘をつかれても仕方がないように、犯罪を犯した人は警察によって嘘をつかれても仕方ないという考え方もある。先に裏切ったのだから自分が裏切られても仕方がないという論理だが、警察によって嫌疑をかけられた人が実際に犯罪を犯した人であるという確証がないことを除いても、さらなる問題がある。ハーヴァード大学の哲学者トミー・シェルビー(「The Idea of Prison Abolition」著者)は、警察が日常的に黒人コミュニティにおいて暴力をふるい、また嘘や騙しを使って人々を不当に陥れていることが、コミュニティの側に「警察の権威を認めない」理由を与えてしまっており、すなわちかれらにとっては警察こそが先に裏切った側だ。警察が持つ非対称的な権力や権限の面からも、そして多くの場合警察が先にコミュニティの信頼を裏切ってしまっていることからも、警察がさらに残されたわずかな信頼を崩すことは良策ではない。
著者は、警察は非常時に武力の行使が認められているが、不当な武力行使には制限がかかっており場合によっては処分を受けたり罪に問われることがあるように、警察による嘘や騙しの利用も本当にそれが必要な非常時だけに限られるような制約が必要だという。それはもっともな話なのだけれど、現実問題として不当な武力行使が横行し、ジョージ・フロイド氏の事件のように大きな話題として騒がれでもしなければ無防備な市民が殺されてもまず警察官の責任が問われることがないなか、どれだけ現実味があるのか。ワシントン州でも未成年の容疑者取り調べに際して「取り調べる側が嘘を言ってはいけない」という法案が今年提出されたけれど廃案になっており、警察による不正行為を止めようとしても警察組織の持つ政治力によって阻まれたり骨抜きにされるパターンが多すぎてうんざりする。