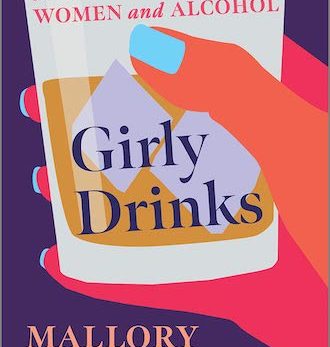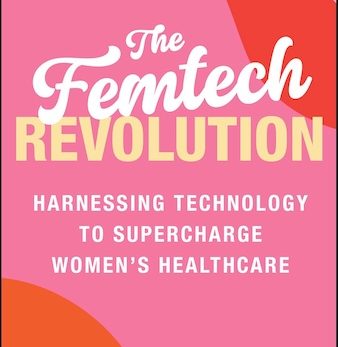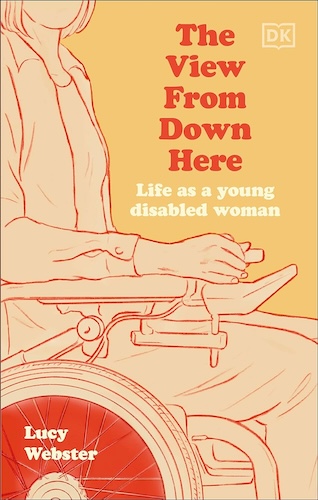
Lucy Webster著「The View From Down Here: Life as a Young Disabled Woman」
CP(脳性麻痺)のあるイギリス人ジャーナリストが障害者女性としての経験について綴った自叙伝。
障害のある女性として経験しているエイブリズム(健常者主義、障害者差別)とセクシズムが複合した社会的偏見や制約について、日常的なな話(ジャーナリストとして取材をしようとしても言語障害のせいで信じてもらえなくて電話を切られる、パブに行ったら建物が車椅子に対応していないというならまだしも「人が多くて危険だから」「音楽があなたに向いていないから」と入場を拒否される)から異性との交際、結婚、出産や子育てができないと決めつけられる問題まで、さまざまな話題に触れられている。
男性の障害者と異なる点について、障害のある女性はことさらセクシュアリティを否定されがちだったり、出会い系アプリなどを使ってデートしようとしても「介護させられたくない」と相手に断られることなどが挙げられる。女性はケアをする側である、という決めつけにより、男性障害者はパートナーとなる女性にケアを期待できるのに対し、女性障害者からは「ケアをする側にさせられたくない」と男性が逃げ出す。自分はちゃんとパーソナルケアアテンダントがいるし、そもそもそういう男性は妻が妊娠・出産したり病気になったり障害を負ってもケアしないつもりなの?と言う著者には、そうだそうだ!としか。
著者は幸いにして自分を受け入れてくれる女友達や職場に出会えたが、そうした交友関係や仕事を持てない障害者は少なくなく、とくに障害のある女性は仕事を得られない割合が高いし、仕事をしていても収入が少ない。ところが学生時代には女友達に恵まれた著者も、卒業して年齢を重ねるうちに仲間が次々に結婚・出産して共通の経験や話題を失い、孤立していくような気持ちになる。出会い系アプリでデートしようとしてうまくいかないので結婚相談所に登録しようとしたが相談所に断られ、それならばと養子斡旋所に連絡するも「あなたは親として安定した家庭を提供することができない」と断られる。女性は結婚して子どもを育てなくちゃいけないというのが古い思い込みなのは分かるけど、自分はそれをしたいのに社会がそれを認めてくれない、と絶望する。女性はこうあるべきだ、という理想を社会に押し付けられ、それに従おうとしても実際には不可能だというのは障害者だけでなく全ての女性が経験することで、だからフェミニズムは障害のある女性が抱える問題に真剣に取り組むべきだ、と著者は言う。
んだけど、うーーーーーーーん、これって今年出版された本なんだよね?個人が何を望むのかは自由だとはいえ内容がなんの説明もないままあまりにシスヘテロすぎるし、生産性があるかないかで障害者を差別するなと言いながら資本主義の問題には触れないし、なにより「障害があるからといって母親になれないのはおかしい」と言いながらそれを単なる社会的偏見として扱っていて優生思想との関連には話が進まない。なにより本書は、エイブリズムとセクシズムの交差はこれまでまったく問題とされてこなかったみたいな書き方で、これまで誰も論じてこなかったことを自分がはじめて取り上げているといった感じで書かれている。「障害の社会モデル」のことを最新の考え方みたいに書かれているのも違和感あるし。フェミニズムと障害者運動や障害学の交差には長い蓄積があるわけだし、なかでも黒人やその他の非白人の女性やクィアやトランス(それぞれ重複する部分あり)を中心としたディスアビリティ・ジャスティスの運動に関わってきたわたしにとっては、なんでいまさらこんな話になってるの?と思った。
でもそれはアメリカのフェミニズムの話であって、ショーン・フェイ著『トランスジェンダー問題』でトランスフォビアの背景として言及されていた帝国主義的フェミニズムの問題や、Louise Perry著「The Case Against the Sexual Revolution: A New Guide to Sex in the 21st Century」やMary Harrington著「Feminism Against Progress」といった保守主義フェミニズム系の本の出版に象徴されるように、インターセクショナリティの視点がアメリカほど普及していないイギリスのフェミニズムの文脈では本書は画期的なのかもしれない。てゆーか最近ちょっとイギリスのフェミニズムがいろいろ分からなくなってきている…