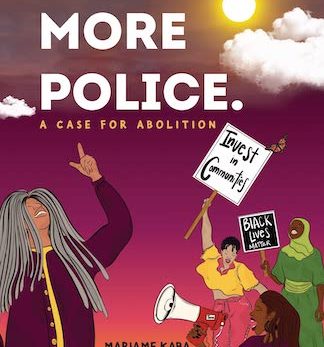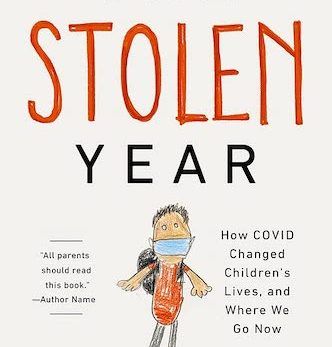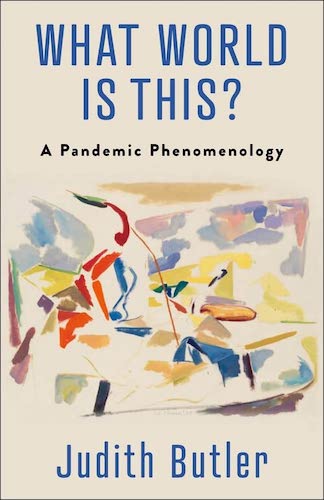
Judith Butler著「What World Is This?: A Pandemic Phenomenology」
ジュディス・バトラーせんせーの量産型新刊。この種の短い本を最近出しまくっている某出版社Vの本かと思ったらちゃんとした大学出版(コロンビア大学出版)の本だったw コロナウイルス・パンデミックによって変わってしまった世界とわたしたちの世界観をフッサール以降の現象学、とくにクィア現象学やフェミニスト現象学の立場から分析し、著者の原点であるメランコリーや2010年代の著書で論じていた「哀惜可能性」(grievability)の議論に繋げる(そこから本題に入るかと思ったら唐突に終わってしまった——紙の本だといま本のどのあたりを読んでいるか意識しなくても分かるけど電子書籍はいちいち見ようと思わないと分かりにくい)。
コロナによって世界が一変したという経験は世界共通だけれど、それは当初一部の人が言っていたような、世界共通の経験をもたらすことにはならなかった。もともと経済的な余裕のある人、先進国に住んでいる人、医療へのアクセスがある人たちが比較的安全にロックダウンをやり過ごす一方、途上国の人たち、貧しい人たち、仕事の選択肢が限られている人たち、普段から医療アクセスを欠いている人や人体に危険な住環境や労働環境にいる人たちらが、前者の生活を支えるために命をかけた労働を続けたり、人々の健康や安全に配慮されない監獄や施設での密集生活を強いられた。
また、先進国でワクチンが十分に提供され医療崩壊の危機が遠ざかると、障害者や老人、密集環境で生活あるいは労働している人たちの命を犠牲にしてでも経済の回復を図るべきだとする新たな優生主義が支持を広げ、またワクチンが行き届かない途上国の命はコストをかけて救う価値がないかのように扱われた。経済の停滞も人を殺す、経済を回さないと貧しい人こそ苦しむ、と言われたが、その貧しい人たちは十分な医療を受けられないまま危険な労働環境に駆り出され、生活のために命を危険に晒すことを強いられた。タイトルの「この世界はどうなっているんだ?」というのは、このような事態に対する、そしてわたしたちみんなが生きるに足る世界とはどのようなものか、という問いかけだ。
一方コロナウイルス・パンデミックは、わたしたちが個々の身体を持ちつつも、完全に独立した生命としては生きていないことを明らかにした。親しい人たちと会って触れ合うことも、亡くなった親戚の葬式に出席することもできない状況に置かれて、わたしたちはお互いに触れ合うことの大切さを痛感したし、自分が吐いた空気がまたほかの人の体内に取り込まれ、その人が吐いた空気をわたしが呼吸している、そしてそれを通してわたしたちは感染する身体であるとともに感染させる身体であるという事実にも気付かされた。前述のように自分だけ安全なところに隠れて自分の命を守ろうとした特権層ですら、物資や食糧やエネルギーを生産して届けてくれる労働者がいなければ生き続けることはできないし、ワクチンが行き届かない地域が地球上にある限りそこでコロナウイルスが変異し、先進国の人たちが接種したワクチンが通用しない新種が生み出されることはほぼ必然だと言える。
コロナウイルスによるロックダウンがはじまって数カ月後に世界中に広がったブラック・ライヴズ・マターの運動は、そして移民や先住民の権利を訴えるほかのさまざまな運動は、コロナによってあらためて可視化された哀惜可能性の構造的格差をめぐる闘争であり、コロナによる影響の格差と共通の要因を持つというだけでなく、ある意味まったく同じ問題によるものだ。しかしソーシャルメディアに投稿された警察の暴力による死は目に見えても、遠い国で、あるいは同じ国の自分が住んでいるのとは異なるコミュニティで、直接的な暴力ではなく組織的な剥奪により殺される命は目に見えにくい。
最初に書いたようにこの本はバトラーの量産タイプの短い本であり、多くの人たち、とくにブラック・ライヴズ・マターや相互扶助の活動を行ってきた活動家たちによってさんざん言われてきたことにバトラー的な味付けをした感じで、特に目新しい視点はないように思うのだけれど、バトラーの名前でこういう視点が出版されることで伝わる層もいるとは思うのでそれはそれで良いと思う。ただまあ、バトラーがこう言っていた、みたいに引用されるとしたらなんかイヤ。