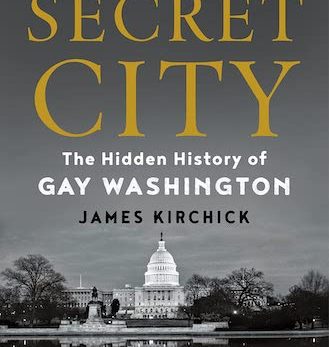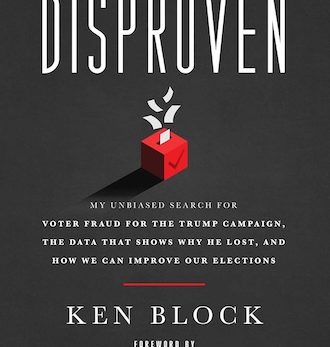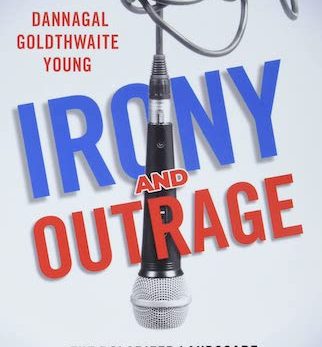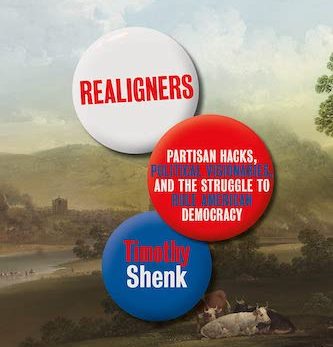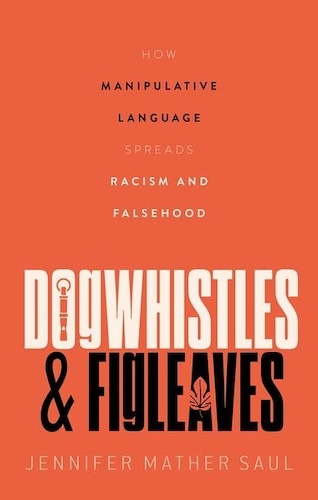
Jennifer Mather Saul著「Dogwhistles and Figleaves: How Manipulative Language Spreads Racism and Falsehood」
人種差別や事実に反する陰謀論などをそうと気づかれずに拡散するレトリック的な道具として知られるようになってきた「犬笛」とその関連概念である「イチヂクの葉」の現在的な用法をフェミニスト分析哲学者が論じる本。
「犬笛」とはもともと犬に命令を与えるために人間には聞こえないけれど犬には聞こえる周波数の音を出すことができる笛のこと。ここから転じて、人種差別的な支持者に「自分はあなたたちの仲間だ」というメッセージを発しつつ、それ以外の人たちには人種差別者だと気づかれないように工夫された表現のことが政治の分野では「犬笛」と呼ばれる。人種差別的な用例が古典的だが、もちろんほかの差別や陰謀論などにも適用される。こうしたレトリックは、「差別はいけない」という規範がある程度社会に広まったとき、一見そうした規範に反していないように見せかけつつ、差別主義者たちに支持や協力を求めるために発達してきた。奴隷制や人種隔離政策の温存をそのまま訴えるのではなく「州の権利」という名目を訴えるのはその古典的な例。
しかし現在の社会において、こうした古典的な犬笛は少なくなってきている。「州の権利」が人種差別を隠すための方便であることは既に知られているし、同じように「都市中心部の犯罪」や「福祉不正受給者」が黒人に対する差別的なステレオタイプを想像させるシグナルであることも周知されている。そこには、「隠された意味を知らない一般人と、自分たちに向けられたメッセージを解読できる一部の差別主義者」という構図は既になく、差別主義者もそうでない人も、多くの人たちがそれが差別的なイメージを流用したメッセージであることに気づくようになっている。しかし問題は、一般的にそれが差別的な犬笛だったものだという理解が広まったとしても、すべての人がそれを認識しているとまでは言えないので、犬笛を発した当人に差別的な意図があったかどうか確定することはできない点だ。すなわち、その表現が犬笛として使われることがわかっていても、それを発した人が犬笛として使ったのか、それともそうした意図はないけれどたまたま同じ表現を使ってしまっただけなのか、客観的に判断することはできない。
こうした解釈の不確定性は、差別のことを構造ではなく個人的な好き嫌いの問題だとか、結果ではなく意図に注視すべきだといった、白人のあいだで一般的な差別に関する浅い認識の弱点を突くことで、発言が差別的であったかどうかという判断を不可能にしている。一部の人たちはその発言は差別的だと正しく認識し批判するが、もともとその発言をした政治家の支持者だった人たちは逆に「リベラルは些細なことで差別だ差別だとでっちあげて騒いでいる」と反発する。その結果、犬笛はかつてのような秘密のコードでなくなったにも関わらず、いまも機能している。
「イチジクの葉」はトランプが多用するレトリックで、単体でははっきりと差別的だと認識される表現に付け足すことで、その表現が差別なのかどうかという疑問の余地を生み出し、差別だという批判者と差別ではないという支持者の対立を巻き起こす表現を指す。たとえばトランプが大統領選挙出馬を発表したスピーチでアメリカに入国するメキシコ人は犯罪者だレイピストだ、と差別的な発言を連発したあとに「一部はいい人もいるだろうけど」と付け加えることで「トランプはメキシコ人全員が犯罪者だと言っているわけではない」と支持者がトランプを擁護する余地を残したことに典型的。「自分はレイシストではないけれども」とか「自分には黒人の友人がいる」など、濫用されすぎてもはやパロディにしか思えないようなイチジクの葉ですら、その発言者を支持している人にとっては「この人はレイシストではない」と安心する要素になり得る。トランプは頻繁に人種差別的な発言を繰り返しながら、こうしたイチジクの葉を多用することにより、支持者たちに「トランプはレイシストではない」と納得させ、逆にトランプをレイシストと批判するリベラルのほうが批判的人種理論によっておかしくなっているのだ、と認識させている。
まあ犬笛にせよイチジクの葉にせよ、そもそもの人種差別に関する認識が浅すぎることが問題なんだけれど、後半では真実や陰謀論をめぐる議論において犬笛やイチジクの葉がどう機能しているかという分析があり、こちらも興味深い。あとがきによると、著者はいまソーシャルメディアなどでトランスジェンダーの人たちに対する差別が犬笛やイチジクの葉を通して拡散されていることに関心を持っており、次にそれらの分析を行おうとしているとのことなので、注目したい。