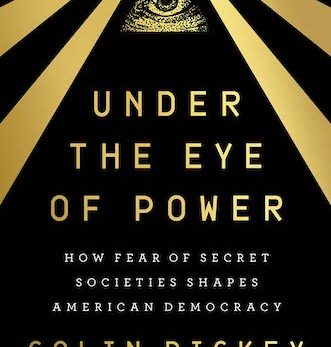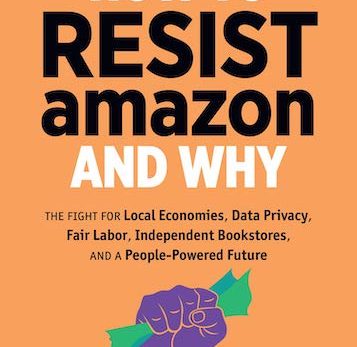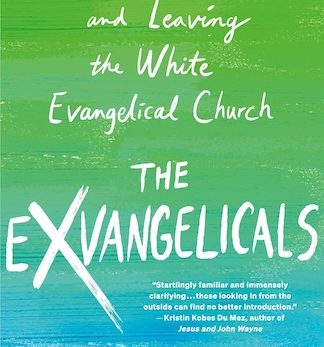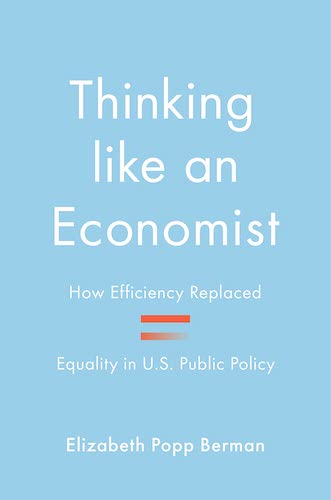
Elizabeth Popp Berman著「Thinking Like an Economist: How Efficiency Replaced Equality in U.S. Public Policy」
第二次世界大戦後のアメリカで急速に広まった、経済学的なアプローチが経済政策だけでなく広い分野の政策において採用されるようになった歴史的な背景と、経済学的手法を採用した結果リベラルが失ったものを指摘する本。戦時中、アメリカ政府はマンハッタン計画などを通して各分野の優秀な研究者たちを結集したけれども、戦後ソ連との冷戦がはじまるなか、研究者たちが分散してしまうのを恐れランド研究所など政策研究の拠点を設置した。経済学の分野ではロナルド・コースらを筆頭に経済学を政策決定に応用する「法と経済学」の研究が進み、なかでもランド研究所とともにシカゴ大学とハーヴァード大学がその中心を担った。そうしたなか、ジョンソン政権が打ち出した「偉大な社会」政策によって貧困撲滅や人種平等などの目的のために政府が期待される役割が大きく拡大すると、どのような政策を取ればそれらの目標がより効率的に達成できるのかという議論が広がり、経済学者たちが政府内外で力を増していく。
とはいえレーガン政権が誕生する1980年代までは、政策に効率性を求める考えはそれほど強くなかった。たとえば環境保護のために制定された1963年の大気浄化法や1972年の(改正)水質浄化法では、汚染物質の排出に対して基準が設けられ、企業には一律にその基準の遵守が求められた。それに対して二酸化硫黄や窒素酸化物が起こす酸性雨が問題とされた1990年の大気浄化法では排出権売買の制度が作られた。これは一定の上限を設けたうえで汚染物質を排出する権利を設置し、より効率的に汚染物質排出を削減できた企業・業界が削減にコストがかかってしまう企業・業界に排出権を売る市場を作ることで、一律に排出基準を決めるよりも効率的に汚染物質排出を減らすための仕組み。
また貧困者に対する住居支援、健康保険の提供などの政策目標に対しても、政府が直接公共住宅を建設したり国民皆保険制度を作るのではなく、民間の住宅を借りたりや健康保険を買うための助成金を出すという形の政策が推奨された。貧困層だけをターゲットとして助成金を出せば助成金を必要としない人の健康保険の費用を政府が支払う必要がないし、市場競争によって価格が決められるのでより効率的だとされたのだ。また、より多くの人が大学教育を受けられるようにするための施策として、大学に助成金を出して授業料を安く(あるいは無償に)するのではなく政府系の学生ローンを拡充したのも、支援の対象をそれを必要とする学生だけに絞って予算を浮かせるとともに、大学間での競争を通して大学教育の向上を促すためとされた。
ここで著者が指摘するのは、こうした経済学的アプローチを採用した効率重視・市場重視の社会政策は、はじめは政府の役割に否定的なシカゴ学派の保守派経済学者ではなく、むしろハーヴァード大学に多かった、政府による社会問題の解決に積極的なリベラル派の経済学者たちによって推し進められたことだ。かれらはジョンソン政権以来の「大きな政府」の政策目標を肯定しつつ、その実現のためのより優れた方法として、貧しい人に対する必要に応じた助成金の支給や、民間や大学の市場競争などを通した効率的な目標実現を主張した。シカゴ学派も一種のベーシックインカムに繋がる「負の所得税」など社会政策を効率化する提案をしたが、かれらが影響力を持つのはレーガン政権以降だった。
ジョンソン政権では政治的に決められた政策目標を実現するためのより優れた方法を決めるために経済学的アプローチが採用されたが、レーガン政権になると政策目標の是非を決める段階で経済学的アプローチを通した判断が求められるようになる。たとえば健康に害がある汚染物質の排出に関して、ジョンソン政権では人体に危険があると考えられている排出量をまず算出して、それより少し余裕を持って排出量の上限を定めていたが、レーガン政権では「汚染物質の排出によるコスト」と「汚染物質を除去するためのコスト」を比べて前者のほうが大きい場合でなければ規制はするべきではない、という考えが採用された。ここで「汚染物質の排出によるコスト」とされるのは、健康被害によって失われる労働力や生産性、医療コストの増大、不動産価格の下落など試算がしやすいものだけであり、健康被害の地位的・人種的偏りによる不公正さや未来の世代が失う素晴らしい環境など、具体的な数字に換算しにくいものは計算に含まれない。また「本当にそれを必要とする層だけ」を政府が支援することは一見たしかに効率的だけれど、レーガンの選挙戦略が煽った「まじめに働かずに支援だけ受けている」などといった貧困層に対するバッシングを生み出し、実際には必要なだけの支援の実現が難しい、という政治的な現実もある。
その後の各民主党政権でも、炭素排出権売買やオバマ政権による健康保険改革––国民に対して市場を通して民間の健康保険に加入することを義務付け、保険料が支払えない人たちに助成金を出す仕組み––など、経済学的アプローチはあらゆる政策的議論の前提として維持されている。党内の進歩派あるいは左派と呼ばれる勢力は、国民全員が加入する公的保険の実現や、将来の世代のために住みやすい環境を維持するための規制、学生ローンに苦しむ人たちの救済など、平等や未来への希望に繋がる価値観を重視した政策を主張してきたが、かれらの主張はごく最近まで党の主流派の支持を得られてこなかった。
一方、共和党や保守派の内部では、保守派の主張に都合がいいときは経済学的アプローチが援用されたけれども、保守派の価値観に反するような場合はその限りではない。たとえばシカゴ学派や保守系経済学者たちがいくら「負の所得税」を主張しても、多くの保守論客や保守活動家たちは、労働の価値を重視するべきだ、怠け者を甘やかすな、との考えからそれを支持しようとはしない。その意味で、経済学的アプローチの政策応用を一貫して進めてきたのは、保守派ではなく、むしろリベラルな政策目標を掲げる民主党側経済学者たちや経済学的アプローチを取る政策専門家たちだ、と著者は指摘する。民主党左派のなかには、平等や健康など抽象的な価値を「正しく」算出して試算に盛り込むことで経済学的アプローチの内側からその欠点を克服しようとする動きもあるものの、それがうまくいくどうかは未知数。
わたし自身、経済学的アプローチを重視する政策を支持しがちな立場で、たとえば炭素排出権売買や炭素税の提案に対して環境保護派が「料金を払えば環境破壊しても良いというのはおかしい」と反発しているのを見ると「いやいやそういうことじゃないんだけど」と思ったりもする。と同時に、経済学的アプローチによって取りこぼされるもの、見えにくくなるもの、そして理論上は効率的な弱者救済措置が実際には頓挫している、などの指摘は重要で、深く考えさせられた。