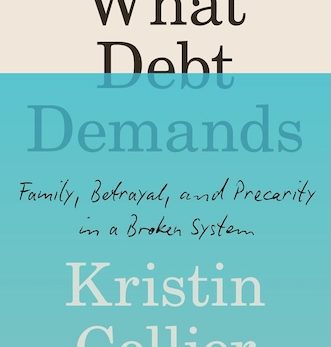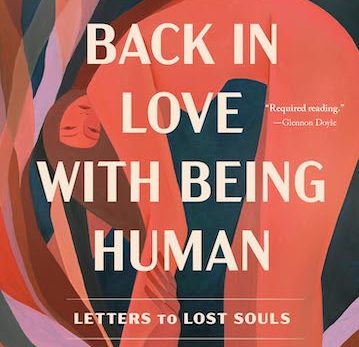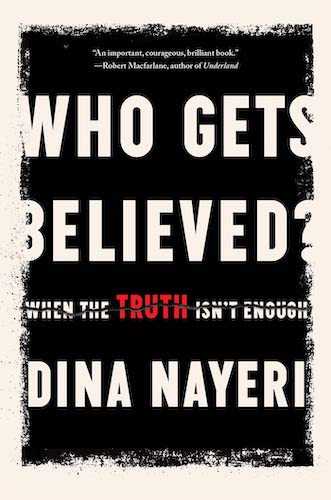
Dina Nayeri著「Who Gets Believed?: When the Truth Isn’t Enough」
キリスト教に改宗したことでイラン政府から迫害を受けた母親とともに難民としてアメリカに移住し、のちに作家として有名になった著者が、彼女自身が経験した難民として認定を受けるための審査をはじめ、病院で、裁判で、教会で、そして助けを求める親戚への対応において、誰の言葉が信じられる、誰が疑われるのか、それはどうしてか、個人的な経験と難民支援の現場の話などを交えて考える本。
子どものころ、母親に連れられてイランを逃れ難民キャンプを転々とした著者は、キリスト教に改宗したことで迫害を受けたと訴える母親の証言が真実かどうか疑う係官により、彼女が母からキリスト教の聖書の内容をどれだけ教わっているのか、クイズのようにして問い詰められる経験をした。しかし難民申請の現場ではそれはまだ甘いほうで、政府によって鞭で打たれたり皮膚に熱く熱した金属を押し付けられて焼かれた拷問の被害者たちに、欧米など人権保護を標榜する受け入れ国の係官たちは容赦のない尋問を行う。その傷はほんとうに政府や多数派武装勢力によるものなのか?欧米に移住するために自分で付けた、あるいは誰かに頼んで付けてもらった傷なのでは?仮に政府によるものだとして、それは人種や宗教など保護の対象となる理由に基づくものなのか?移住しなくても平和に暮らせる方法はあるのでは?と。難民認定されるためには規則で決められた特定の要件を満たさなくてはいけないけれども、難民の多くはその規則が何であるのか知らないので大切なことを言いそびれたりするし、逆に何を言うべきなのか知っている人は「詳しすぎる」と怪しまれたりする。
難民申請の現場では、係官は申請者たちは嘘をつくという前提で訓練され、一人でも多くの申請者に不認可の裁定を出すことが評価される。しかも係官たちは個別の国でどのような人権侵害が行われているか詳しく知っているわけではなく、同じ国から同じような人権侵害を訴える申請者が続けば「話を合わせている、怪しい」と疑い、また独特な訴えであれば「そんな話は聞いたことがない、怪しい」と疑われる。性暴力の被害や同性愛者であることを理由とした迫害など、赤の他人に話しづらい事情がある人たちが「隠し事をしている」と判断される。ある例ではある例ではウガンダの警察によって性的指向を矯正することを目的としたレイプの被害を受けたレズビアンが、ウガンダでは実際にそういう被害を受けた人が大勢いるにも関わらず、「性的指向をレイプで矯正できるはずがないのでそんなことをするはずがない」という係官の判断によって難民申請を却下された。真実を語ることは、それが事実であると受け入れられるためには十分ではない。
著者はアイビーリーグの大学を卒業、マッキンゼーに就職し、さらにハーヴァードでMBA(経営学修士)を取得する。そのなかで彼女が学んだのは、どうやってコンサルタントである自分を顧客企業に信用させ、自分のアドバイスの価値を認めさせるかという、信用のテクニックの数々。それは服装を含めた外面的なプレゼンテーションからメタファーを多様するレトリックまで、彼女がイラン人難民の娘として必要に迫られて学んできた技術をより洗練したものだった。こうして、ただでさえはじめから社会的信用に恵まれた白人アメリカ人のエリートたちがその技術を独占する一方、多くの難民や貧しい移民たちはなんの武器も持たずに予め敵対的なステージに立たされている。
同じことは病院の緊急治療室でも毎日起きている。貧しくて医療を受けられない人たち、とくにホームレスの人たちは、かかりつけの医者がいなくても緊急治療室なら診察を受けられることを知っているけれども、かれらに対して病院のスタッフは暖かい部屋でベッドに横になって休みたいだけ、話相手が欲しいだけ、ドラッグが手に入らないから鎮痛薬が欲しいだけ、と決めつけられ、冷たい目を向けられるばかりか、痛みや病状を訴えてもまともに診療すらしてもらえないことも多い。その人に薬物依存があったとしても、それは痛みに対する治療を必要としていないことにはならないのだけれど、一旦「鎮痛薬を求めている」と判断されてしまうとまず処方してもらうことはできない。では貧しい人が本当に鎮痛薬を必要としているとして、何と言えばいいのか?ここでも難民申請の現場と同じように、ルールを知らなければ必要なものが手に入らないけれど、知りすぎているとまた逆に疑いを持たれるというなか、緻密なパフォーマンスが必要となる。
難民申請の現場についてのこれでもかという不正義の描写と並んで本書を読んでいて息が詰まりそうになるのは、全般を通して言及される著者のパートナーの弟の話。弟には精神疾患があり頻繁に自殺をほのめかしているが、著者から見ると、やればできるのに家族に依存していつまでの自立しようとしない、恵まれた白人家庭の甘えた息子にしか見えない。イランの家庭ならかれがそんなに甘やかされることはない、いっそイランに送り込んでやりたい、と辛辣なコメントをパートナーやかれの家族に伝えるが、かれらはそれに部分的に同意しつつ、かといってかれを支えるのをやめてホームレスになってもいいとは思えない、とかれを支え続ける。自殺するという脅しも何度も繰り返されると著者だけでなく医者らも信じなくなった。しかし結果的に、かれは自殺してしまう。著者はいまでもかれが本気で自殺しようとしていたとは思えず、死ぬつもりはなかったのについうっかりやり過ぎてしまったのでは、と思わないでもないものの、同時にかれを信じなかったことを、そしてかれのことをさんざん悪く言ってきたことを後悔する。恵まれた家庭に甘えている人間だって苦しみは本当だし、自殺を脅しに使っている人が本当に自殺しない保証はない。
難民認定や刑事裁判、医療、自殺予防などさまざまな問題に触れ、それらが社会的・経済的階層によって形作られていることを指摘しつつ、本書はそれらへの制度的改革を提唱することを目的とはしていない。そうではなく、わたしたちが人権侵害の被害者やその他の支援を必要としている人たちに、真実を語ることではなくわたしたちの偏見に寄り添った演技を求めていること、そして同時にその演技を暴いてはかれらを貶めようとしていることを指摘し、それに向き合うよう仕向けている。これは、非人道的な国家による制度だけの話ではなく、わたしたちは身近な人たちとのあいだにすらそうした構図を作り出してしまっている。すっきりとしないけれど、とても考えさせられる一冊。