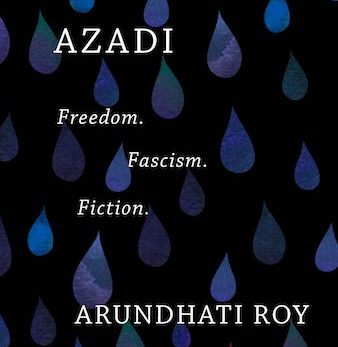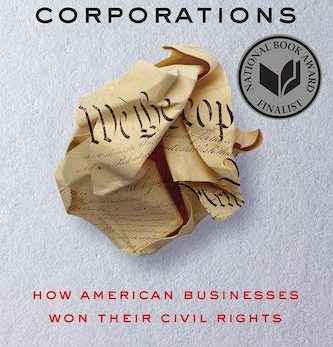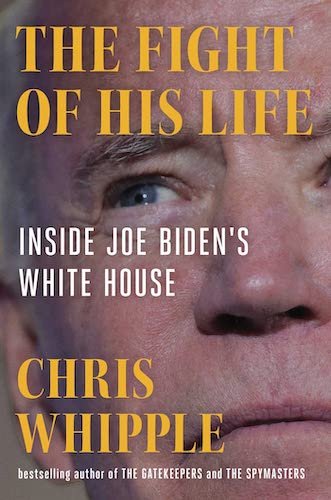
Chris Whipple著「The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House」
バイデン政権のはじめの2年間の内幕を追った本。前任者に比べ地味だしドタバタしてなさそうだし暴露話もそうないだろうし、つまらないのでは?と思いながら読み始めたけど、思っていた以上におもしろい。ちょうど数日前に辞任を発表したロン・クライン大統領首席補佐官やその後任と目されているジェフ・ジエンツ氏ら側近がどのように動いていたのかも知れてタイミングもとても良かった。
本書によると、バイデンが三度目の大統領選挙への立候補を最終的に決意したのは、トランプ就任一年目の2017年の夏、ヴァージニア州シャーロッツヴィルに集結した白人至上主義者らの集会に抗議した反差別派活動家が白人至上主義者に轢き殺される事件が起きたとき。「どちら側にも良い人がいる」と白人至上主義者と反差別主義者を対等に扱ったトランプの発言を聞き、それまでにも多数の問題発言を繰り返していたトランプがついに超えてはいけない一線を超えたとバイデンは痛感した。かれが2020年の選挙の、そしてその後の政権のスローガンとした「わが国の魂をめぐる闘争」という言葉が生まれたのはこの時で、側近からはそのスローガンは選挙を有利にはしないからやめておけと何度も言われながらも使い続けた、バイデンの信念を表す言葉となっている。
本書は2020年の選挙後、敗北を認めないトランプが政権引き継ぎを拒否し平和的な権力移行が行われるか懸念された場面からはじまる。トランプが司法省や国防省の上層部を自分に忠実な人物に置き換え、軍を使って選挙結果認定を遅らせようとするなか、バイデンとその側近らはペロシ下院議長ら第三者を通して政権内部の政治的空白を避けようとする人たちと政権移行の準備を行う。1月6日にトランプ支持派による連邦議会襲撃が失敗に終わっても、最後の最後まで本当にアメリカの民主的な政権移行は危うかったんだなと再確認。しかもコロナパンデミックは収まらず経済も停滞、多くの人たちが失業やケアの不足に苦しむなか、トランプ政権の行動によってアメリカは世界から孤立し同盟国の信頼を失った状況。
アフガニスタン政府と国軍の能力を過剰評価して同国からの撤退で失敗した際には政権内部で責任の押し付け合いがあったし、バイデン政権の目玉政策の一つであるBuild Back Better Actをめぐって党内左派と保守的なマンチン・シネマ両議員とのあいだで身動きが取れなくなってどちらからも叩かれるようなこともあった。コロナウイルス・パンデミックについてはワクチン接種が予定以上のペースで進んだことに気を良くして早々と勝利宣言してしまったけれど、ワクチンに対する陰謀論やイデオロギー的な拒否反応を甘く見すぎていたし、デルタやオミクロンの登場によりマスク着用や学校再開の是非をめぐって迷走もした(けれど、その迷走の一部は科学そのものの不確かさが原因であり、ジエンツを中心に科学的かつ透明な政策決定をしてきた、と言うこともできる)。そういったさまざまな失敗はあれ、大統領就任直後にAmerican Rescue Plan(コロナ対策、経済支援)、American Jobs Plan(インフラストラクチャー整備、気候変動対策)、American Families Plan(社会的セーフティネット整備)という3つの巨大政策を提案、マンチン・シネマとの妥協により削除された社会的セーフティネットの部分を除きその多くを実現させたことは、公民権法など20世紀後半のアメリカの方向を決定づけたリンドン・ジョンソン大統領以来の立法的快挙だとされる。
そしてそれ以上にバイデンの未来の評価を大きく左右しそうなのは、いまだに出口の見えないロシアによるウクライナ侵攻をめぐるバイデンの対応。ヨーロッパにおける、そして民主国家に対する第二次世界大戦以降最大の危機に際して欧米がこれだけまとまることができたのは、バイデンが副大統領だった2014年にロシアがウクライナのクリミアとドンバスに侵攻した際に足並みをそろえることができなかった反省を活かし、まだほとんどの人が「まさか本当にウクライナ全土に侵攻するはずがない」と思っていた早い段階からロシアの計画を示唆する情報を共有し、「万が一のために」と対応を協議していた動きのおかげだ、と本書は指摘する。そのなかにおける、あまり知られていないカマラ・ハリス副大統領の活躍は、彼女が外交経験をきちんと積み実力を付けてきていることを示している。
バイデンにとって、かれを三度目の大統領選立候補へと駆り立てたシャーロッツヴィルの悲劇とそれに象徴される白人至上主義の国内での拡大は、ロシアのプーチン大統領が体現する外国の権威主義の増長と密接に繋がっている。勢いあまってプーチンの退陣を要求するような発言をしてしまって「そんなこと言ったら停戦できなくなるだろボケ」と世界中から叱られたけど、アメリカの政策として退陣を要求しているのではなく一人の人間としてブチャ虐殺などの戦争犯罪が許せないのだ、というのはかれの本音だろう。わたし個人にとってはいろいろ不満がある大統領なのだけれど(アニタ・ヒルさんへの扱いとか、いまだに許せない)、基本的に善良でまともな人間が大統領であることはほんとうに大事だ。