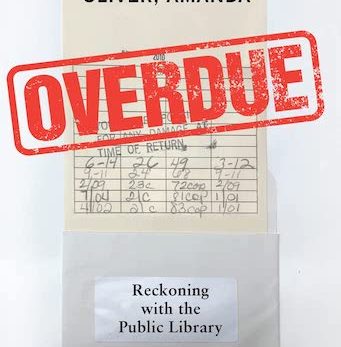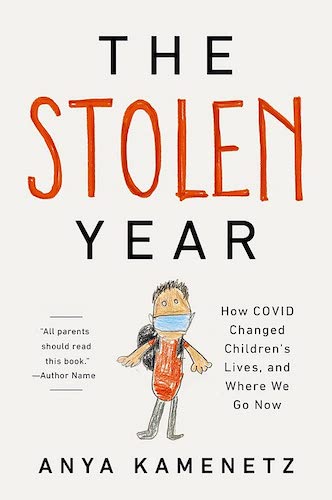
Anya Kamenetz著「The Stolen Year: How COVID Changed Children’s Lives, and Where We Go Now」
コロナウイルスパンデミックが最初の1年間で子どもたちの生活にもたらした重大な影響についての本。著者はニューオーリンズ出身のジャーナリストで、新人記者だったころニューオーリンズを襲った特大ハリケーン・カトリーナ(2005年)による人々の生活の破壊を目撃した経験から、早くからパンデミックによる子どもたちへの影響を懸念し発言してきた。彼女によると、当時ハリケーンによって国内難民となった子どもたちは学習のペースを乱され、本来のペースに追いつくのには平均で2年かかった。そのあいだに卒業する年齢に達した子どもたちは遅れを取り戻すことができず、いまに至るまで学歴や失業率の点からほかの世代より不利な状況にある。
アメリカの学校について特筆すべきことは、社会的セーフティネットが脆弱で子育て支援や生活保護、医療保険などの点においてほかの先進国より劣悪な環境に置かれているアメリカにおいて、公教育は唯一アメリカ全土ですべての子どもに保証された権利であるということだ。さまざまな問題を抱えているとはいえ、毎日一定の時間のあいだ親は子どもを学校に預けることができ、家がどんなに貧しくても、それどころか非正規に滞在している移民の子どもでも、すべての子どもたちは教育とともに食事や簡単な医療を受け、クラスメイトらとの社会的繋がりを維持することができる。と同時にJack Schneider & Jennifer Berkshire著「A Wolf at the Schoolhouse Door: The Dismantling of Public Education and the Future of School」にも書かれているように公教育は、公民権運動時代に行われた人種隔離政策の撤廃をきっかけとして右派による継続的な攻撃の対象となった。
コロナウイルスパンデミックによる学校の閉鎖は、教育の停滞だけでなく、家庭におけるケアの不足とともに子どもたちのあいだに深刻な食事不足や精神的トラウマをもたらした。公立学校の閉鎖はまた、速やかにリモート教育に対応するだけの余裕のある学校や地域とそうでない地域の格差を深刻化させたほか、障害のある子どもたちや英語を母語としない子どもたちへの支援が後回しにされた結果、多くの子どもたちの将来に大きな悪影響を残した。子どもたちのメンタルヘルスへの影響についての章では、環境の激変や亡くなった親族を看取ったり追悼できない状況のなか鬱に陥ったり、毎日のリモート授業で自分の姿や部屋をクラスメイトと比較してセルフエスティームを損なったり摂食障害を起こしたりした子どもたちの話が紹介される。本書では周囲の支援を受けて立ち直ることができた子どもたちの例だけが紹介されているものの、そのような環境に恵まれない多くの子どもたちが将来に渡って深刻な問題を抱えるであろうことが示唆される。
本書は2020年の春から2021年の春までの一年間のあいだ、ロックダウンやマスク着用についての公衆衛生上の論争が政治化されるとともに、ブラック・ライヴズ・マター運動や大統領選挙の結果をめぐる世間の分断が公衆衛生行政を麻痺させ、そのなかでパンデミックが子どもたちに与える影響への配慮が後回しにされてきた事実を告発する。学校の閉鎖と再開の是非について起きた議論については、少しでも早く再開させようとする政治家とそれに抵抗する教職員組合、という構図で報道されてきたけれども、著者は再開に向けたプランのないまま閉鎖し、安全に再開するためのプランのないまま突然(リモートと対面の二つのモードに加え)ハイブリッド授業を強いるなどして再開を急いだ政治の失敗を強く批判する。他国に比べアメリカは学校閉鎖を極端に長引かせ、それによって多くの子どもたちの未来を傷つけたけれども、早期再開派はそもそもコロナを脅威と認めておらず、再開するために必要な対策に反対していたように社会全体に子どもたちを重視して安全に再開しようという姿勢が欠けていたことを思うと、もっと早く再開していれば良かったとも言えない。
読みながら、パンデミック初期の息苦しさ、突然生活の基盤から切り離された多数の人たちの苦しさやトランプ大統領を筆頭に政府がわたしたちの命を守ろうとしてくれない悔しさを思い出し、どんよりとした気分になった。わたしの周辺にも、2020年に高校を卒業して大学に行く予定だったのにリモート授業になって学習意欲を失い、オンラインゲーム以外での人との交流を失い、大学進学を取り止めた人がいる。「失われた一年」が失われた世代・失われた未来にならないように、急遽パンデミック世代の子どもたちを支援する取り組みが必要。