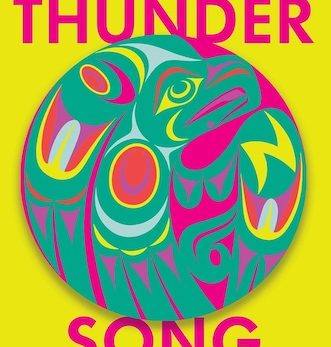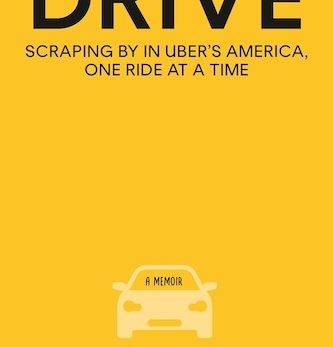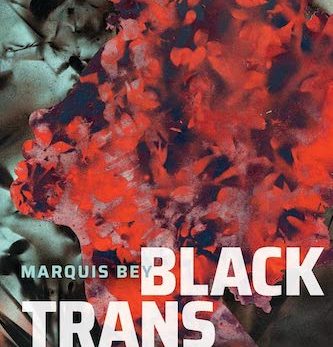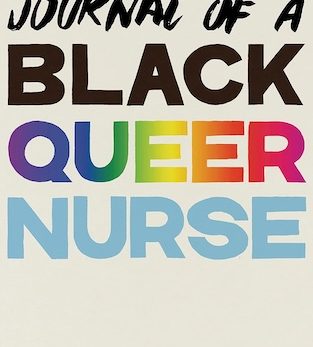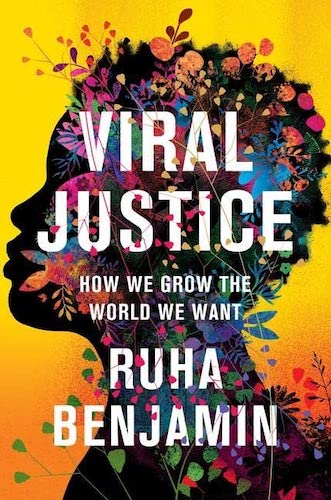
Ruha Benjamin著「Viral Justice: How We Grow the World We Want」
前著「Race After Technology」では一見人種中立的なテクノロジーが既存の権力関係を反映した結果として反黒人主義的に機能する仕組みを指摘した著者が、コロナ危機とブラック・ライヴズ・マター運動の世界的拡大の最中、個人史を振り返りながら新たな政治運動のあり方を考える本。
本書のタイトルにある「ウイルスの(に関する)正義」という言葉は、コロナウイルス・パンデミックにより明らかにされたさまざまな社会的不公正に対抗するという意味と同時に、ウイルスのように目に見えない小さな試みが周囲に感染して大きな変化を巻き起こしていく、という運動のあり方を指し示している。前者については白人に比べて非常に多くの黒人やラティーノがコロナウイルスに感染したり亡くなったりしたこと、アマゾンやドアダッシュなどのIT企業が史上空前の売り上げを記録し富裕層の資産が膨れ上がるいっぽうアマゾンの配送所で働く人たちや食品などを配達する運転手たちが安い賃金で過酷な労働を強いられ体を壊していること、多くの女性にケア労働の責任がのしかかり賃金労働を辞めざるをえなかったことなどが語られ、コロナをめぐるさまざまな政策が人々の命に優先順位を付ける行為、すなわち現代における優生主義であることなどが指摘される。
後者について著者が最初に挙げるのは、著者自身の出身地でもあるロサンゼルスのサウス・セントラルで「ギャングスタ・ガーデナー」として知られTEDトークも行ったロン・フィンリー氏。サウス・セントラル地域は「ドライブバイ(対象に車で近づいて銃撃しそのまま逃走する犯罪行為)とドライブスルー(ファストフード店)」ばかりだ、と表現するフィンリー氏は、ドライブバイよりもドライブスルーに象徴される新鮮な野菜や果物の欠如のほうが多くの地域住民を死に至らしめていると考え、仲間たちと一緒に自宅の前の車道と歩道のあいだの草地に野菜を植え育てはじめる。市は公有地の不法使用だとしてフィンリー氏を逮捕しようとするけれど、それがメディアに報道されると市議や市民からの支持が集まり容認されることに。市の許可や予算を得るわけでもなく自分たちの身の回りでできることに取り組んだ小さな試みは、地域の住民の健康を取り戻す一歩となるだけえなく、若い人たちを巻き込み自分たちの食べる野菜や果物を育てる楽しみと誇りを与えた。
著者がイメージするのはこのように、いまの社会の問題––貧困だったり人種差別だったり警察による暴力だったり––に対してなにか一つの大きな解決を提示するのではなく、何百何千何万もの小さな取り組みを試行し、拡散させ、積み重ねることだ。これはアボリション・フェミニズムの立場から各地で行われている無数の実験的取り組みを紹介し共有するプロジェクト「One Million Experiments」の趣旨とも重なる。
ここでは著者の個人史の部分には触れないけれど、彼女の家族の話や過去の経験がどのように「Race After Technology」でも見せたシャープな分析に繋がっているのかよく分かる、親密さと希望のある本だった。