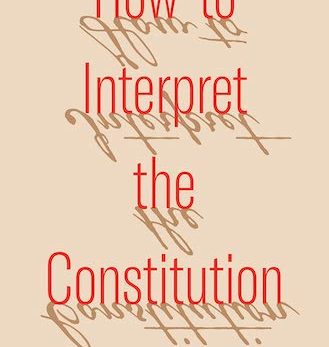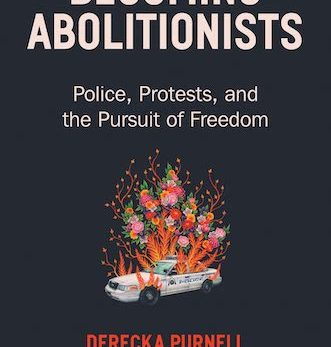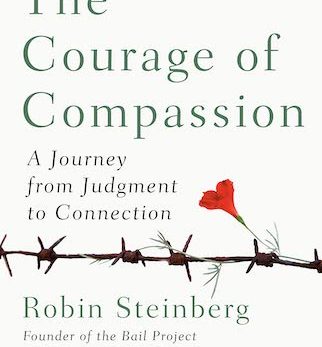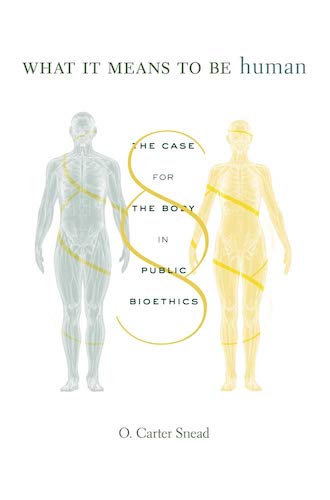
O. Carter Snead著「What It Means to Be Human: The Case for the Body in Public Bioethics」
ローマ教皇の生命倫理アドバイザーも務める公共生命倫理学者が、「妊娠中絶」「生殖医療」「死の自己決定」という政治的論争の題材となっている3つの分野を通して、既存の生命倫理学がその前提としている表出的個人主義(cf. ロバート・ベラー)を批判し、それに替わる「身体性に基づいた」公共生命倫理を主張する本。著者はカトリック生命倫理界の大物で、批判対象としている「表出的個人主義」もカトリック哲学においてよく宗教的な価値観と対比されているものであり、当然のことながら人工的な妊娠中絶や安楽死などには反対の立場。
公共生命倫理とは、医療と倫理の関係における法のあり方を議論する分野。著者は法の目的は生本来の豊かさを守るためであるとして、独立した個人の利己的な自己実現欲求だけを追求する表出的個人主義に反対する。かれによれば、表出的個人主義は「完全に自立した個人による自己決定」を前提としており、生まれた瞬間から家族や周囲の庇護を必要とし、生涯をとおして病や障害や老いによりケアを必要とする人間の身体性を無視している。人は存在するだけで家族や周囲の人たちからとうてい返しきれないほどの助けを受け、また周囲の人たちに対して扶助やケアの責任を負う。これは独立した個人同士による自己決定をとおした合理的な取り引きではなく、人が生きることの本質的な状態なのだと著者は主張する。表出的個人主義を前提とした生命倫理は、そうした本質を無視して「完全に独立した個人」というフィクションに基づいた法を生み出しており、現実の生の豊かさを守れていない、と。
たとえば妊娠中絶について、フェミニスト哲学者のジュディス・ジャーヴィス・トムソンは1971年の有名な論文において、「ある日起きたら、あなたは寝ているあいだに音楽愛好家たちによって誘拐され、死にかけている有名なバイオリニストの体が自分の体に繋がれていた。バイオリニストには腎臓の病気があり、あなたの体に繋がれることによってあなたの腎臓を使って生き続けていた。あなたは唯一の適合者であり、あなたが管を外せばバイオリニストは死んでしまう」という思考実験を提唱した。この例において、バイオリニストが生きるためにはあなたの体が必要であり、管を外せばバイオリニストは死んでしまうが、バイオリニストを生かし続けるためにあなたが自分の体を提供する義務はなく、したがって管を外すことは許される、とトムソンは論じた。女性が胎児を体から除去するのもそれと同じであると。いっぽう同じころ、胎児の命が保護に値する可能性は認めた上で女性が自分の身体を提供する義務はないと論じたトムソンに対して、同じく哲学者のマイケル・トゥーリーやマリー・アン・ウォレンは、胎児はそもそも人格が認められるパーソンではなく、したがって胎児の命は保護に値しないと主張した。トゥーリーはある個体がパーソンと認められるためには自分を連続した個とする自己認識が必要だと論じたが、その基準を元にすると胎児だけでなく生まれたばかりの赤ちゃんや、重い知的障害のある人、病気や事故により認知能力を失った人などもパーソンから外れることになった。(これらの論文は、江口聡・訳編「妊娠中絶の生命倫理 哲学者たちは何を議論したか」にまとめられている。)
著者はこれらの主張について、既存の生命倫理学が「完全に自立した個人による自己決定」を前提としているために、妊娠中絶の問題が妊婦と胎児というそれぞれ独立した個人の権利の衝突か、もしくは胎児のパーソンフッドを否認することによってそうした衝突の存在を否定することになってしまっていることを指摘する。しかし胎児と妊婦の関係は、ある日突然バイオリニストとそのファンたちによって誘拐されて勝手に繋ぎ合わされた被害者でも、ただ権利が衝突してしまった赤の他人同士でもなく、親と子という関係にある。表出的個人主義はそうした親密な繋がりや、その関係性によって生じる庇護の責任を否定し、自分と繋がりのある胎児を、自分の自己決定を阻害する対立者にしてしまう、として著者は妊娠中絶擁護論を批判したうえで、妊婦にも、もちろん胎児の父親にも、そしてその家族や親族、コミュニティの人たちや、最終的には政府にも、最も弱い立場にある胎児や身体的負担を抱える妊婦を庇護し支える義務がある、と主張する。
表出的個人主義が生命倫理を考えるうえで不十分だ、というのはそのとおりだと思うし、ぶっちゃけGriswald v. Connecticut (1965)のプライバシー権を元に妊娠中絶の権利を認定したRoe v. Wade (1973)アメリカ最高裁判決の論理は弱いと(わたしだけでなく大抵のフェミニストが)思っているんだけど、妊娠中絶を禁止したところで「胎児を庇護する義務」から来る負担が妊娠した女性だけに押し付けられる状況がいまより悪化するだけとしか思えない。逆に、父親やコミュニティや政府が子どもや母親に対する支援を充実させたら、妊娠中絶の何割かは必要ではなくなるかもしれないので、そっちを先になんとかしてほしい。また、Gonzales v. Carhart (2007)でルース・ベイダー・ギンズバーグ判事は妊娠中絶の権利を「プライバシー権」からではなく女性が男性と対等に生きる権利の一部として主張したのだけれど、そうした意見について著者は「現在の妊娠中絶支持派の代表的な考え方」とコメントするだけで、一切論じていない。女性という集団の権利を主張するフェミニズムも著者が主張する宗教的コミュニタリアニズムと同じく「表出的個人主義に対する批判的立場」の1つなんだけど、扱いが軽すぎてなんなのって感じ。
生殖医療についての議論でも、たとえば代理母の問題について表出的個人主義を前提とした手放しの市場主義を著者は批判しているけど、フェミニズムにおける代理母やその他の生殖医療に関する議論は一切扱っていない。「死の自己決定」に関しては辛うじて自殺幇助に対する障害者運動からの反対論に言及しているけど、障害者運動が実際になにを求めているのかは取り上げない。わたしだって自分とは明らかに立場の違うカトリック生命倫理学者の本を読んでいるんだから、この著者にもフェミニズムや障害者運動の本を読んでそれらの議論にちゃんと向き合ってほしかった。とくにディスアビリティー・ジャスティスの枠組みでは、著者が語っているようなインターディペンデンシー(相互依存性)の問題について細かく論じられているわけだし。まあわたし個人にとっては、普段あんまり読まない主張を読めたので、十分興味深かったんだけど。