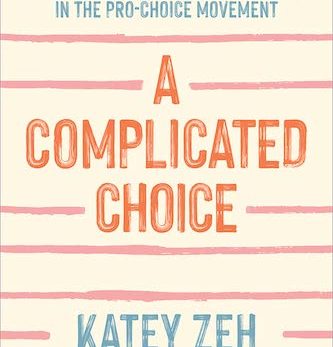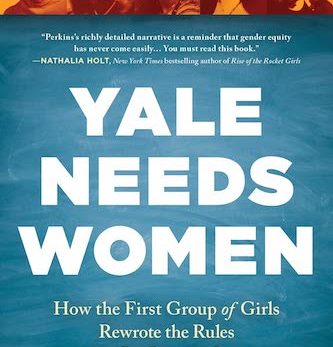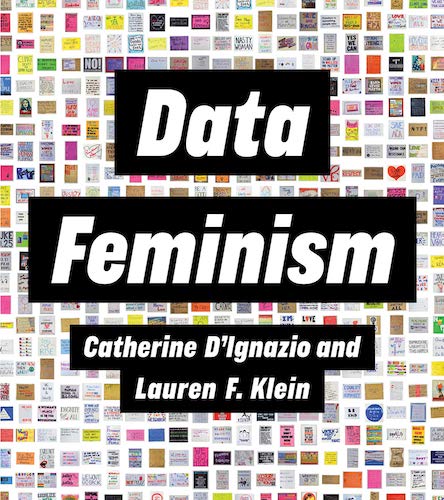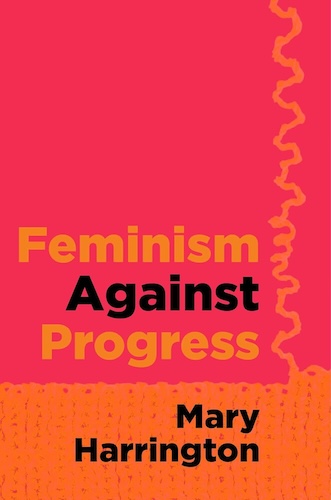
Mary Harrington著「Feminism Against Progress」
反動フェミニズムを掲げ「進歩的」なフェミニズムを批判する本。Louise Perry著「The Case Against the Sexual Revolution: A New Guide to Sex in the 21st Century」と並び、イギリスで単に反トランスジェンダー的なだけにとどまらない保守主義フェミニズムが浸透しつつあることを示している。
産業革命以降のフェミニズムは、男女の身体的な差異を口実とした女性差別に対抗する運動だった。かれらが批判したのは、たとえば母性の保護を口実とした性役割分担や、妊娠のリスクとコストを前提とした二重規範的な(男性と女性で異なる)性規範の強要であり、それらの多くは技術的な進歩によって正統性を失い、女性の機会や自由が拡大してきた。それはたとえば身体的な大きさや筋肉量に依存しない職や産業の創出であり、避妊薬や妊娠中絶の合法化による望まない妊娠・出産からの解放だった。その結果、結婚制度はPerry「The Case Against the Sexual Revolution」が主張しているような性の供給と需要のマッチングと社会的再生産のための安定的な手段という機能を失い、女性の性や再生産が女性本人から切り離されたパーツとして売買春や代理出産などの形で市場経済に乗せられてしまう。すなわち、技術的な手段によって性差を消し去る手法は、一部のエリート層の女性たちの社会的活躍を可能にした一方で、それ以外の大多数の女性たちの身体を男性や社会のための性や再生産の道具に貶めたと著者は訴える。
著者はトランスジェンダー女性を同じ女性として女子刑務所やその他の女性用の施設に受け入れろとするトランスジェンダーの運動を批判するが、人口比でいうとほんの僅かしかいないトランスジェンダーの人たちの運動がここまで社会的影響を得たことには理由があると指摘する。反トランス的なフェミニストの一部は「トランス女性は男性であり、男性権力が女性のスペースを破壊するためにトランス女性の権利拡張を行っているのだ」と言うが、著者の考えはそれとは異なる。さまざまな調査によるとトランスジェンダーの権利に肯定的なのは高い教育を受けた層が多く、また男性より女性の方が肯定的だということから、つまりトランスジェンダーの権利を擁護しているのは進歩的フェミニズムによって利益を得ているエリート層の女性たちだと指摘する。代理出産だけでなく介護など社会的再生産労働を移民女性や貧困女性に外注し、頭脳労働で男性と競争している彼女たちは、身体的な性差は存在しないか重要ではないと考えた方が都合が良い。すなわち、彼女たちはトランス女性のためではなく自分自身のために女性の身体性を否定しているというのだ。
著者はもともと進歩的なフェミニストであり、また自身も以前は自分の性自認で悩み、一時期はセバスチャンという男性名を使ったこともある。そうした彼女が考え方を大きく変えたきっかけは、若くして結婚・妊娠した際に周囲から「あなたのようなフェミニストがなんで」と見下された経験と、妊娠・出産を経て感じた自分の子どもに対する母性的・自己犠牲的な感情だった。エリート女性たちが自分のキャリアを追求するために生み出した理論によって女性が母親として子どもを育てるための安定した環境である結婚制度は壊され、一見男女平等に見えるが実際には男性の性的欲求を満たすための「性の解放」のために多くの女性たちが望まないセックスや生活のための売春に駆り出されることに対し、著者は反動フェミニズムを掲げるようになる。
保守派の多くは、著者と同じように「性の解放」や結婚制度の弱体化を批判し、「伝統的な家族」への回帰を訴えている。しかしかれらの考える「伝統的な家族」はせいぜい20世紀中盤に一般化した比較的新しいものであり、そもそも産業構造の変化によって夫の給料で一家の生活を賄えるような幸福な経済状況は存在しない。それに対して著者が回帰を訴えるのは、それより前の、産業革命以前の「本当の」伝統社会だ。その社会では家と職場は分離しておらず、女性は妊娠・出産など身体的な要因に配慮された労働を、男性とともに行っていた。もちろん当時は女性の自由や権利は認められておらず父や夫の所有物のように扱われていたなど、復活させるべきではない側面もあるが、自由恋愛によらない結婚、よほどのことではない限り離婚ができない決まり、避妊や妊娠中絶の段階的廃止などによって結婚やセックスの伝統的な価値を復活させることを著者は訴える。
Perry「The Case Against the Sexual Revolution」およびこの本について本書でも批判的に参照されている「Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation」著者のSophie LewisさんとSNSで話したのだけれど、わたしがこれらの本に対して思うのは、「ヘテロセクシュアリティとヘテロノーマティヴな社会的再生産を前提とする限り」一見暴論にしか見えない彼女たちの主張に一定の説得力があることは否定できない、という事実だ。Lewisさんも、彼女たちが家父長制的な社会的再生産に塗り込まれた暴力性をおおっぴらに認めつつ、それ以外の選択肢が存在しないという信念に貫かれていることを指摘している。だからやっぱり本書のような「反動フェミニズム」が生まれてくることも、やはりJane Ward著「The Tragedy of Heterosexuality」が論じる「ヘテロセクシュアリティの悲劇」に繋がる問題なのだと思う。ところでLewisさんがトランス女性のパートナー(本書では「女性を自認している異性」と描写)と結婚していることを「伝統的な結婚の根強さの証拠」と書いているのはさすがにいじわるだと思うよHarringtonさん…