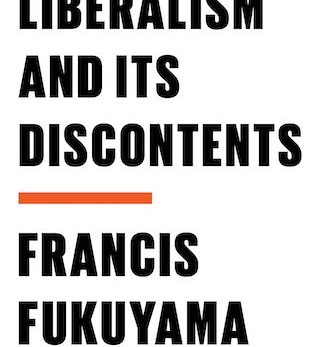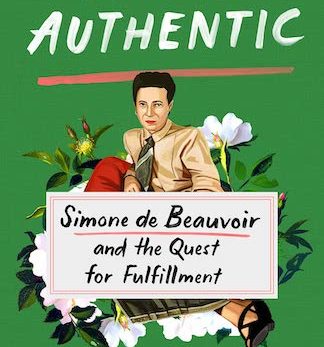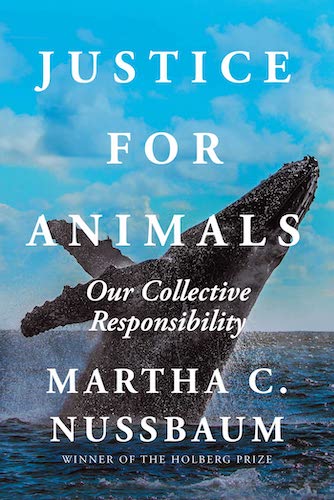
Martha C. Nussbaum著「Justice for Animals: Our Collective Responsibility」
動物倫理の議論にケイパビリティ論を拡張する哲学者マーサ・ヌスバウムせんせーの新著。クジラやシャチなどの海洋生物に魅了され野生生物保護の活動をしていた弁護士の娘が2019年に亡くなったことを受け、著者が彼女から教えられたことをもとに建設的な哀悼として書かれた本。
アマルティア・センにより提唱され著者もその発展に寄与したケイパビリティとは、概念的な権利や自由や経済的指標ではなく、実際に個人が生きるうえで価値を置くこと、能力を活かせることを実行する、実質的な自由を保証しようとする考え方。その対象をヒトに限る必然性はなく、感覚や意識を持ち自らの可能性を実現しようとすることができるあるあらゆる動物に対しても適用できる、と著者は主張する。
著者が持論と比較するのは、動物倫理の議論で訴えられてきた3つの主要な考え方だ。それはまず類人猿やその他の一部の生物の保護のために法律家などによって採用されてきた「ヒトに近い種はパーソンとしての法的権利が認められる」という考え方、次にピーター・シンガーが代表する功利主義的主張、そして最後にクリスティン・コースガードが主張するカント的な「目的の王国」の拡張。
パーソン論はおもに現実の法をもとに権利拡張を目指す法律家によって採用されているもので、哲学的な立場というよは現実的な戦略であり、それを哲学的な立場から否定するのはフェアではないと著者は認めつつ、それが結局ヒトを特権的な立場にあることを前提としてヒトに近い性質を持った一部の動物だけしか保護しないことを批判する。逆にシンガーら功利主義者は、すべての種に平等に適用できる基準を求めた結果、「苦楽」という単純な指標を生み出したが、それはさまざまな種がそれぞれ独自の可能性や価値を持つことを軽視している。種に関わらずすべての個を手段ではなく目的として扱うべきであるというコーストガードの主張について、著者は個々の動物の尊厳を尊重しているとして高く評価すると同時に、彼女の議論がヒトの倫理的な特異性というカント由来の不必要な要素を含んでいることを批判する。
ケイパビリティの立場からは、それぞれの種にはそれぞれ特有の能力や価値、可能性が存在し、それによって自らの可能性を実現するために必要な環境や境遇も違ってくる。牧場や動物園の檻への収容によってそうした環境を奪うことはもちろん、人類によって起こされる気候変動やマイクロプラスチックの拡散などによって環境を破壊することは動物たちのそうした権利を侵害することになる。しかし種によっては人類が生み出した環境に適応した(遠い昔に人類によって行われた非倫理的な行為によって適応させられた)ものもいるし(犬や猫などの伴侶動物)、自由に生きるために必要な環境の種類や広さによっては人為的に作られた自然保護区や動物園のような環境におかれても権利の侵害とならないものもある。そもそも環境破壊の影響を考えると人類の手の入らない環境などもはや存在せず、野生動物をただ放置していれば良いという段階ではない。動物たちのケイパビリティを尊重するために自然保護区の設置や気候変動による災害の対応などの介入が必要とされる場面も多い。
本書はさらに、倫理的に動物を殺すことは可能なのかどうか、養鶏や羊毛目的の羊の飼育など倫理的に動物を利用することは、肉食動物の捕食行動についてどう考えるか、犬や猫など伴侶動物を個としてケイパビリティを尊重するとはどういうことなのか、などさまざまな方向に議論を広げたうえで、最終章では動物の権利を守るための法の役割について論じる。伴侶動物の保護についてはヒトの子どもと同じように法的に規定された第三者による権利の擁護という形で国内法の整備で対処できるが、さまざまな動物保護法規から畜産業界が除外されていることから分かるようにそれ以外の動物の権利を守るためには世論の高まりとともに国際的な取り決めが必要。現状からはそうした取り組みが世間一般の支持を得ることは想像しにくいが、過去には個としての権利が否定されていた女性たちが権利を認められるようになった例などもあり、動物倫理の一般化に著者は期待を寄せる。