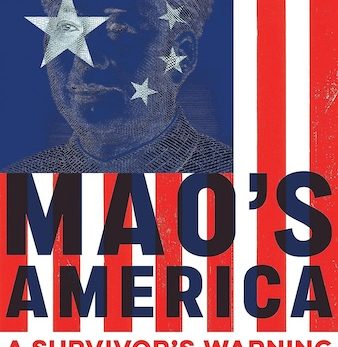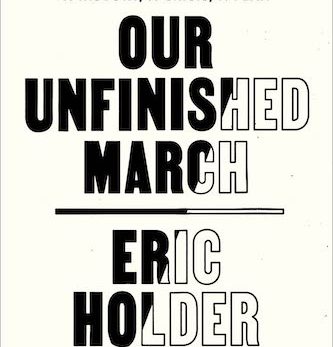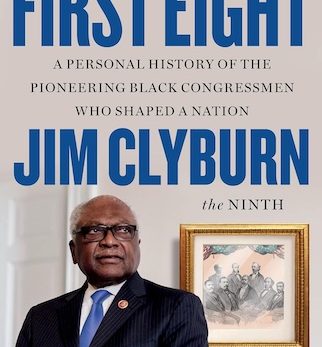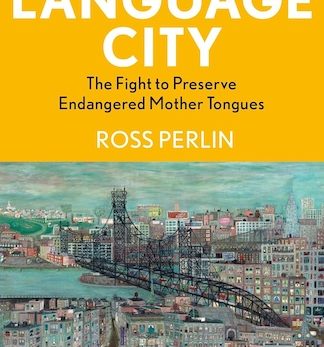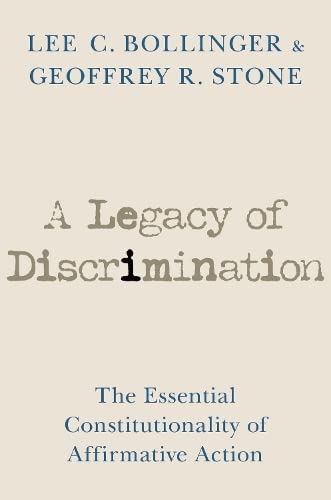
Lee C. Bollinger & Geoffrey R. Stone著「A Legacy of Discrimination: The Essential Constitutionality of Affirmative Action」
今年、大学入学におけるアファーマティヴ・アクションの合憲性をめぐるアメリカ連邦最高裁判所の判決が迫るなか、アファーマティヴ・アクションの倫理的な必要性とそれが合憲とされるべき法的根拠を主張する本。著者はどちらも著名な憲法学者で、なかでもBollingerは2003年に最高裁が判決を下したGrutter v. Bollinger裁判ではミシガン大学の学長として同大学のアファーマティヴ・アクションを守るための矢先に立った人。
アファーマティヴ・アクションがいまでも必要な理由は、多数の研究でも明らかになっているように奴隷制から解放されていらい黒人たちがその賠償を受け取っていないだけでなく、さまざまな形で階層上昇の機会を妨げられてきたこと。それは奴隷制を別のかたちで再現しようとした政府による不当な取り締まりや刑罰としての奴隷制時代と同じプランテーションでの強制労働、参政権の否定、住宅政策や金融政策を通した資産形成と中流階層の創設からの排除、人種隔離に基づいた教育機会の否定など。
1954年のBrown v. Board of Education判決で最高裁は教育における人種隔離を違憲と判断、南部の白人たちによる暴力的な抵抗を経て人種別の学校は廃止されていったけれども、白人たちは黒人と同じ学校に子どもを送ることを良しとせず、「隔離学校」を呼ばれた私立の学校に子どもを通わせたり、黒人が多く住む都市部から黒人の入居を拒む慣行が行き渡っていた郊外へと引っ越すことで対抗した。その結果、都市部は教育予算の原資となる税収を失い、公立学校だけでなく医療や社会サービス、道路や水道などのインフラに至るまで荒廃した。また警察や裁判は郊外に住む白人によって運用され、都市部に住む黒人への不当な取り締まりや暴力が横行するとともに、投票所を減らすなどの方法で都市部の有権者が選挙に参加する機会を奪われた。
そういうなかにおいて、有力な大学への進学はいまでも黒人が階層上昇し、次の世代により多くの機会を与えるための最高の手段であることを、著者らはデータを使って示す。本書はこれらの前提から、アファーマティヴ・アクションが数百年続いた差別的な制度の産物である人種間の不均衡を是正するために有効な手段であるとして、その倫理的な必要性を説く。
法律論としては、アファーマティヴ・アクションが違憲であるという主張は憲法修正14条を根拠としている。これは南北戦争のあと、連邦政府が解放された元奴隷たちを対等な市民として扱うために成立させたリコンストラクション条項の一つで、修正13条が奴隷制の禁止、修正14条が法の下の平等、修正15条が市民権の保障を規定している。Kermit Roosevelt III著「The Nation That Never Was: Reconstructing America’s Story」ではこれらの憲法修正条項を建国以来の法思想とは異なる画期的なものだとして、現代のアメリカに繋がる本当の建国は1776年の独立宣言ではなくこれらの修正条項が成立した1870年だと主張している。
アファーマティヴ・アクションに反対する人たちは、人種によって扱いをかえるアファーマティヴ・アクションは憲法修正14条に違反していると主張するが、主流の憲法学ではそのように考えない。なぜならリコンストラクション条項を成立させた議会は同時期に奴隷制から解放された黒人たちを支援するために教育や住居などに関連した多数の法律を成立させており、かれらが人種によって差別を受けていた人たちを支援するためのあらゆる取り組みを禁止しようとしていたとは考えられないからだ。保守派はふだん、妊娠中絶の権利や同性愛者の権利、環境保護、インターネットプライバシーなどは憲法制定時点では起草者により想定されていなかったのだから憲法によって保護するべきではない、というオリジナリズムという理論を主張するが、Erwin Chemerinsky著「Worse Than Nothing: The Dangerous Fallacy of Originalism」にも書かれているように「起草者の意図」が自分たちに都合が悪くなると異なる基準を持ち出してくる。
少なくとも新たな判決が出るまではアファーマティヴ・アクションは合憲とされているが、実のところアメリカでは「過去の差別や現在の機会不平等を理由として不利とされた人たちを優遇する」タイプのアファーマティヴ・アクションはかなり以前から否定されている。その判例はカリフォルニア大学において人種を考慮に入れた入学審査の合憲性が問われた1978年のRegents of the University of California v. Bakkeで、結果はアファーマティヴ・アクションは合憲とされたものの、判事たちの意見は割れに割れ、合憲・違憲それぞれの立場から判事たちによる合計六つの異なる意見書が書かれた。その結果多数意見となったのは、学内のダイバーシティを拡充することは全ての学生にとって利益になるから志願者の人種を考慮に含めることは認められるが、過去の差別や現在の機会不平等を理由として異なる扱いをするのは認められない、というもの。この判決がBollingerを含め以降のアファーマティヴ・アクションをめぐる法的議論のベースとなる
このようにしてアファーマティヴ・アクションは辛うじて存続できたが、差別によって不利な立場に置かれた黒人たちのためではなく、多数を占める白人の学生たちの利益のために黒人学生を増やすべきだ、という捻れた論理となっており、差別の根絶と真の平等を目指していたアファーマティヴ・アクションの本来の性質は歪められた。現在大学や職場などで反差別や機会均等ではなく「ダイバーシティ」自体を奨励するキャンペーンが行われがちなのも、この判決に原因がある。保守派が支配している現在の最高裁は今年、こうした抜け道すら防ぎアファーマティヴ・アクションを全面的に禁止する新たな判決を下すと予想されているけれど、著者らは今こそアファーマティヴ・アクションを支持する側は「ダイバーシティの効用」ではなく本来目指していたはずの人種平等を正面から訴えるべきだ、と主張する。
これはリプロダクティヴ・ジャスティスの運動が「プライバシー権」の一部として妊娠中絶の権利を保護してきたRoe判決の破棄を契機として、プライバシーではなく本来の「女性の平等権」を根拠とした運動をすすめるべきだ、と訴えていることと通ずる。女性の権利としてではなくプライバシー権の一部として妊娠中絶の権利を認めたRoeや差別への是正措置ではなくダイバーシティの価値のためにアファーマティヴ・アクションを認めたBakkeのような判決は、最高裁のリベラルな判事と保守的な判事がそれぞれの思想をすり合わせた結果として生まれた妥協だけれど、そうした妥協すら破棄されるのあれば、妊娠中絶の権利やアファーマティヴ・アクションが必要とされている本来の理由を声高に主張するしかない。
なお、クレランス・トマス判事ら一部の保守派は、アファーマティヴ・アクションが支援するはずのマイノリティを傷つけているという主張もしている。それはたとえば、本来なら入れないはずのエリート大学にアファーマティヴ・アクションの結果入学しても授業についていけなくてドロップアウトするだけだし、実力で入学しても黒人であるからというだけで「あいつはどうせアファーマティヴ・アクションで入ったんだろ」という偏見で見られて自尊心を傷つけられる、など。最近ではArline T. Geronimus著「Weathering: The Extraordinary Stress of Ordinary Life in an Unjust Society」でも中途半端なアファーマティヴ・アクションにより入学した黒人たちが成功を手にする一方白人たちのなかで孤立して心身を傷つけられているという指摘もある。
著者はこれらの主張に対して、アファーマティヴ・アクションによって入学した学生たちが授業についていけなくてドロップアウトするという事実は存在しないこと、黒人学生が経験する偏見や孤立はアファーマティヴ・アクションが原因ではなくむしろ十分なアファーマティヴ・アクションが行われておらず学内における黒人学生や教員の人数がかれらが自尊心を保護できるだけの臨界値に足りていないことなどを、データによって次々示していく。まあもともと「アファーマティヴ・アクションは逆にマイノリティを傷つけている」と主張する人たちは実際にはマイノリティの地位向上なんて興味ないわけだけど、かれらの言い分が社会科学的な研究に基づかない点はもっと周知されるべき。
また、人種ではなく親の収入を基準としたアファーマティヴ・アクションを行うべきだという主張や、Kenny Xu著「An Inconvenient Minority: The Harvard Admissions Case and the Attack on Asian American Excellence」にも書かれているような黒人を対象としたアファーマティヴ・アクションはアジア系アメリカ人から機会を奪っているという主張に対しても、それぞれ丁寧に反論。著者らが擁護するアファーマティヴ・アクションは、奴隷制から人種隔離、参政権や階層上昇機会の剥奪といったアメリカの黒人に特有な状況への解決策であり、もちろん他のマイノリティに対してもかれら特有の経験を元としてアファーマティヴ・アクションの必要性を別に議論することはできるけれども、歴史的な特有性を無視してマイノリティの権利をめぐる一般論としての処理はできないことが説得的に示されている。