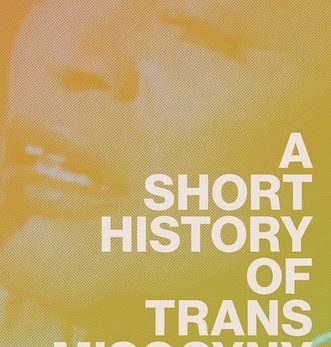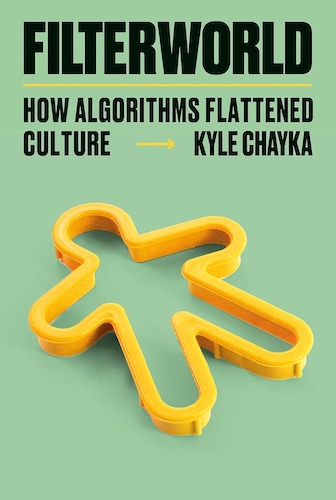
Kyle Chayka著「Filterworld: How Algorithms Flattened Culture」
アルゴリズムによって消費者に提示されるコンテンツがフィルターされる仕組みによって起きる文化のフラット化を指摘する本。
メディア消費のフィルタリングについての議論では、イーライ・パリサー著『閉じこもるインターネット――グーグル・パーソナライズ・民主主義』やキャス・サンスティーン著「Republic.com」シリーズ(最新作は『#リパブリック: インターネットは民主主義になにをもたらすのか』など、アルゴリズムによって個々のユーザに提示されるコンテンツがそれぞれの嗜好によってフィルタされてしまう結果世間の共通認識が消滅して会話が成り立たなくなる、という政治面での分極化を訴えるものがベストセラーになってきた。いっぽう同じくベストセラーとなったクリス・アンダーソン著『ロングテール‐「売れない商品」を宝の山に変える新戦略』は経済や文化の面に目を向け、特定のニッチな層にしか需要されないためこれまで日の目をみなかったさまざまなコンテンツが技術の進歩により商売として成り立つようになり、多種多様な嗜好に応じた商品やコンテンツが提供されるようになると主張した。
これらの議論は、個々の消費者や市民がフィルタを通して自分の趣味嗜好に沿ったメディアやコンテンツに接することで起きる、価値観の多様化と分極化がもたらす危険と可能性を考察するという共通点がある。しかし現実のインターネットにおいては、必ずしも個人の趣味嗜好を満たすためではなくソーシャルメディアなどを運営する企業の利益を最大化するためにアルゴリズムが設計され、さらにそうしたアルゴリズムの上で活動するクリエイターやインフルエンサーと呼ばれる人たちもそれに順応することで、ストリーミングサービスの仕組みによってイントロが短く30秒間だけテンションを維持するが展開に乏しい音楽が大量に生み出されるなど、むしろ文化のフラット化が進んでいると本書は指摘する。ネットフリックスがユーザの過去の視聴歴を分析して次に観る映画を推薦してくるのはよく知られているけれど、それだけではなく好きな映画のジャンルや俳優の傾向をもとに同じ映画をユーザごとに異なるサムネイルを選んで表示しているという事実は、リコメンデーションアルゴリズムが単に個人の嗜好に合ったコンテンツを紹介しているのではなく、嗜好に便乗して消費者を特定の方向に誘導していることを意味する。
著者がノスタルジーを感じる1990年代から2000年代はじめ頃までのインターネットはこうではなかった。拙いHTMLで多くの人が思い思いのサイトを自作し、またそうしたサイトを通してニッチな趣味を持つ人たちがお互いを発見して好きなコンテンツを紹介しあった。そこでは、アルゴリズムではなく生身の人間がそれぞれの趣味や価値観でキュレーションしたメディアが共有され、それに触れ、自ら開拓していくなかで、自分の趣味や嗜好を認識していった。たとえば著者はケーブルテレビで放映されていたドラゴンボールZから日本のアニメにハマり、違法ダウンロードサイトを漁りファンが製作した英訳字幕を利用し、一時はハーレム系アニメに迷走するも、『灰羽連盟』など安倍吉俊作品に傾倒していく。違法ダウンロードをしていたことは反省していると言いつつも、このようにして手探りで自分が好むコンテンツを探していく醍醐味は、ソーシャルメディアやコンテンツ配信業者がアルゴリズムを使ってコンテンツを押し付けてくる現代では失われてしまったと著者は言う。
著者自身、実験的にアルゴリズムに影響されない生活をしようとソーシャルメディアやストリーミングサービスを削除するも、いまやニューヨーク・タイムズなど大手ニュースサイトですらアルゴリズムによりリコメンデーションを採用しているし、世界中を旅する著者が仕事するために使うカフェなど現実までもがインスタグラムなどソーシャルメディアに適応してフラット化してしまっている。まあ最後のはグーグルマップで「hipster cafe」を検索してカフェを見つけている著者が悪いので、本当にその気なら道をぶらぶら探索してカフェを見つけろよとは思うけど。てゆーかカフェでラップトップ広げて仕事をする著者みたいな人がたくさんいるから、それにカフェが適応して似通ったようになってるわけでもあるし。とはいえ、自分の生活からアルゴリズムを排除するのは現代では難しいけれど、少しでもアルゴリズムのフィルタを通さずに世界を観て経験することを著者は提唱している。