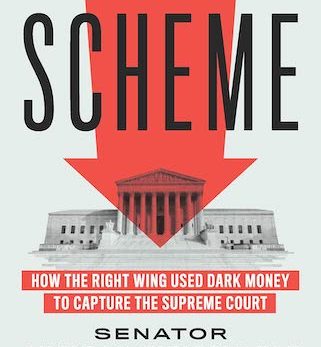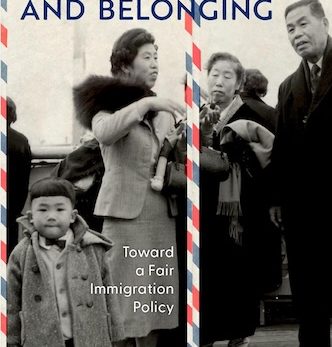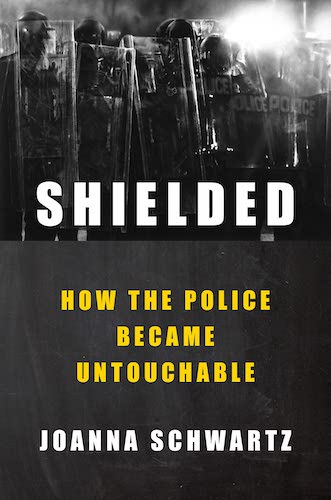
Joanna Schwartz著「Shielded: How the Police Became Untouchable」
米国において警察による一般市民への暴力や人権侵害の責任を追求することがどうしてできないのか説明し、必要な改革を訴える本。
2020年の5月にジョージ・フロイド氏を殺害したミネアポリスの警察官デレク・ショーヴィンは殺人罪に問われ20年以上の刑期を課され、またミネアポリス市は遺族に対する賠償金の支払いに応じたが、市民を殺害した警察官やかれらを雇っている自治体がその責任を問われるのは例外中の例外。本書は責任追及を妨げるさまざまな取り決めがどのように作られてきたのか歴史的経緯を追いつつ、その多大な弊害を明らかにする。
警察官による人権侵害の責任を追求する根拠とされる連邦法は、南北戦争後に制定された1871年公民権法(通称KKK法)によって生まれた1983条だ。当時南部ではKKKなど白人至上主義団体による黒人への私刑が横行したが、地元の警察や検察・裁判官はそれを取り締まるどころか積極的に参加することが多かった。1983条は黒人市民の人権侵害に加担した州政府・自治体やその職員を連邦裁判所に訴えて賠償責任を負わせることでそうした行為を止めようとした。
この法律はリコンストラクションの終了とともに使われなくなったけれども、20世紀中盤の公民権運動の時代になって再び注目され、人種差別をめぐる裁判で援用されるようになる。しかしその後起きた最高裁の保守化に伴い、さまざまな判例を通して1983条の認定を受けるのが困難になっていった。
警察による人権侵害を裁判に訴えようとするとき、まず第一の問題は公民権をめぐる裁判について十分な知識や経験を持つ弁護士は非常に少なく、都市部に集中していることだ。警察による人権侵害の被害を受けるのは黒人やラティーノ、貧困層、移民、ホームレスの人たち、障害者、クィアやトランスジェンダーの人たちが多く、長期に及ぶ裁判の費用を負担できる人はごく少ない。弁護士は無償で請け負って勝訴したときの賠償金で費用を回収しようとするので、よほど証拠がはっきりしていて確実に勝てそうなケースしか引き受けようとはしないけれども、そもそも警察が暴力をふるう対象となる人たちは世間一般からも差別や偏見の対象となっている人たちであることが多く、どれだけ証拠があっても勝てるとは限らないし、多額の費用をかけて警察の違法行為を立証して勝訴したのに「このような人物(薬物常用者であったり犯罪歴のある人だったり)に大金を与えるべきではない」と賠償額がゼロだったり1ドルだったりすることも。
そのハードルを超えて裁判を起こしても、警察による人権侵害の証拠を被害者の側が揃えて提出しなければ、すぐに却下されることも。通常の民事裁判では、原告の言い分が法律的に筋が通っていればとりあえず受理され、原告被告双方がお互いが持っている証拠を開示するよう請求することができるのだけれど、警察に対するものにおいてはその前の段階で原告側が証拠を手にしている必要がある。たとえば暴力をふるった警察官の名前やその警察官が身につけていたボディカメラの映像など、そこに確実に証拠があるのに「犯罪捜査に関係するので開示できない」と警察側が言い張れば原告側はどの警察官が具体的にどういう行為を行ったのか指摘するのも困難。
そうしたさまざまな困難を乗り越えたところで最後にそびえ立つ壁が、クオリファイド・イミュニティと呼ばれる取り決め。これによると、警察官が行った行為に責任が認められるためには、それが違法だったり違憲な人権侵害行為だったりするだけでは不十分で、それが人権侵害であることが過去の判例によってはっきり確定していなければいけない、とされており、その過去の判例はまったく同じ状況でまったく同じ行為が行われ、それが和解ではなく判決として人権侵害であるとして確定しており、判例集に掲載されている必要がある。要するに、はっきりその行為が人権侵害であると確定していないのであれば、現場の警察官にその場で法的判断を下すよう要求することになり不当だ、という話なんだけれど、実際のところ警察官は判例集なんて読まないし、著者が調査した多数の警察署の訓練プログラムのなかでも判例について教えてはいない。この制限により、過去の判例とほんの少しでも違いがあれば「判例がないので責任を問えない」とされる。
もともとクオリファイド・イミュニティは「緊急時に瞬時に判断を下さなければいけない警察官が、専門の法律家でもないのにある行為が人権侵害になるかどうか正しく判断することは難しく、仕事上の些細なミスをおかしただけで賠償責任を負わされるべきではない」というまっとうな理由で導入されたもの。しかし「緊急時」「誠実に」などの要件が保守化した最高裁によって次々取り払われ、誰がどう見ても明らかに何の正当性もない明らかな人権侵害ですら「過去にまったく同じケースに基づいた判例がない」というだけで警察官の行為に対して責任を問うことは不可能になった。ジョージ・フロイド氏殺害の件では世間からの批判を気にしたミネアポリス市がフロイド氏の遺族と和解したが、もしメディアの注目を集めておらず市が裁判を続けていれば、遺族の訴えは却下されていた可能性が高かった。
これらの取り決めは、警察官が仕事上のミスで賠償責任を負わされるようでは警察官のなり手がなくなる、あるいは人権派弁護士たちはお金目当てで1983条を悪用して些細なケースで警察や自治体を提訴している、といった保守派の言い分に基づいて作られたが、どちらも現実に即していない。ほとんどの自治体では警察官個人が訴えられた場合でも自治体が弁護費用や賠償金を負担する仕組みになっており、著者が何百もの大小の自治体の記録を調査したところ警察官個人が賠償責任を負わされたケースは全体の1%もない。また「お金目当て」だというが実際にはさまざまな仕組みによって1983条訴訟によって弁護士が裁判費用を回収する手段が制限されていてフロイド氏のような例外的なケースを除いては儲からないようにされているし、そもそも遺族の多くが本当に求めている「警察の改革、再発防止」は1983条訴訟を通して実現することができないので賠償金を求めるしかないのが事実。
1983条は人権侵害行為を行った警察官やかれらを雇用している自治体に賠償責任を負わせることで被害者の救済とともに再発防止を狙ったものだが、裁判も賠償金もすべて自治体が負担するので実際のところ人権侵害を指摘された警察官の多くは自分が訴えられたこともどれだけ賠償責任を負わされたかも知らないことが多い。それによって支払われる賠償金は、警察予算ではなく一般予算から支出され、そのために警察の暴力に晒されている貧困層のための住居や教育、福祉予算が圧迫されているが警察予算はなんの影響も受けない。さらにどの警察官がどれだけ人権侵害行為を裁判に訴えられているか、あるいはその警察署においてどういう行為が人権侵害だとして訴えられているかというデータも蓄積されず、再発予防に一切つながらない。
本書に書かれた事実はあまりに酷すぎてここで書ききれないけど、これでは警察による黒人を中心とした一般市民に対する暴力が減らないのは当たり前だとしか。クオリファイド・イミュニティはフロイド氏の事件のあと注目を集め、多数の州で廃止や改革への取り組みがはじまったが、それらが実際に実現したのはコロラド州一つだけ。コロラドではフロイド氏の事件の少し前に州議員がクオリファイド・イミュニティ改革法を提案していて、そのときは廃案になったけれども、すでに準備ができていたおかげでフロイド氏殺害の直後に再提出され当時の空気のなか一気に成立した。実はわたしの住むワシントン州でも今年クオリファイド・イミュニティ廃止法案が提出されていて、成立は難しいと言われているのだけれど注目しているところ。とはいえ警察による人権侵害を不問にしている仕組みはクオリファイド・イミュニティだけではない。本書で提案されている全ての提案がきちんと議論されてほしい。