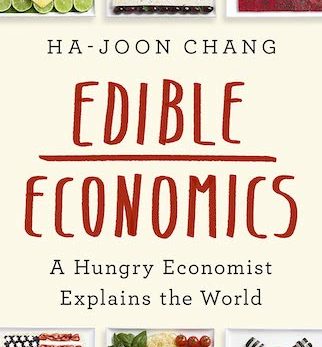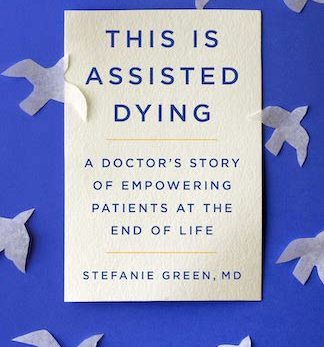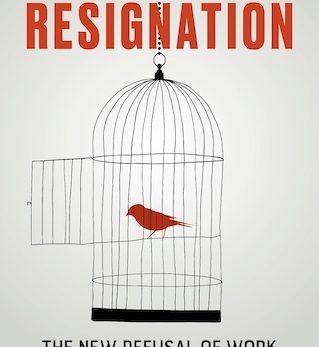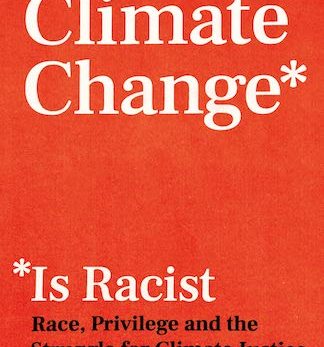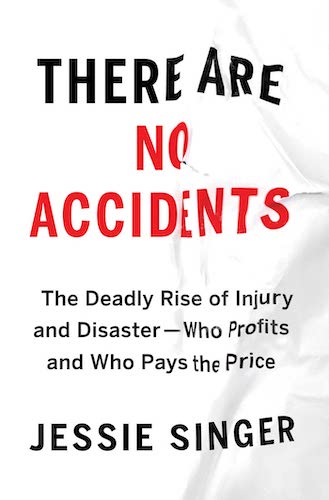
Jessie Singer著「There Are No Accidents: The Deadly Rise of Injury and Disaster―Who Profits and Who Pays the Price」
「アクシデント(事故)なんて存在しない」という刺激的なタイトルのとおり、世の中で起きるさまざまな事象が「事故」と処理されることによって何が覆い隠され、結果として危険が放置されるのかを指摘する本。想像を超えて良い本だった。家庭・職場・路上などさまざまな場所で発生する「事故」は、偶発的に起きるのでもなければ、なんらかのミスや不注意のせいで起きるのでもなく、わたしたちの法や市場が作り上げた環境によって起きている。人はミスをおかすものだし、不注意になることも――とくに生活のために必要な長時間労働に追われるなどしたとき――あるのが当たり前。それをふまえたうえで、労働者や消費者を保護する法律や、車の安全性能や交通網の設計を向上させたりる取り組みなどによって危険を取り除くことが「事故」を減らし、また「事故」が起きたときの被害を抑えることに繋がる。
ところが労働者や消費者に危険を強いている企業は、より安全な労働環境やより安全な製品を提供するよりも、従業員はより安全ルールを遵守すべきだ、消費者はより賢くなるべきだ、とその責任を押し付ける。たとえば古くは炭鉱労働者から最近のアマゾン倉庫員やウーバーイーツ配達員まで、労働者は危険な環境で働かされ、「事故」が起きたとき個人のミスや不注意を責められる。さらに人種・民族差別を受けていたり貧しかったりで選択肢の少ない人ほど、ありとあらゆる「事故」の被害にあう確率が高く、その責任を押し付けられやすい。差別を受けていたり貧しい人はより危険な仕事につかざるを得なかったり、安全性の低い車や家にしか手を出せなかったり、生活空間にある道路や街頭や信号機や公園などがきちんとメンテナンスされてなかったりする。そのような人工的に作られた環境を原因とする危険に対して「火の元に気をつけよう」「道路を渡るまえに左右を確認しよう」のように個人の選択によって対処させようとする呼びかけは、被害にあった人たちに責任を押し付け、根本的な原因から目を逸らさせることになる。必要なのは(特に危険にさらされている)人々が日頃から完璧にその危険を制御することではなく、多少コンロの扱いを間違えても簡単に燃え移らない家や、多少不注意な人でも安全に渡れるような道路だ。
さまざまな危険を減らすための方法は、実のところかなり解明されている。だからこそ社会的地位やお金のある人たちが運転する車は搭乗者を守るための安全性能が満載だし、かれらが住む地域の道路には歩道や街頭や信号が設置されていて、公園の遊具もきちんとメンテナンスされている。人種や収入によってあらゆる種類の「事故」にあう確率に大きな差があるのはそのせいだ。社会的・経済的地位に関わらず市民の安全を守るためには政府による規制が有効なのだけれど、ここ数十年にわたってアメリカでは規制緩和や産業界による規制当局の乗っ取りが進み、さらに安全格差が拡大している。さらに「訴訟社会」を是正するためとして安全性の欠けた商品によって被害を受けた消費者が製造者を訴える権利が著しく後退しているせいで、企業は賠償責任をただの「計算可能な潜在的コスト」として計上することができるようになり、お金をかけて安全性を向上させるインセンティヴを失っている。
このような状況を変えるためには、まずわたしたちが「事故」という言葉に対してもっと懐疑的になり、「事故」について聞くたびにその直接的な原因(=ある人のミスや不注意)ではなく、より根本的な原因(=人間である限り無くせないそのようなミスや不注意を許容しない非人間的な人口的環境と、そうした環境をもたらした経済的・政治的な仕組み)に考えを至らせるべきだ、というのが著者の主張。「事故なんて存在しない」というのはそのための呼びかけだ。
薬物のオーバードーズについての章では、「事故」という言葉が家族をオーバードーズで失った人にとって「自分たち家族や本人が悪かったのではない、あれは事故だったんだ」という救いをもたらすことを認めつつ、オーバードーズは本来予防できるものであり、多くの場合それが予防できないのは、薬物使用に対するスティグマや法的制裁や社会的孤立、オピオイド拮抗薬が入手困難であることなど、ハームリダクションの視点から的確な指摘を行っている。わたしはもともとこの本でハームリダクションの話が出てくるとは思っていなかったので良い驚き。