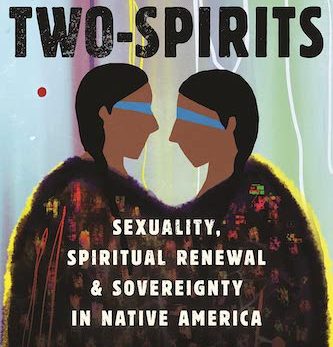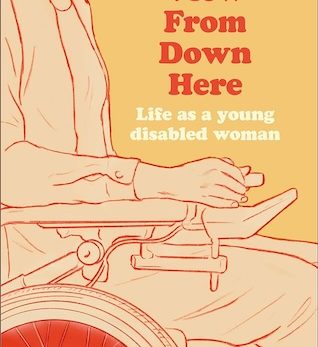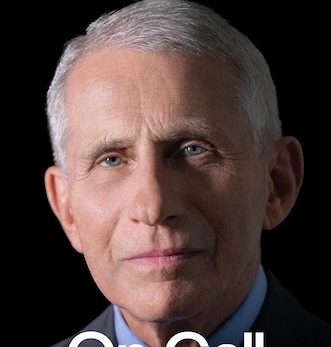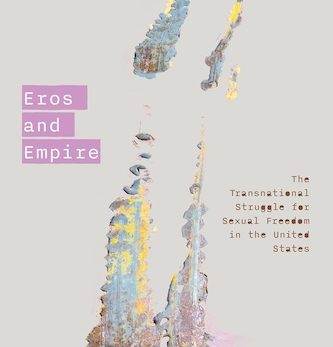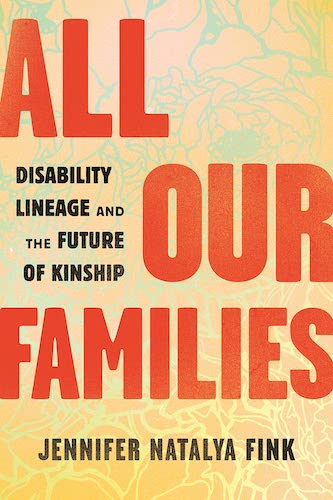
Jennifer Natalya Fink著「All Our Families: Disability Lineage and the Future of Kinship」
障害者がいまも残る優生主義の作用によって世間からだけでなく家族史からも抹消される事実を指摘し、障害を例外的な悲劇ではなく誰もが身近に経験するごくありふれた事実として取り戻し、失われた家族の繋がりを復活させようとする本。
著者はユダヤ系アメリカ人でクィア女性の文学者・文学研究者で、音声会話をしない自閉症の娘を持ったことから娘の存在を抹消しようとする社会のあり方やそれに自分も加担していたことに気づく。障害のある子どもを産んだあと彼女は、家族からこれまで聞かされていなかったダウン症などの障害のある近い親戚が何人かいたことを聞き、名前すら失われたかれらについて調査をはじめる。親族の多くをホロコーストで失ったユダヤ人の家系が、ユダヤ人より早い段階でナチスによる殺戮処分の対象となった障害者たちの社会的抹消を自ら行ってしまったのはどうしてか?そこには、ナチスの敗北によって否定されたはずの優生主義が「専門機関への隔離」や「親権放棄により国に預ける」といった形で続いていることを示している。
障害理論家のマイケル・オリヴァーは障害学の古典的名著『障害の政治』(原著初版は1990年、2012年に英語ではアップデート版が「The New Politics of Disablement」(障害の新しい政治)として出版されている)などで障害が「個人的な悲劇」として扱われていることを批判したが、いまでも障害を例外的な悲劇として扱う風潮は続いており、それによって障害者は家族や社会の一員として扱われない。著者は妊娠中、何度も周囲から「男の子がいい?女の子がいい?」と聞かれたが、それに対するフェミニストとして政治的に正しい回答は「どちらでもいい、その子が健康ならば」だと思っていた。「健康ならば」?ダウン症や自閉症などの障害のある子どもを隠避し、その出産をごくありふれた人生経験の一つではなく、本来あってはならない個人的な悲劇として扱う姿勢がここにも現れている。
障害に関わる議論の歴史において、著者のような「障害児を持つ白人の母親」は特権的な発言力を持ってきた。国家が十分な児童福祉を提供せず、障害児の父親が自らの責任を放棄することが多いなか、障害のある子どものケアを全面的に負担させられるのはその母親か、親に金銭的な余裕があった場合は安い給料で搾取的なケア労働に従事する移民女性や貧しい白人や非白人の女性であることがほとんど。その中で唯一発言力を持つのが白人の母親たちだけれど、ケア負担の軽減や医学の進歩による障害の「治療」を求める彼女たちの運動に対して、障害者自身による当事者運動は障害者としてのアイデンティティとプライドを主張し、治療ではなく社会の側が障害者の存在を前提とするように変わるべきだと訴える。
著者はこうした対立の存在に意識的で、だから「白人の母親」として発言することが障害者を沈黙させることに繋がりかねない危険を念頭に、障害者当事者たち、なかでもディスアビリティ・ジャスティスの担い手であるたくさんのクィアや非白人の障害活動化たちを頻繁に引用し、かれらの主張を織り込んでいく。基本その姿勢には信頼が置けるのだけれど、2020年に亡くなったステイシー・ミルバーンさんに関する部分は、Leah Laksmi Piepzna-Samarasinha著「The Future Is Disabled: Prophecies, Love Notes and Mourning Songs」からも分かると思うけど、最近のことだしちょっとセンシティヴな部分なんで、「待って待って、彼女はわたしたちのアンセスターだよ、取らないで!」と思ってしまった。もちろん「わたしたち」に彼女のレガシーを独占する権利なんて一切ないんだけど。
著者はディスアビリティ・ジャスティスを好意的に紹介しつつ、ディスアビリティ・ジャスティスについて積極的に発言している人たちに比較的若いクィアが多く、育てられた家族との関係が薄く、また子どもを育てている人も少ないことから、横の軸の繋がりは強いけれども縦の軸の繋がりが欠けていることを指摘していて、おもしろいと思った。作家のアンドリュー・ソロモンは人々が持つアイデンティティを民族や宗教のように家族の繋がりを通して伝えられることが多い「垂直方向のアイデンティティ」と性的指向や趣味などに基づいて共通項のある人と出会う「水平方向のアイデンティティ」に分類したけれども、障害はどの家族にも普遍的に起こることでありながら、世間から隠され家族史から抹消されるため垂直方向の繋がりが蓄積されない。ディスアビリティ・ジャスティスの界隈でも縦軸の繋がりが少ないため、子どもや高齢者のケアを行うインフラストラクチャーが存在せず、世代間の支え合いを通り越してミルバーンさんら既になくなったアンセスターや想像される「将来の世代」との概念的な繋がりが優先されがち。あんたに言われたくないなあとは思うんだけど、考えさせられたのは事実。
上にも書いたとおり著者は、わたしが知るディスアビリティ・ジャスティス界隈の人たちを多数引用していて、個人的には同窓会的な楽しさもあったのだけれど、ミルバーンさんの部分をはじめやっぱりこの人はコミュニティの中ではなくその外側からコミュニティが作り上げているアートや議論を見ているなあ、と感じた。これはほとんど感覚的なことでうまく言えないんだけど、「わたしたち」の意見が伝わっているのはうれしいと思うのと同時に、なんだか怖いな、という気持ちもある。