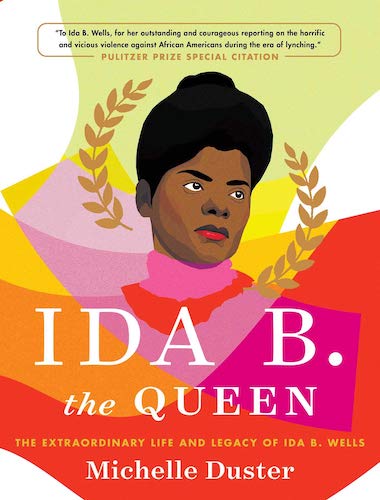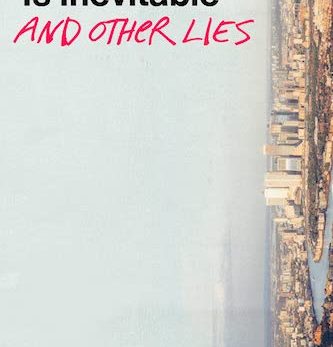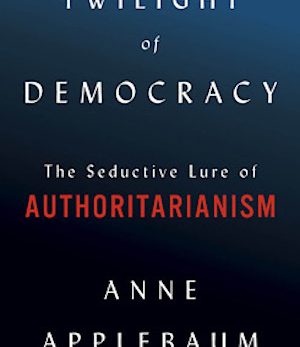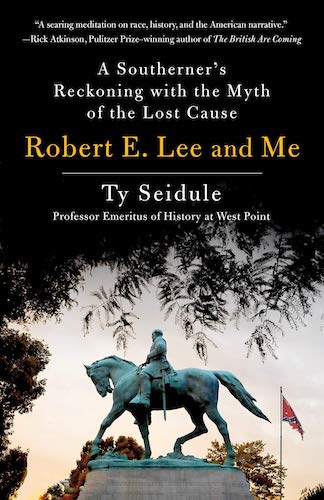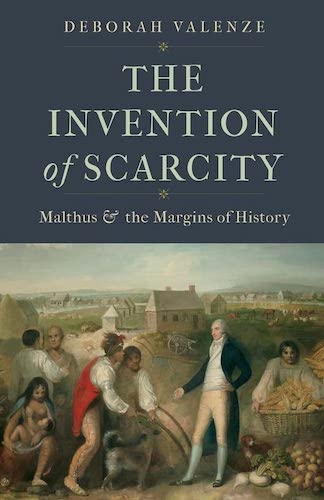
Deborah Valenze著「The Invention of Scarcity: Malthus and the Margins of History」
伝統的な保守派による反福祉論の根拠となったマルサスの「人口論」を読み解き、それを論理や実証によって反証するのではなく、マルサスが考察に含めなかった市場外の食糧生産や共同体的な経済体制、米やジャガイモなどマルサスが文化的な程度が低いとみなした食糧生産の仕組みなどから、マルサスが無視した部分にマルサスの論理への抵抗の可能性を見出す本。
マルサスの人口論といえば、「経済的その他の制約がなければ人口は等比級数に増加するが、食糧生産の増加はそれに追いつかないので、食糧の不足が起きる」という論理で有名。かれは貧民救済が議会で議論されていた時代にこの論文を発表し、貧しい人に経済的な支援を与えてもそれはかれらの人口増加を抑えていた自然な制約を取り除くことになり、結果的にかれらはより多くの子どもを生むので、結果的に貧困は解決されないことを主張、古典派経済学の発展に影響を与えた。
しかしマルサスが食糧生産について書いていたものを詳しく読むと、小麦の生産と市場による流通が最も文化的に進んだ正しいあり方だという前提が置かれていて、それ以外の穀物や市場を通さずに消費される食糧、狩猟が食糧生産の大きな部分を占める文化などについては一方的に軽視していた。それらはマルサスにとって話にすらならないもので、それらの伝統文化がどのような複雑な相互扶助やフリーライダー防止の仕組みを持っているのか考察しようともせず、貧困した社会だと一方的に決めつけた。
イギリス文化の至上を疑わないマルサスや同時代の古典派経済学者たちは、そうした認識に基づき、「遅れた」「貧しい」社会を文明化しようと、市場向け作物の単一生産などを通してそれらの社会を市場に組み込もうとした。その結果、伝統的な食糧生産体制やそれを前提としていた社会的な仕組みは崩壊し、単一作物の不作や市場の暴落などをきっかけに飢饉が起きた。食糧不足の原因を説明するはずのマルサスの議論が、その食糧不足の原因そのものになってしまったのだ。
マルサスの「人口論」なんて、ある程度内容については知っているつもりになっている人が多いけど、確かに研究者でもなければ実際には読まないし、その周辺のマルサスの他の著作なんてさらに読む人は限られている。しかしこれだけ世界に影響を与えた論文を批判的な立場からきちんと読みなおした著者はエラい。飢饉の原因は食糧不足ではなくその不公正な分配である、とアマルティア・センらも指摘しているが、原因と結果を取り違えた議論によって命が奪われる現実にそうした議論の根本まで遡って対抗する本書は貴重。