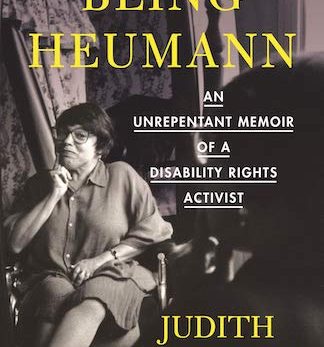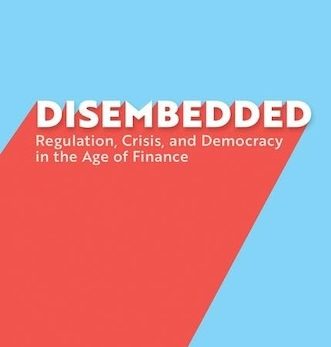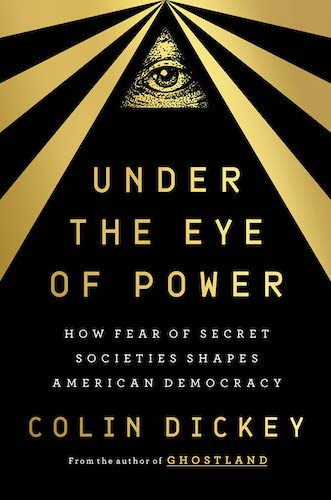
Colin Dickey著「Under the Eye of Power: How Fear of Secret Societies Shapes American Democracy」
アメリカの政治において「秘密結社による陰謀」を訴える陰謀論が独立宣言から2021年1月の議事堂占拠事件まで歴史的にどのような影響を与えてきたのか指し示す本。
著者が言いたいのは、陰謀論はアメリカの歴史において重要な場面において必ず発生し大きな影響を持ってきたのであり、ことさら近年突然影響力を持ったわけではない、ということ。右派のあいだでは民族的・宗教的マイノリティなどに対する偏見を元とした荒唐無稽な陰謀論が広まりやすいのに対して左派のあいだでは実際に存在する権力者による横暴を誇張するタイプの陰謀論が広まりやすいという違いはあるものの、独立戦争の時代にワシントンをはじめとする「建国の父」たちがイギリス王政の失政を勝手に大掛かりな陰謀論に拡大解釈してしまった例から、ジョン・アダムスのフェデラリスト党とトマス・ジェファーソンの民主共和党や南北戦争のときの南北双方が相手側の背後に巨大な秘密結社的な陰謀を見出した話などに見られるように、さまざまな政治的立場の人たちが陰謀論に魅了される。歴史的な事例とともに、フリーメーソンやイルミナティがどのようにして大規模な陰謀組織として妄想され、そしてのちの陰謀論のネタ元となったのかという指摘はおもしろい。
おもしろいで済まないのは、反ユダヤ人主義や反カトリックの陰謀論が現代でもシャーロッツヴィルの右派集会やFOXニュースで叫ばれている「リプレイスメント理論」やQアノンが拡散する、民主党やハリウッドによる大規模な子どもの性虐待ネットワークなどの陰謀論に形を変えて大きな影響を持ち、さまざまな暴力事件や差別を巻き起こしている点。ユダヤ人がキリスト教国家としてのアメリカを破壊するために非白人の移民を流入させているという「リプレイスメント(置き換え)理論」やブラック・ライヴズ・マター運動はユダヤ人実業家がスポンサーしているという主張は、本来は所有者に従順なはずの黒人奴隷たちが逃亡したり反抗するのはユダヤ人やカトリックに扇動されているからだという南部の奴隷所有者たちの陰謀論と同じだし、子どもを虐待してアドレノクロムを採取しているというQアノンの主張は「ユダヤ人が儀式で飲むためにキリスト教徒の子どもを誘拐して血を抜いている」という陰謀論を元にしている。
著者によると、こうした陰謀論は古くはフランス革命など一部の人にとって複雑で理解し難い社会現象や政治的な変化を説明するために歴史上繰り返し発生するもので、それぞれの時代で偏見や差別の対象とされている集団(ユダヤ人、カトリック、トランスジェンダーなど)に対するモラル・パニックを巻き起こすが、それらは一時的に政治的な影響力を持つことがあっても、永続的な政治勢力となることはめったにない。たとえばアメリカ初の第三政党である「反フリーメーソン党」は長続きしなかったし、反移民・反カトリック運動の「ノウ・ナッシング」は各党のなかで活動しているうちは拡大したものの政党化に失敗して失速した。政治に進出した第二期クー・クラックス・クランや反共産主義的な陰謀論を訴えたジョン・バーチ・ソサエティも一時的に影響力は持ったものの、やはり一時的なモラル・パニックが終わると勢いを失った。
しかしそうした失速は、陰謀論が失敗に終わったことを意味しない。マイノリティに対するモラル・パニックを巻き起こす陰謀論の役割は現実に起きている、あるいは起きようとしているマイノリティの権利獲得を阻止することであり、マイノリティ運動の高まりやマイノリティ人口の増加に対する反発として生まれる陰謀論は変化を一定のあいだ押し止めることでその役割を終えて終焉していく。そしてほんの少し前に起きたモラル・パニックがすぐに忘れ去られることで、次のモラル・パニックが広がる頃には前回の教訓は失われ、また同じ構造で新しいマイノリティ集団に対する社会不安を糧に陰謀論が広められる。
オバマ大統領の出生や信仰を疑うことからはじまりコロナウイルス・パンデミックや大統領選挙についての世界規模な陰謀を拡散するまでに至った現代のQアノン周辺の陰謀論は、Mike Rothschild著「The Storm is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult, and Conspiracy Theory of Everything」がサブタイトルで「Conspiracy Theory of Everything」と描写しているように、これを信じなければいけない、という中心的な陰謀論が存在しないことが特異といえば特異だ。Qアノン運動の中ではあらゆる種類のそれぞれ矛盾する陰謀論が紛れ込んでいて、人々はそれぞれについて自分で調べ、考えるべきだ、とされている。ネットの雑多な情報や議論へのアクセスを前提としたインタラクティヴ・ゲーム的な参加様式は新しいが、しかし主軸の緩さや矛盾は現代の陰謀論に限った話ではない。たとえばユダヤ人はキリスト教徒から富を奪い支配している、という主張とユダヤ人は共産革命を起こし私有財産を否定しようとしている、という主張が同じ陰謀論のなかで共存していたりするのは、あらゆる不平や不満をユダヤ人による陰謀のせいにするという構図が反ユダヤ人主義陰謀論の本質であり、個々の陰謀論は現代だけでなく歴史的にも重要ではなかったことを示している。
陰謀論が大きな影響力を持っている現代のアメリカ政治の状況は決して例外的な状況ではないという指摘は、現にそうした陰謀論によって移民やトランスジェンダーの人たちの排除が進み、教育のなかで多様性や反差別を扱うことを禁じる動きが広がるなか、じゃあどうすればいいんだという絶望に繋がりかねないけど、とても興味深くはある。また本書はエピローグで、アメリカ政府がCIAやFBIを通して市民に対する違法薬物投与実験や市民団体の内紛や過激化を推し進め社会の対立を深めるような活動を行っていた事実が20世紀中盤以降次々と明らかにされたことが陰謀論が広まりやすい土壌をいっそう広めてしまったいっぽう、それらの存在を暴露したのは強い影響力と膨大なネットワークを持つ秘密結社などではなく民主主義を守ろうとした少数の一般市民からなる活動家やジャーナリストたちであったことを指摘し、かれらの活動を希望として提示する。